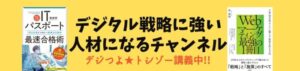 デジつよ|トシゾー講義中
デジつよ|トシゾー講義中みなさん、こんにちは。トシゾー【西俊明】です。
当ブログでは、ITパスポート試験や中小企業診断士試験の対策コンテンツを始め、みなさんのデジタル活用能力向上に役立つコンテンツを提供していきます。
YouTubeと連携し、わかりやすくて楽しいブログを目指しています。よろしくお願いします!
最新情報
2025年7月の情報処理技術者対策(FE/SG/IP)の最新トピックスは下記動画をご覧ください
チャンネルオーナー様専用ページ
アクセスにはパスワードが必要です。
ITパスポート試験
全ての社会人や学生が共通して備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。情報技術に加え、経営全般、プロジェクトマネジメントなど、ITを効果的かつ安全に活用するための幅広い知識を問います
動画だけで完全合格!合格パーフェクトパッケージ(完全無料)
ITパスポート試験に高得点で合格するために必要なコンテンツを8本の動画にまとめました。基本講義動画から過去問3年分、新シラバス用語解説、計算問題やプログラミング問題、直前対策まですべて揃っています。YouTubeでご視聴できるため完全無料です。ぜひご活用ください。
1番わかるオンライン講座
全76回のITパスポート基本講座です。市販のテキスト以上の充実した内容を噛み砕いてわかりやすく説明しています。
過去問解説
誤りの選択肢も含め、丁寧に説明しています。過去問学習で実践力を養いましょう。
絶対わかる擬似言語
私の講座の中でも特に評判の高い「擬似言語」の講座です。まったくゼロからでもすっきり理解できると嬉しい評価を多く頂いています。
コラム記事
ITパスポートに絡む様々なトピックスをご紹介しています
■
情報セキュリティマネジメント試験
組織全体における情報セキュリティの確保と継続的な改善を推進する人材向けの国家試験です。情報資産の管理・運用、リスク分析、情報セキュリティ関連の法令遵守、インシデント発生時の適切な対応など、実践的な知識が問われます
基本情報技術者試験
高度IT人材を目指す上で基本となる知識・技能を測る国家試験です。ITエンジニアに必要となる情報技術の基礎理論、開発技術、プロジェクトマネジメント、経営戦略などの幅広い知識と、それを活用する応用力が問われます
中小企業診断士試験
中小企業の経営課題を診断し、成長戦略の策定など具体的な助言を行う、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。財務・会計、人事、マーケティング、生産管理、法務、IT活用など、企業経営全般にわたる専門的で幅広い知識が求められます
中小企業診断士について
中小企業診断士の概要など基本的な事項について掲載しています。
中小企業診断士試験
中小企業診断士試験の勉強法ノウハウ等について発信しています。
教材・講座
中小企業診断士の教材・講座をレビューしています。
ワンポイントWeb講座
中小企業診断士1次試験7科目の講座内容を掲載しています。
診断士コラム
各種コラムを掲載
NEWS・トピックス
合格発表、試験日程など
■
関連資格
簿記
商業・工業会計の基礎を測る資格。経理・税務実務で必須。3級〜1級が設定されています
FP
個人資産管理の専門家。税金・保険・年金・投資を総合的に助言します。国家検定資格のFP技能士(3/2/1級)と民間資格のCFP/AFPがあります
宅建
不動産取引の国家資格。重要事項説明と契約書記名押印が可能です。合格率は15%~17%程度です。
行政書士
官公署提出書類や許認可手続を代理作成・提出できる法律系国家資格です。合格率約10%です
社労士
労働社会保険手続代行、就業規則作成、給与計算相談などを担う人事労務の国家資格です










