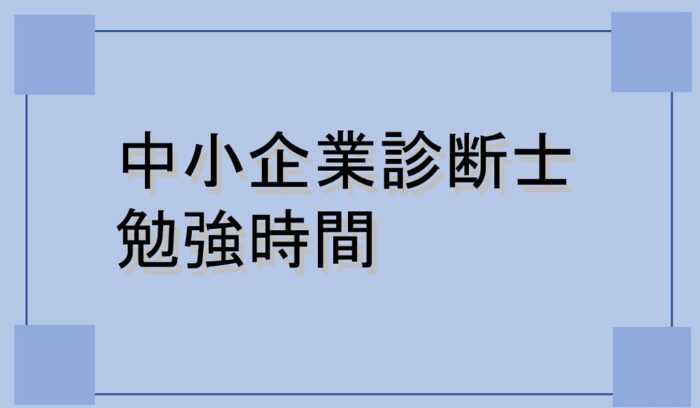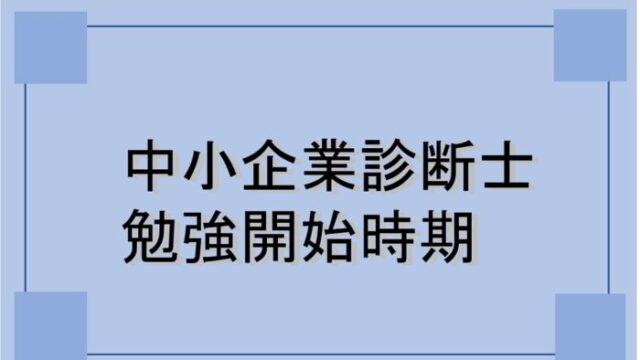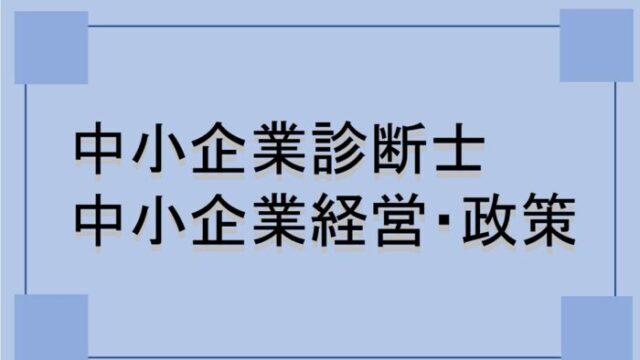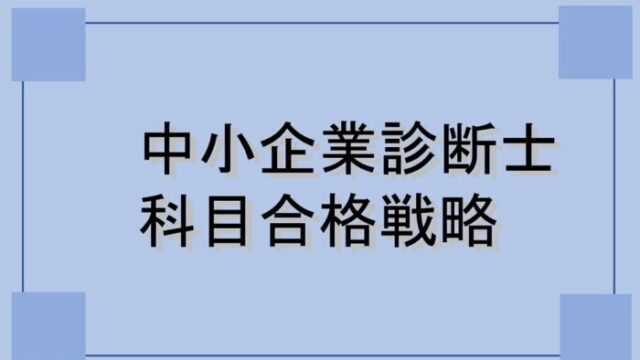こんにちは、トシゾーです。
中小企業診断士試験は科目数も多く、難易度は高い、と言われています。
そのため、初学者の方は
「いったい、合格までどれぐらい勉強時間が必要なの?」
と疑問が出てきますよね。
そこで、この記事では、科目別・一次/二次試験別など、目安(平均)となる勉強時間を分かりやすく説明します。
また合わせて、
「中小企業診断士の試験科目の勉強する順番」
「中小企業診断士の勉強開始時期は、いつがよいのか」
など、中小企業診断士の資格に興味のある方が、効率的に勉強するために気になる点についても、紹介します。
関心のある方は、ぜひ参考にしてください。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
書店で購入すると1,500円もする書籍が、なんと無料【0円】です。中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
中小企業診断士の勉強時間 実際は1,000~1,200時間程度
中小企業診断士は「日本版MBA」とも言われる資格試験であり、「民間の経営コンサルタントの唯一の国家資格」です。
非常に魅力ある資格ですが、そのぶん難関なため、合格までに必要な実際の勉強時間の目安(平均)は、1,000~1,200時間前後とされています。
ただし、これから勉強を始める初学者の方は、余裕をもって計画を立てるべきですから、効率的に勉強したとしても「1,200時間は必要」と考えたほうがよいでしょう。
1年を50週として、単純計算すると、
1,200時間÷50 = 24時間/週
1週間に20時間以上の学習が必要になります。
また、365で割ると1日あたりの勉強時間は約3時間20分。毎日3時間以上の勉強を1年も続けるイメージであり、決して簡単な道ではありません。土日に集中的に勉強するにしても、平日に2時間程度は必要でしょう。
効率よく工夫したり、モチベーションを高く持って集中したりすることが大切で、それが短期合格のコツになります。
なお、1,000~1,200時間というのは、一次試験・二次試験のすべてに対する勉強時間です。
配分としては、1次試験に1000時間、2次試験に200と考えており、合格を目指せる能力を養成するには、このぐらいの時間を費やす必要があると考えています。
※twitterでも多くの受験生が勉強時間について呟いていますが、やはり1,000~1,200時間程度という数字が一般的になっています。
中小企業診断士試験の勉強時間目安、1000時間っての見るけど、1000時間で足りる??笑
全然足りん気がするんだけど😂😂— はる@中小企業診断士勉強中🐭 (@Haru_Hiramoto) March 27, 2022
1,000時間。中小企業診断士資格の平均勉強時間。勉強したいと思ったのは新婚1年目。いつ合格できるか分からない。反対を覚悟で妻に相談。なんと「やりたいならやったら」と背中押してくれた。10ヶ月後に無事合格。あれから10年。コツコツ複業続けて副収入は年7桁に到達。あのときの妻の応援に感謝。
— やす (@yasulog2) April 2, 2022
中小企業診断士の一次試験 試験科目ごとの勉強時間の目安(内訳)
一次試験7科目、それぞれに必要な勉強時間を一覧すると次のとおりです。
- 経済学・経済政策:150時間
- 財務・会計:200時間
- 企業経営理論:150時間
- 運営管理:150時間
- 経営法務:100時間
- 経営情報システム:100時間
- 中小企業経営・中小企業政策:100時間
合計:全950時間
上のように合計950時間となっていますが、予備をみて、1次試験トータルで1,000時間程度と考えましょう。
人によって必要な勉強時間の差は大きく変わる
とはいえ、科目ごとの時間配分は、それぞれの人の、得意分野・不得意分野と大きく関わってきます。
たとえば私(管理人)の場合は、前職がIT系企業のマーケティング部門でしたので、企業経営理論と経営情報システムには、あまり時間をかける必要はありませんでした。
銀行員や経理部の方、簿記資格をすでにお持ちの方は、財務会計の習得の時間を大きく削減できるしょうし、大学で法律を学んだ方の場合、経営法務の勉強時間を短縮できるでしょう。
受験者ごとに、これまで経験した業種や職種、出身大学および学部、保有資格など、経歴やバックグラウンドは多種多様。
それらとの関連性から、自ずと得意・不得意な知識が決まってしまうのです。
自分の実力を把握した上で、効率的な学習で得意な科目の勉強時間を短縮し、不得意科目に使える時間を捻出するような計画を立てるとよいでしょう。
以下、それぞれの科目について、上記の勉強時間が必要となる要因を説明します。
財務・会計の勉強時間:
財務会計は、1次試験7科目中で最長の200時間が目安(平均)となります。
簿記のマスターから始まり、広範な範囲において一つずつ基礎の理解を積み上げていき、かつ、手を動かして正しい解を導き出せるよう、反復して学習しなければ合格できません。
財務・会計は2次試験にも相当深い関係がありますし、中小企業診断士試験に合格において、最大のカギとなる科目といえます。
企業経営理論、運営管理の勉強時間:
企業経営理論と運営管理も、財務・会計と同様、1次試験だけでなく2次試験にも深い関連のある科目です。
また、どちらの科目も、出題範囲が広範です。さらに、単なる暗記だけでなく、理解して覚えなければ得点に結びつかない点も、財務・会計と同様です。
ただし、財務・会計ほど理解を積み上げるものではありません。その分、財務・会計よりは勉強時間が短く150時間程度ですむことになります。
経済学・経済政策の勉強時間:
経済学・経済政策は、ほとんど二次試験には関係のない科目です。ただし、単なる暗記では得点できない、積み上げ式の理解が必要な科目です。
そのため、他の暗記科目よりは勉強時間が必要となります。
経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策の勉強時間:
経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策の3科目は、暗記中心の学習で合格レベルに到達することができます。
経営法務と中小企業経営・中小企業政策は、二次試験との関連は薄いので、一次対策と割り切って、出題されそうな点を中心に勉強を進めるのがよいでしょう。
経営情報システムは、一部、二次試験に関連してきますが、二次試験への対応は暗記するような内容ではありません。二次試験では、事例企業に対し、課題解決策の一つとしてどのようなソリューション(システム)を導入すべきか、その提案力が問われます。
注意点としては、二次試験の過去問を解く際に、
「事例企業に対し、どのような場合に、どのようなソリューションが有効か」
という考え方を整理するのがよいでしょう。
上の3科目は、あまり深入りせずに、合格レベルの得点力を目指すことが必須です。
中小企業診断士の二次試験 勉強時間の目安
二次試験の勉強時間は、200時間程度と考えてください。
二次試験には、以下の4科目(事例)がありますが、それぞれを5年分×3周すると、計60回ほど事例問題を解くことになります。
200時間の中で事例を60回解くペースとしては、1回につき3時間と20分が使える計算になります。
問題を解く時間は本試験と同じ80分間(1時間20分)を制限とし、残りの2時間で採点および解説の確認を行う、といったスケジュール感で実施しましょう。
1つアドバイスをしたいのは、一発合格を狙う方は、一次試験前から二次試験の対策を始めておくべき、ということ。
なぜなら、1次試験の合格発表後~2次試験までは日程が短く、1日1事例を解いても間に合わないからです。
そこで、過去3年~5年間分(1周目の分)を、1次試験の前にもやっておくことが重要です。とは言え、一次試験直前には、そんな余裕はないでしょうから、春ごろからコツコツやっておくのがオススメです。
マークシートで暗記中心の一次試験と違い、二次試験は思考力を問う試験です。部分点も取れるので、早い段階から少しずつ対策するほうが有利ですよ。
中小企業診断士の勉強時間 最短では500時間未満の知人がいた
ここまで、一次試験・二次試験の科目別の勉強時間の内訳をみてきましたが、最短(最低)では、どれぐらいで合格できるのでしょうか。
私の知人では、4月末(GWの始まり)から試験勉強を始めて、その年の二次試験までストレート合格された方がいます。
正味の勉強時間を聞くと、「500時間を少し切るぐらい」とのことでした。
ただ、この方は、もともと経理職の方であり、財務・会計について、最初から多くの専門知識をお持ちでした。
財務・会計以外でも、あなたの専門分野が、中小企業診断士試験の科目と重なっていれば、その分、勉強時間を短縮できることになるでしょう。
中小企業診断士試験の合格に必要な年数は?
平均受験回数は約3回
中小企業診断士試験の平均的な受験回数は3回程度となります。年に1回しか試験は実施されませんから、受験生の平均勉強期間は3年となる計算です。
とはいえ、現実には合格を手にすることが出来ずに諦めてしまう人も多いです。数年間、地道な努力を継続できるのであれば決して無理な目標ではありませんが、物理的・精神的に、それが如何に難しい目標であるかは、留意しておくべきでしょう。
働きながら受験する方が多い
中小企業診断士の合格者のボリュームゾーンは30代・40代となっています。そして、これらの方のうち、ほとんどが職業に付いている方です。
つまり、中小企業診断士試験は「働きながら合格できる試験」といえますが、一方で、働きながらだと、常に必要な勉強時間が確保できるとは限りません。
そのため、無理して1年でストレート合格しようとせず、戦略的に2年計画(複数年計画)を実行する方も多くいます。
家族のサポートも必須となるでしょう。
2年計画(複数年計画)を実行する
1年間でストレート合格できるのであれば、それが最も望ましいのは間違いありません。
資格スクール各社の宣伝の結果、巷には「中小企業診断士試験は1年間でストレート合格を目指そう!」という言説で溢れています。
しかし、仕事や家庭の都合などで、十分な時間が取れない人が多いのも現実。
そうであっても、焦る必要は全くありません。
診断士試験の合格を、無理せず計画的に進めるため、2年計画を立案し、実行することがおすすめです。
たとえ1年では難しくとも、2年計画を実行すれば余裕を持って中小企業診断士試験の対策ができるはずです。
中小企業診断士試験の2年計画について詳しくは、下記記事を参考にしてください。
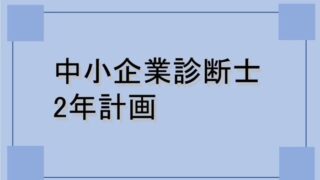
科目合格制度を使った戦略も重要
2年計画を実行するのであれば、科目合格制度を戦略的に狙って活用することが必要です。
ただ、科目合格制度には少し注意すべき点があり、メリットだけでなく、単純に「1年目に合格した科目を全て免除した結果、むしろ不利になってしまう」場合もあります。
各科目は毎年一定の難易度ではなく、年度ごとに難易度が変化する点も、科目合格戦略を立てにくい要因の一つです。
科目合格については、同制度を細かく調べ、メリットだけでなくデメリットなどついても検討・執筆した「最強の科目合格戦略」の記事を、ぜひ参考にしてください。

忙しい社会人はオンライン通信講座の利用も検討する
社会人で忙しい受験生は、隙間時間を使って学びを深めることができるオンライン通信講座を利用する手もあります。
診断士は難関試験のため、通信スクールにもよりますが、複数年度をサポートするコースも少なくない状況です。動画配信をベースにしたものが多いですが、音声の聞き流しなど、様々なメディアに対応するなど、幅広い視聴環境から選べます。
全体として通学コースよりかなりコスパがよいですから、一度検討してみてはいかがでしょうか。
勉強のスケジュールの順番は
資格受験校LECでは、一次試験7科目のスケジュールを以下の順番で学習します。
- 第1科目:企業経営理論(戦略、組織、マーケ)
- 第2科目:運営管理(生産、販売・店舗)
- 第3科目:財務会計
- 第4科目:経済学/経済政策
- 第5科目:経営法務
- 第6科目:経営情報システム
- 第7科目:中小企業経営/中小企業政策
LECに限らず、他の受験校や通信講座のスケジュールも、多少の前後はあれ、だいたい、このような順序で学習します。
理由としては、暗記中心の科目(経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策)は、できるだけ後で学習し、理解が必要な科目は早い段階から学習する、という考え方をしているためです。
さらに、しっかり理解することが必要な科目の中でも、中小企業診断士の基本となる企業経営理論は、ほぼすべての講座が、一番に学習します。
もし、あなたが独学をされる場合でも、このような学習の順番は、必ず参考にして欲しいと思います。
勉強開始時期 おすすめは?
「試験の学習は、いつから開始するべきですか?」
という質問を、時々受けることがあります。
これには、様々な意見があり、
- 翌年のストレート合格を目指し、9月から10月頃に開始する
- 科目合格制度を使って2年計画で合格を目指すため、4月から5月に開始する
などが代表的な意見です。
しかし、私の考えるおすすめの勉強開始時期は「中小企業診断士になりたい!と、思った時に始める」というもの。
このことに関しては、別の記事でくわしく説明しています。よろしければチェックしてみてください。
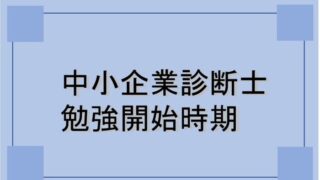
難易度や勉強時間を他の国家資格と比較
勉強時間から見た難易度
著名な士業について、資格取得までの目安時間を調べてみました。
- 弁護士(司法試験および予備試験):約6,000時間
- 公認会計士:約3,000時間
- 司法書士:約3,000時間
- 弁理士:約3,000時間
- 税理士:約2,500時間
- 社会保険労務士(社労士):約1,000時間
- 行政書士:約500~800時間
- 宅地建物取引士(宅建士):約300時間
表では、目安となる勉強時間が長い順に並べていますが、弁護士(司法試験)が突出しているのが明確です。
また、弁護士~税理士までの資格は「働きながら取るのが難しい」と言われたりしますが、確かに2,500~6,000時間も必要だとすると、勉強に専念するほうが現実的かも知れません。
逆に言えば、勉強時間が1,000時間超の中小企業診断士や社会保険労務士(社労士)、行政書士ぐらいまでが、現実的に働きながら取得することが可能な資格といえるでしょう。
※中小企業診断士試験の難易度については、下記の記事も参考にしてみてください。
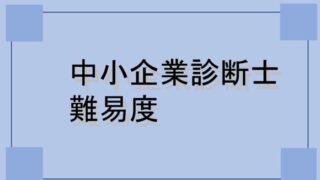
試験の概要(特徴)
勉強時間や勉強開始時期などを検討するためには、試験日程を押さえておく必要があります。
ここでは、試験日程を中心に、試験制度の各項目を確認しておきましょう。
1次試験の概要(特徴)
受験資格
誰でも受験可能(年齢、学歴、国籍による制限はありません)
試験方式
マークシート方式、7科目(各科目の配点:100点満点)
受験手数料
14,500円
合格基準(合格点)
総点数の6割(60%)以上であって、かつ1科目でも満点の4割未満のないこと
1次試験 実施スケジュール(試験日)
- 申込受付(出願):5月~6月上旬
- 試験実施:8月上旬(土曜日・日曜日の2日間)※2021年度は五輪実施のため8月下旬実施でした
- 解答発表:試験終了後、数日以内に中小企業診断協会のwebサイトで公開
- 合格発表:9月上旬
合格率
近年は30~40%程度
合格者数
近年は4,000~5,000人程度で推移
2次試験の概要(特徴)
受験資格
当年、および前年に一次試験に合格した者
試験形式
筆記試験: 事例Ⅰ~事例Ⅳの計4科目(与件の設問に答える記述形式、各科目の配点:100点満点)
口述試験: 面接の実施(約10分)
受験手数料
17,800円
合格基準(合格点)
筆記試験が満点の6割(60%)以上、加えて、1科目でも4割未満がないこと。筆記試験合格者のみが受験する口述試験では、評定が6割以上の者
実施スケジュール(試験日)
- 出願期間:8月下旬から9月中旬
- 筆記試験実施:10月下旬の日曜日 ※第3日曜日が多い
- 筆記試験合格発表:12月上旬
- 口述試験実施:12月中旬の日曜日
- 口述試験合格発表:12月下旬
合格率
20%程度
合格者数
例年、900人前後
実務補習・実務従事
中小企業診断士は、「民間の経営コンサルタントの国家資格」と位置づけられています。
そのため、合格した後に、コンサルティングの実務経験が義務づけられています。
具体的には、登録申請をする前3年以内に実務補習を15日間以上受けるか、診断実務(実務従事)を15日間以上実施することが必要です。
- 登録専門機関が実施する実務補習を受講する(15日間以上)
- 一定の条件を充たす実務に従事する(15日間以上)
「実務補習」と「実務従事」について詳細は、下記記事をご覧ください。
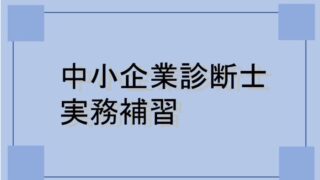
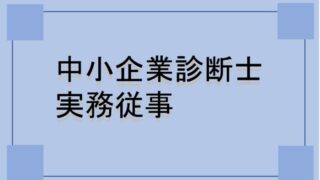
最短の勉強時間で合格するための勉強方法
難関国家資格試験に合格するための勉強法のポイントは以下のとおりです。
- 100点を目指してはいけない(診断士の場合、合格基準+10点の70点を目指す)
- テキスト等のインプット学習に時間を使い過ぎない
- 過去問題集を徹底活用したアウトプット学習に時間を使う
- 細かいセクション毎に【テキスト→過去問】の反復を繰り返し、何回も回す
ポイントは、テキストと過去問の時間配分の使い方です。
テキストのインプットの量が多くなり過ぎて、アウトプット演習が不足するのが、一番悪いケース。
過去問を何度も反復しながら分からない点はテキストに戻り、疑問点を潰す。この繰り返しで基本的な問題を取りこぼさないようになれば、自然と合格は見えてくるでしょう。
復習こそ、最短合格のための秘密兵器!
カナダのウォータールー大学によると、以下のよう実験結果が得られたとのこと。
- 講義を1時間ほど実施したあと、1日(24h)以内に10分間の復習をすると、100%記憶が甦る
- 講義の1週間後に、再度、5分間だけ復習をすると、また知識を思い出すことができる
- さらに、1カ月後に数分だけ復習すると、三度(みたび)完全に思い出すことができる
- まったく復習しない場合、1ヶ月でほぼ全ての記憶を忘却してしまう(記憶が定着しない)。
参考:https://the-owner.jp/archives/6006
この実験結果は「いかに復習が効果的であるか」を如実に表しています。毎日学習したことを、翌日わずかな時間復習することで完全に思い出すことができるのです。
そして1週間後、1ヶ月後に、わずかな時間繰り返すことにより、あなたの覚えた知識は、スムーズに長期記憶へ移行され、定着するでしょう。
こんなに効率のよい勉強術は他にありません。ぜひ毎日の復習を徹底してください。
一次試験の勉強方法
一次試験の勉強方法について、さらに詳しく知りたい方は、下記の「一次試験 完全合格マニュアル」をチェックしてみてください。
1次試験は全問マークシート方式で、記述式の2次に比べ、取り組みやすいですが、決して難易度が低いわけではありません。丸暗記で覚えるのではなく、しっかり理解してから覚えるようにしましょう。
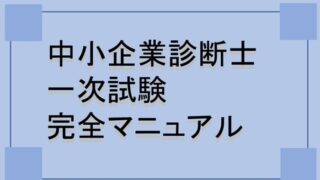
二次試験の勉強方法
二次試験の勉強方法については、下記の記事をチェックしてください。
2次試験対策のポイントは過去問を徹底的に演習することです。4つの事例問題について過去問の回答を作成した後、採点したうえで自身の課題を抽出して把握する。その繰り返しで実力が養成されていきます。

独学より通信講座のほうが勉強時間を短縮できる
多忙な受験生ほど資格スクールに通学する時間が取れないので「独学で頑張る!」と考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、中小企業診断士は働きながら独学で取得できない資格ではありません。優秀な方ほど、「仕事しながら独学でも何とかなるでしょ!」と考える傾向にあるようです。
ただし、独学だと以下2つの要因により、どうしても時間がかかります。
- 学習計画や教材選びに時間が必要
- 経営戦略・財務会計など難しいテキストを読んで理解するまで一定の時間がかかる
もし、あなたが当初から「数年かけてコツコツ頑張る」というのなら、独学でも良いでしょう。
しかし、
「合格には1,000時間必要なのはわかったけど、仕事も忙しいので、少しでも勉強時間を短縮したい!」
と考えるのであれば、通勤通学や外出時などのスキマ時間を徹底活用でき、コストパフォーマンスも高い「スマホ動画対応通信講座」の利用をおすすめします。
というのも、
- スマホ対応の動画で、いつでもどこでも、スキマ時間を使って学べる
- テレビやYouTubeの番組を見ている感覚で、リラックスしながら知識を覚えられる
- 大手スクール並みの、質の高い専門講師の講義やカリキュラムを受講できる
など、それらの講座は進化した学習環境となっているからです。
テキストを読むより、かみ砕いて説明してくれる動画講義の方が理解が早いですし、何よりスキマ時間を徹底活用すれば、机に向かって勉強する時間は大きく削減できます。
現在ではスマホ対応講座は多くありますが、5万円台から受講できる「スタディング」と「診断士ゼミナール」が、品質の高さと価格の安さにおいて、他の講座より頭一つ抜き出ています。
どちらを選んでも間違いはないので、気になる方は「スタディング中小企業診断士講座の口コミ・評判」と「診断士ゼミナールの口コミ・評判」の記事をチェックしてみてくださいね。


各講座の公式ページをチェックしたい方は、以下からどうぞ(無料で体験できる動画講座などが提供されています)。
まとめ
ここまで、合格に必要な勉強時間について、くわしく説明してきました。
あなたが将来独立するにしても、現在の会社でキャリアを重ねるにしても、中小企業診断士の資格は、十分に大きな力になることは間違いありません。
ぜひ、将来のためにも、適切な勉強方法を選択して、楽しみながら勉強を進めてほしいと思います。
なお、中小企業診断士の独学で利用するテキストや問題集などについては、下記の記事を参考にしてください。

| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |