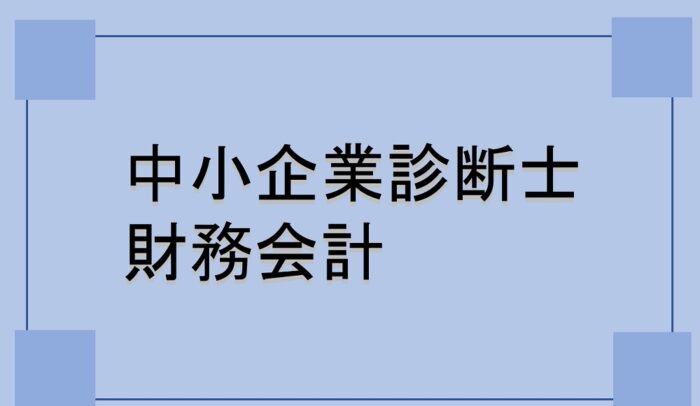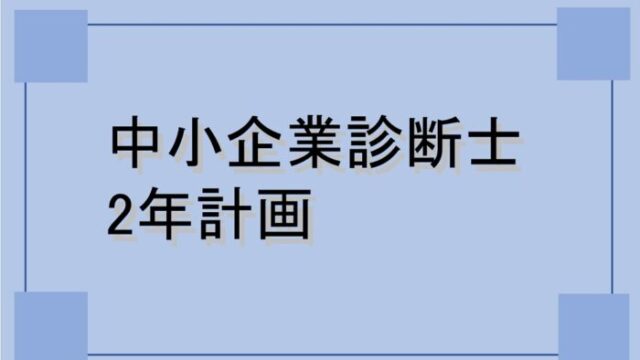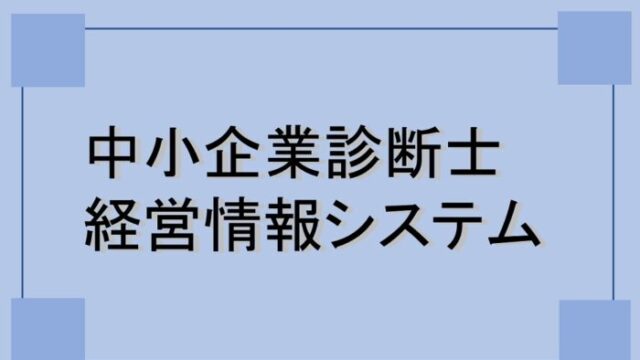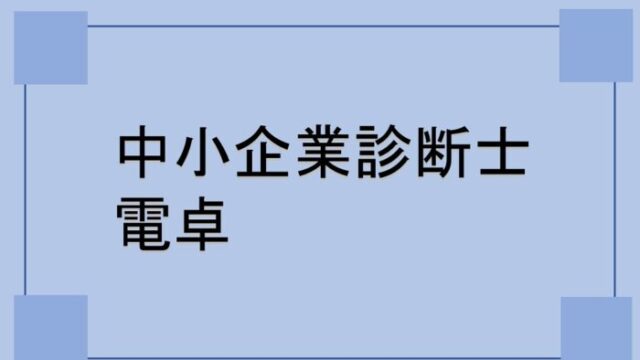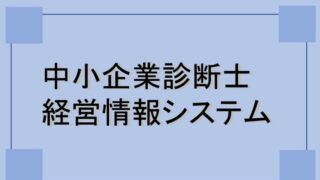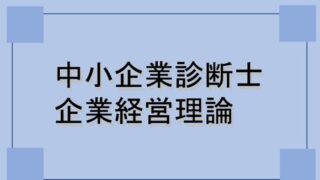こんにちは、トシゾーです。
今回は、財務会計の勉強法についての記事です。
財務会計では、企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、カネ(資金)に関する様々な経営理論を学びます。
私は、前職ではIT系の企業でマーケティング部門に所属していました。
それまでまったく財務・会計などに縁がなく、学ぶことも無かったので知識ゼロからのスタートでした。そのため、財務・会計の科目に対しては、正直、苦手意識を持っていました。
私のように、実際、財務会計に縁のなかった方の中には、数字に苦手意識を持っている方も多いでしょう。
しかし、基礎からきちんとやっていけば必ずマスターできますし、ゲームみたいにコツコツやるのが性に合っている方は、得意科目にすることも出来るかも知れません。
食わず嫌いをする前に、財務会計の概要や傾向などを見ていきましょう。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
財務会計 科目設置の目的
(科目設置の目的)
財務・会計に関する知識は企業経営の基本であり、また企業の現状把握や問題点の抽出において、財務諸表等による経営分析は重要な手法となる。また、今後、中小企業が資本市場から資金を調達したり、成長戦略の一環として他社の買収等を行うケースが増大することが考えられることから、割引キャッシュフローの手法を活用した投資評価や、企業価値の算定等に関する知識を身につける必要もある。このため、企業の財務・会計について、以下の内容を中心に知識を判定する。
やはり、お金の問題は中小企業にとって非常に大切ですし、そのためのスキルは中小企業診断士として当然持っておくべきですよね。そうしたスキルを身に着けることが目的です。
財務会計の科目には、いろいろ難しい用語も出て来ますが、1つずつマスターしていけば必要以上に怖れることはありません。
財務会計 科目の位置づけ
財務会計の科目は数字面における企業経営の基本理論です。
中小企業診断士は経営コンサルタントとして、企業の経営者に対し、「会社の血液」である資金の流れを分析し、経営診断やアドバイスをすることが必要です。
あなたが経営者のよきパートナーとなるために、「企業経営理論」の科目とともに、もっとも重要な科目と位置付けられる、といえるでしょう。
財務会計 科目の内容
試験案内に書かれた財務会計の出題内容を一覧すると、次のようになります。
- 簿記の基礎
- 企業会計の基礎
- 原価計算
- 経営分析
- 利益と資金の管理
- キャッシュフロー
- 資金調達と配当政策
- 投資決定
- 証券投資論
- 企業価値
- デリバティブとリスク管理
- その他財務・会計に関する事項
引用:令和4年度中小企業診断士第1次試験案内
以上の内容は、大きく「アカウンティング(会計)」と「ファインアンス(財務)」に分かれます。
アカウンティング(会計)
会社のお金を集計したり分析したりする方法に関するものが会計です
会計では、簿記の知識を活用して集計を行い、貸借対照表【B/S】や損益計算書【P/L】、キャッシュフロー計算書【C/F】などの、いわゆる財務諸表を作成するところまでを行います。
また、財務諸表などの数値を用いて、経営分析する手法を問われます。
※なお、アカウンティングは、「制度会計」と「管理会計」の2つに大きく分けることができます。詳細については、以下の記事をチェックしてみてください。
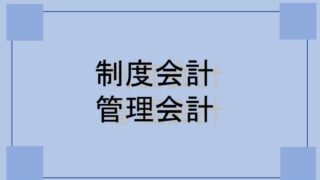
ファイナンス(財務)
ファイナンスとは、会社のお金を「いかに活用するか」に関する分野です。
ファイナンスでは、資金を調達する様々な方法を学んだり、株主に配当する手法などを学習します。
また、「どの投資案件が一番儲かるか」を計算し、効果が最大となるよう意思決定するための手法が問われます。
上記のほか、株価の評価方法など企業価値の算定方法も問われます。
試験時間と配点
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
財務会計 科目免除
財務会計の科目免除には、他の国家資格等保有による免除と、前年以前の科目合格による免除の2通りがあります。
他資格等保有による免除
- 公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者
- 税理士、税理士試験合格者、税理士試験免除者
- 弁護士または弁護士となる資格を有する者
引用:令和4年度中小企業診断士第1次試験案内
※上のとおり、簿記(簿記検定)は科目免除の対象になりません。
科目合格による免除
前年または前々年に財務会計の科目を受験して合格した場合、科目免除が申請可能となります。
※科目合格による科目免除について、詳細は以下の記事を参考にしてください。

財務会計の勉強方法
積み上げ型の学習で、丁寧に基本を理解していく
財務会計は単純に暗記すればよいのではなく、積み上げ型の学習が必要な科目です。つまり、手順を踏んで学ばないと理解ができません。そのため、独学の場合でも、基本的にテキストの順番にやっていくのがよいでしょう。
最初は時間が掛かっても良いので、丁寧にテキストを読んで理解していきましょう。分かったつもりになって曖昧なまま先に進むと、「どこが理解できていないのか分からない」という中途半端な状態となり、自信を持って解答できなくなります。
結果、最初からやり直すこととなり、却って時間が掛かる状況になります。特に学習初期の簿記の部分などは、効率のよさを考えすぎず、簡単と思える部分でもしっかり理解しながら進めることで記憶が定着するのは間違いありません。
一見遠回りでも、一つひとつ確認しながら対応することが大事であり、それが最短のスピードで財務会計をマスターすることにつながります。
手を動かして計算問題を解く
しかし、ただテキストを読んでいるだけでは駄目です。しっかりと手を動かして計算して、初めて身につきます。頭で理解したつもりになっているだけでは、いざ本番ではなかなか手が動いてくれません。結果、「試験時間が足りない!」というようなことになってしまいます。
多くの過去問や問題集の問題演習をこなしておくことにより、問題を見るだけで解き方がイメージできるようになります。
1次試験では電卓持ち込み不可、2次試験は持ち込み可
ちなみに、1次試験では電卓を持ち込めません。つまり、手で計算できるレベルの問題しか出題されません(あまり細かすぎる数値ではない)。だからと言って安心せずに、しっかり手を動かして問題を解く練習をしておきましょう。
なお、2次試験は電卓の持ち込みは可能です。診断士2次試験で使う電卓の選び方・有利な活用方法などについては、下記記事を参考にしてください。
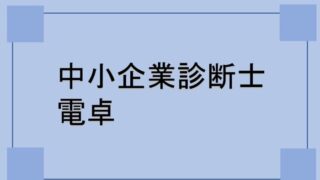
財務会計の勉強時間
私のような財務会計の初心者は、他の暗記系科目の2倍ぐらい勉強時間がかかると考えたほうがよいです。
「他の暗記系科目」とは、経営情報システム、経営法務などを想定しています。それらの科目の共通の特徴には、暗記が中心ということに加え、
2次試験との関連が薄い
というものもあります。
つまり、ギリギリ足切りに引っ掛からない程度に集中的に暗記すれば、何とかなるものです(もちろん、全科目平均で60点以上取る必要はありますが)。
それに対し、財務会計は2次試験にも大きく関係します。ただでさえ範囲が広いのに、本質的に理解し、かつ、きちんと手を動かせて正しい解を導き出せなければ、合格できません。
具体的な時間のイメージを言うと
経営情報システムや経営法務が100時間であれば、財務会計は200時間
ということです。
逆に言えば、それだけ時間を使う、と最初から意識しておけば、変に焦る必要はありません。しっかり腰を据えてやることが、合格の秘訣だと考えています。
なお、中小企業診断士試験の勉強時間全般については、下記の記事を参考にしてください。

合格率から見た、財務会計の難易度
財務・会計の1次試験の難易度は、年度によってかなり上下します。
過去の科目別合格率をみると、他の科目は毎年平均15~20%程度なのですが、財務・会計は年度により、3.8%、4.1%、6.1%など、非常に難易度の高い年度が続出しています。
あなたが受験する年の難易度がどうなるかは、神のみぞ知る、ということであり、悩んだり考えこんだりしても仕方がありません。どんな問題が出題されても、「1問でも多く正しい解答をする」ということで、焦らずに日々の積み上げが重要です。
もっとも、財務会計の難易度が高くなることは、ある意味当たり前かも知れません。なぜなら、中小企業診断士試験の受験生には、税理士・銀行員・経理部員なども多数います。そのような人物と競う試験であるわけですから、当然、それ相応の内容になります。
また、社長にアドバイスして説得できるだけのレベルになる必要もあります。
初心者には「それだけのレベルアップが望まれる」と、心してかかるべきです。
財務会計 勉強のポイント・留意事項
初心者は先に簿記3級を取得した方がよい
簿記3級は、初学者の方でも、1週間程度でマスターできます。仕訳の仕組みや電卓を使った計算に慣れるため、最初に簿記3級を学習することをお勧めします。私も受験生の頃、財務会計の勉強の最初に、簿記3級の勉強をしました。受験にも合格し、基礎が身に着いただけでなく、財務・会計に対する苦手意識もなくなりました。
試験勉強時には、財務会計は後回しにしない
前述のとおり、財務会計は「積み上げ型学習」が必要な科目です。財務会計に限らず、苦手な科目は後回しにして、試験直前に暗記で乗り切ろう・・・と考える方がいます。
しかし、財務会計に限っては、直前の付け焼刃で何とかなるものではありません。
決して後回しにはせず、早い段階から計画的に学習しましょう。
受験時には「後回し」が重要(あまり1つの問題にこだわり過ぎない)
財務会計の1次試験の試験時間は60分です。範囲が広い割に試験時間は短く、計算問題などは、問題文を見た瞬間に手を動かす、ぐらいの感覚が必要です。
注意が必要なのは、悩ましい問題が出た時です。1つの問題にあまりこだわり過ぎるのはよくありません。たとえば、「1分以上考えても分からない場合は、次の問題へ進む」など、自分なりにルールを決め、そのとおりに実行することが重要。
分からなくて飛ばした問題は印をつけておき、最後の問題まで終了したら、あらためて後回しにした問題に手をつけるようにしましょう。
どうしても苦手な方は、TAC等の通学講座も検討してみる
TACなどの通学スクールには、財務会計の単発コースや短期コースなどが設定されていることがよくあります(一部、通信講座もあるようです)。それらを受講することで、体系的に学ぶことができます。TAC等大手スクールの講師は経験豊富で、受験生の悩みや質問に丁寧に答えてくれます。各論点を分かりやすく解説し、正解への道筋を示してくれるため、非常に有益です。
2次試験との関連
2次試験の事例4は、財務会計そのものの事例です。与件(問題文)に書かれたターゲット企業の財務諸表を見ながら、経営分析をしたり、経営アドバイスの案を考えたり、本当の経営コンサルタントの力を試されます。
2次試験できちんと成果を出すためにも、財務会計の勉強は付け焼刃ではなく、しっかり取り組む必要があります。
私の財務会計受験体験記
ここでは、私の受験体験記を記載します。
中小企業診断士と財務会計の資格試験は、多くの人にとって非常に重要なキャリアステップです。これらの試験を突破するためには、適切な準備と戦略が必要です。ここでは、資格試験の内容や勉強法、受験生が抱える悩みについて解説し、成功への道筋を示します。
改めて、中小企業診断士の資格試験とは
中小企業診断士は、中小企業の経営に関するアドバイスを行う専門家です。この資格を取得することで、経営コンサルタントとしての仕事の幅が広がり、より多くの業務に携わることが可能になります。
財務会計の重要性
財務会計は、企業の経営状態を把握するための基本的なスキルです。収益性や損益分岐点などの指標を理解し、適切なマネジメントを行うためには欠かせません。中小企業診断士試験においても、財務会計の知識は必須となります。
試験突破のための勉強法
過去問の活用
試験を突破するためには、過去問を解くことが非常に重要です。過去問を解くことで、出題傾向や難易度を把握し、効率的に勉強を進めることができます。
YouTubeとブログの活用
最近では、YouTubeやブログなどのオンラインリソースを利用する受験生が増えています。これらのリソースを活用することで、自分のペースで学ぶことができ、疑問点をすぐに解消できます。
費用と時間の管理
資格試験の準備には、費用と時間がかかります。計画を立て、効率的に学習することで、これらのリソースを有効に活用できます。また、試験の費用対効果を考え、資格取得後のメリットを見据えることも重要です。中小企業診断士と財務会計の資格試験は、難易度が高いものの、しっかりとした準備と努力を重ねることで突破可能です。各受験生が自分に合った勉強法を見つけ、目指す資格を取得できることを願っています。コメント欄で皆さんの経験やアドバイスを共有し、共に学び合いましょう。
成功への第一歩は、まず始めることです。計画を立て、実行に移し、資格取得を目指して頑張りましょう。
中小企業診断士試験 財務会計 まとめ
初学者にとってはハードルの高い科目でもありますが、中小企業診断士として基本となる科目のため、確実に身につける必要があります。
また、多くの経営者は経理や数値を苦手としているため、財務会計的な指摘を適切に行えるコンサルタントは、頼りにされやすくなります。
繰り返しになりますが、財務・会計の科目は、やればやるだけ、きちんと理解できますし、確実に得点が伸びる科目です。そのことを意識して、直前まで学習に励みましょう!
中小企業診断士の通信講座おすすめは? ~独学にも使える、2023年最新版 比較・ランキング
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |