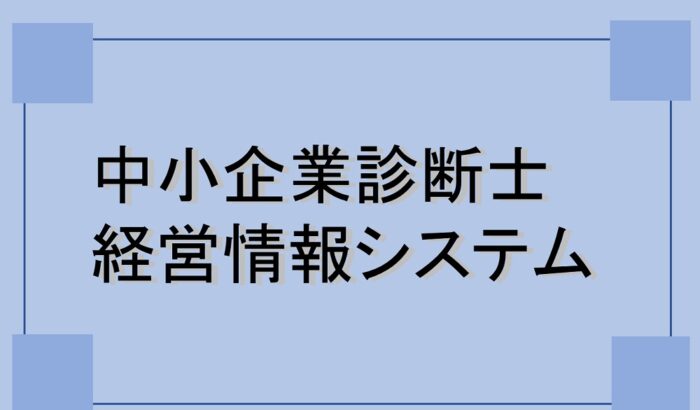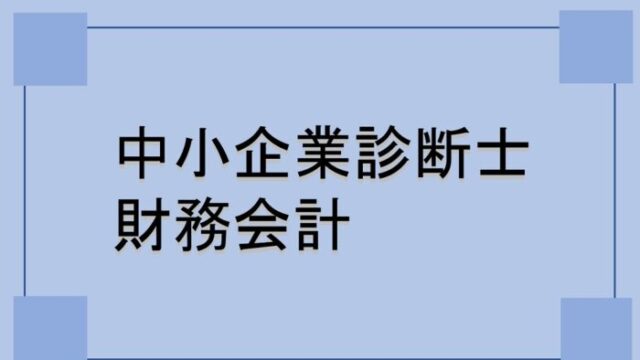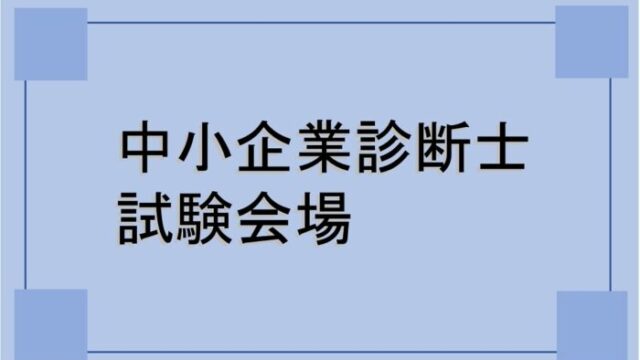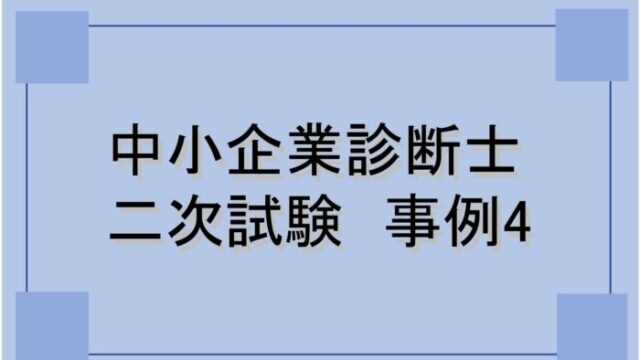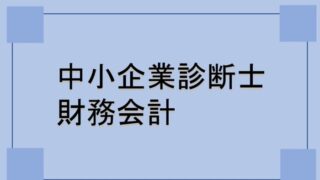こんにちは、トシゾーです。
経営情報システムは、いわゆるIT(情報技術)に関する科目です。
この科目の特徴として
得意科目とする人と、苦手意識がある人、大きく二つに分かれる(二極化する)
というものがあります。
私はというと、中小企業診断士試験の受験当時は、IT企業に勤務していましたので、もっとも得意とする科目でした。
実際、ITパスポートや基本情報技術者などの国家資格を持っていましたし、得点源の科目と考えていました。
しかし、銀行業務や経理業務などを始めとして、業務でITに関わってこなかった方には、苦手意識を持つ方も多いようです。
この記事では、そのような苦手意識を持つ方でも、経営情報システムの科目を突破できるような勉強法などについて書いていきます。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
中小企業診断士1次試験 経営情報システム 科目設置の目的
中小企業診断協会の試験案内には、科目設置の目的は次のとおり記載されています。
(科目設置の目的)
情報通信技術の発展、普及により、経営のあらゆる場面において情報システムの活用が重要となっており、情報通信技術に関する知識を身につける必要がある。また、情報システムを経営戦略・企業革新と結びつけ、経営資源として効果的に活用できるよう適切な助言を行うとともに、必要に応じて、情報システムに関する専門家に橋渡しを行うことが想定される。このため、経営情報システム全般について、以下の内容を中心に基礎的な知識を判定する。
現在では、中小企業と言えども、IT(情報技術)を抜きに企業経営を語ることはできません。
なぜなら、経営戦略や企業革新を実現するためには、「情報技術」という経営資源を効果的に活用することは欠かせないからです。
そのため、中小企業診断士は、経営の専門家として、一定のITに関する知見が必要です。
また、システム構築会社のようなITの専門家と、企業経営者の間に立ち、橋渡しをする役割も期待されています。
以上のような理由から、経営情報システムの科目が設置されているのです。
中小企業診断士1次試験 経営情報システム 科目の内容
経営情報システムは、「情報通信技術に関する基礎知識」「経営情報管理」の2つのテーマに分かれます。
情報通信技術に関する基礎知識
試験案内に記載の出題内容は、次の一覧のとおりです。
- 情報処理の基礎技術
- 情報処理の形態と関連技術
- データベースとファイル
- 通信ネットワーク
- システム性能
- その他情報通信技術に関する基礎的知識に関する事項
引用:令和4年度(2022年度)中小企業診断士第1次試験案内
ここでは、科目名のとおり、ITに関する基礎知識の有無を問われます。具体的には
コンピュータが動作する原理(2進数、ハードウェアやソフトウェアの詳細など)
コンピュータシステムの種類や関連技術(集中処理や分散処理、Webシステムなど)
データベースやファイル、データの種類や特徴(関係データベースなど各種の方式の概要など)
インターネットを始めとするネットワークの種類や特徴
などです。
純粋な技術的分野と考えてよいでしょう。なお、上記の一覧には書かれていないものの、「その他」のなかにはセキュリティ(情報セキュリティ)に関する論点も含まれます。
セキュリティは現在ITの使用において大変重要な論点であり、セキュリティの実務やサービスを適切に運用しない場合、会社が傾くほどの重大な結果に簡単に陥ることになりかねません。
そのため、例年、年を追うごとにセキュリティに関する問題は多く出題されるようになっています。
経営情報管理
試験案内に記載の出題内容は、次の一覧のとおりです。
- 経営戦略と情報システム
- 情報システムの開発
- 情報システムの運用管理
- 情報システムの評価
- 外部情報システム資源の活用
- 情報システムと意思決定
- その他経営情報管理に関する事項
引用:令和4年度(2022年度)中小企業診断士第1次試験案内
このテーマでは、ITを経営戦略でどう活かすか、という視点で、企業経営に利用する情報システムの種類や特徴について問われます。
その他、情報システムの開発に関する事項や、日々のシステム運用に関する事項、情報システムの開発や運用を外部委託をする際の考え方、情報システムの投資対評価の考え方などについても学びます。
試験時間と配点
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
経営情報システムの免除
経営情報システムの科目免除には、他資格等保有による免除と科目合格による免除の2通りがあります。
他資格等保有による科目免除
- 技術士(情報工学部門登録者に限る)、情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者
- 次の区分の情報処理技術者試験合格者(ITストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)
引用:令和4年度(2022年度)中小企業診断士第1次試験案内
※「ITパスポート」「基本情報技術者」「情報セキュリティマネジメント」は免除になりませんので注意してください。
科目合格による科目免除
前年または一昨年に、「経営情報システム」の受験および合格していれば、科目免除の申請が可能です。
※科目合格による科目免除について詳しくは、下記記事を参考にしてください。

中小企業診断士1次試験 経営情報システム 勉強のポイント(勉強法など)
経営情報システムの勉強法
経営情報システムの科目を苦手とする方は、まず、暗記科目だと割り切り、「足切りだけは回避する」と考えて対応することが、もっとも効率的です。
テキストを読んでいるだけでは、なかなかITやシステムの状況などをイメージしにくいですが、それらをイメージできるようになるには、かなりの学習時間が必要です。
具体的には、基本項目・頻出項目を中心に、単語カードなどを作成して、「覚えるべきことは覚える」と割り切った学習をする方が、より合格に近くなると思います。
経営情報システムの勉強時間
この科目が得意な方は、そもそも、ほとんど勉強しなくても、合格レベルにある方が多いです。そのような方は、テキストを一通り眺めながら、抜けている知識を確認するだけで大丈夫でしょう。十数時間~数十時間もあれば十分です。
苦手科目とする方も、他の科目との調整上、あまり時間をかけたくない科目です。そのため、できるだけ効率的に暗記しながら過去問や問題集を解くようにして、中小企業診断士の経営情報システムの勉強時間は100時間程度を上限(目標)と考えてスケジュール化することをおすすめします。
なお、中小企業診断士の勉強時間について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

経営情報システムの合格率から見る難易度
経営情報システムの過去8年間の科目合格率の推移は以下のとおりです。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 15.0% | 6.4% | 8.5% | 26.6% | 22.9% | 26.6% | 28.1% | 9.28% |
ご覧のとおり、中小企業診断士の経営情報システムの難易度は、年度によって大きく変わります。
最近は、合格率が高い傾向にありましたが、令和3年度は急激に難易度が上がりました。
この科目を苦手とする方が難易度の高い年度に受験した場合、足切り点の確保も難しくなる可能性があります。
複数年かけて科目合格を積み上げていく場合でも、経営情報システムの科目は、初年度から合格を狙いにいくことが必要です。
※中小企業診断士の難易度について詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。
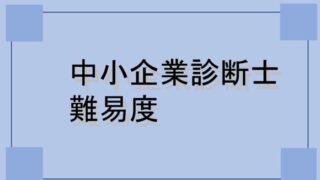
経営情報システムはITパスポートのテキスト(参考書)で学習する
「ITパスポート」とは、経済産業省の国家資格である「情報処理技術者試験」のうち、もっとも初心者向け、つまり入門的な位置づけの資格試験です。
そのため、経営情報システムが苦手な方には、格好の腕慣らしとなります。
ITパスポート試験の難易度は、経営情報システムより少し低いことに加え、受験者層が学生や若手ビジネスマンということもあり、圧倒的に分かりやすいテキストが多く販売されています。
ITパスポート試験の年間受験者数は20万人程度と市場規模が大きいため、市場競争が激しく、それが「分かりやすいテキスト」が多く発売される要因ともなっています。
そんなITパスポートのテキストの中では、以下がおすすめ。

「改訂6版 ITパスポート最速合格術」
※画像をタップするとAmazonのページに遷移します。
ITや情報システムに関連する内容を、「たこ焼き屋チェーンを運営する企業がIT化を推進する」という物語をベースに解説されるので、楽しみながら本書を読むだけで知識を定着させることがができます。
実は当ブログの管理人(私)が執筆したテキストですが、分かりやすさには絶対の自信を持っていますので、ぜひ書店でチェックしてみてください。
※また、ITが苦手な診断士受験生にITパスポートがおすすめな理由を、以下の記事ではくわしく説明しています。「なぜITパスポートを勉強すると効率的なのか」をしっかり理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
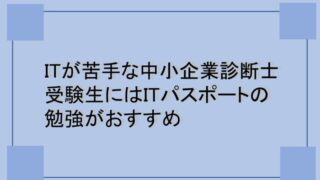
中小企業診断士1次試験 経営情報システム 勉強時の留意事項
統計・分析の問題には深入りしない
平成29年度までは、毎年2問(問題番号だと問24、問25)は、統計・分析の問題が出題されるのが定石でした。
具体的には、検定・コンジョイント分析・回帰分析などの知識やスキルが問われますが、これは非常に難易度が高く、専門的な訓練を受けた方以外は解答できないレベルの問題です。
そのため、仕事で深く関係している人など以外は、統計・分析の問題に対しては深入りしないことが大切です。
なお、平成30年・令和元年では出題傾向が変わり、それまでのような統計・分析の問題は見られなくなりました。
→その後、統計・分析の出題は復活し、令和2年は2問、令和3年は1問出題されました。
今後の傾向がどうなるのか分かりませんが、「難易度の高すぎる統計・分析には深入りしない」ことは押さえておきましょう。
ガイドラインの問題には深入りしない
毎年1問程度、情報処理技術に関するガイドラインなどからの出題があります。
マイナーなガイドラインから出題されることも多く、こちらも深入りしないほうが賢明です。
なお、令和3年度は以下のガイドラインについて出題されています。
- 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
少なくとも、数年以内に同じガイドラインから出題される可能性は極めて小さいでしょう。
最短で合格を目指すためには、定期的に出題される基本的な問題を中心に知識を固めていくようにしましょう。
ITが苦手な文系の方こそ、SQLを得意分野とすべき
SQL文はデータベースを操作するプログラム言語です。
プログラムと聞くと、ITが苦手な文系の方には「とても苦手で・・・」と尻込みする方が少なくありません。
しかし、SQL文は、ほぼ毎年出題されますし、型も決まり切っています。覚える用語も少なく、一度覚えてしまえば確実に得点源にできます。
ITが苦手な文系の方こそ、SQLをマスターして確実に点数を計算できるようにしてください。
普段から新聞やWebサイトの最新ITニュースをチェックするようにする
経営情報システムでは、科目の性格上、毎年数問は最新技術に関する論点が出題されます。
そうした論点の出題は難問奇問になる場合もありますが、一方で「用語の意味をなんとなく知っているだけで解答できるボーナス問題」が潜んでいる場合も間々あります。
たとえば、下記は平成29年の問8の選択肢アの内容です。
ア AR(拡張現実)とは人工知能技術を指し、これを Web サイトに組み込むこと
ができれば、顧客が Web サイトを通じて商品を購入する場合などの入力支援が
可能となる。引用:中小企業診断協会
これなどは、「人工知能といえばAIだ」という知識さえあれば、一瞬で不適切な選択肢と判定できる問題ですよね。
また、「第4次産業革命(インダストリー4.0)がドイツ発祥」という知識さえあれば、一瞬で判定できる出題がされたこともありました。
他にも、クラウド、IoT、ビッグデータなどは確実におさえておく必要があります。
上のように、最新技術に関しては、用語の正確な意味すら知らなくても判定できる場合がありますので、普段から是非、最新技術に関するニュースはチェックできる環境に身を置くようにしましょう。
※ビッグデータ関連用語についてくわしくは、下記動画をチェックしてみてください。
2次試験との関連
2次試験の事例では、ITや情報システムに関する詳細な知識は問われません。しかし、事例の問題文の与件企業に対する解決案を解答する際に、
〇〇のような情報システムを導入する
などのアイデアが求められるケースがあります。
つまり、各業種や職種の代表的なソリューション(問題解決を行うための情報システムの形態)を理解しておいた方が断然有利となります。
その対策としては、2次試験の過去問を解きながら、どのような業種に対して、どのようなソリューションが求められているのか、チェックするようにしましょう。
また普段から、あなたの勤務している企業や関連会社などで、どんな部署でどんな情報システムを活用しているのか、興味を持って知っておくことも役立つでしょう。
中小企業診断士の経営情報システム 私の受験体験談
ここでは、私が中小企業診断士の資格取得を目指していたころ、どのように経営情報システム科目を勉強していたかについて、私の受験体験談を共有したいと思います。このブログ記事を通じて、同じように中小企業診断士を目指す方々に少しでも参考になる情報を提供できれば幸いです。
1. 改めて、中小企業診断士の経営情報システムとは
中小企業診断士の試験科目の一つである経営情報システムは、企業の情報システムに関する知識や、ビジネスにおける情報技術の活用方法について問われる科目です。この科目は、企業の競争力を高めるためにどのように情報技術を利用するかを理解するために非常に重要です。
2. 試験準備の始まり
私が最初に手に取ったのは、過去問題集です。過去問題集は、試験の出題形式や難易度を把握するために非常に有効です。過去問題集を解きながら、どのような問題がよく出題されるのかを把握し、自分の弱点を見つけることができました。
過去問題集の利用方法
最初に全体を把握:まずは、過去問題集を一通り解いてみて、出題傾向や自分の理解度を確認しました。
- 重点的に復習:間違えた問題や理解が不十分な部分を重点的に復習しました。
- 繰り返し解く:何度も繰り返し問題を解くことで、知識を定着させました。
3. セミナーとオンラインコースの活用
試験勉強を進める中で、私はセミナーやオンラインコースも活用しました。特に、経営情報システムは専門的な知識が必要な科目であるため、専門家からのアドバイスは非常に役立ちました。
セミナーのメリット
- 専門家のアドバイス:現役の中小企業診断士やIT専門家から直接アドバイスを受けることができました。
- 最新情報の入手:情報技術は日々進化しているため、最新の知識をセミナーで得ることができました。
- 疑問点の解消:講師に直接質問することで、自分の疑問点をすぐに解消できました。
オンラインコースのメリット
- 自分のペースで学習:オンラインコースは、自分のペースで学習できるため、忙しい合間にも勉強を進めることができました。
- コースの多様性:さまざまなコースが用意されているため、自分に合った内容を選択することができました。
- 復習が容易:録画された講義を何度も視聴できるため、復習が容易でした。
4. 試験直前の準備
試験の直前には、最終確認として模擬試験を受けました。模擬試験は1次試験と同じく7科目全体を受けました。本番と同じ形式で出題されるため、試験の雰囲気を体験することができました。また、試験時間内に問題を解く練習にもなりました。
模擬試験の重要性
- 時間管理:試験時間内にすべての問題を解くための時間配分を練習しました。
- 本番のシミュレーション:本番の試験環境をシミュレーションすることで、緊張感を体験し、対策を立てることができました。
- 弱点の発見:模擬試験を通じて、自分の弱点を再確認し、直前に重点的に復習しました。
5. 試験当日の心得
試験当日は、できるだけリラックスして臨むことが大切です。経営情報システムは2日目ですが、私は前日の試験が終わった後、早めにベッドに入ってしっかりと睡眠をとり、試験当日は早めに会場に到着するようにしました。また、必要な持ち物を前日に準備し、忘れ物がないように気をつけました。
6. 試験結果とその後
試験結果が発表されるまでの期間は非常に緊張しましたが、無事に合格することができました。最終的に2次試験まで合格した後は、すぐに中小企業診断士としての活動を開始しました。資格を取得したことで、ビジネスの現場での診断やコンサルティングの仕事が増え、非常に充実した日々を送っています。
おわりに
中小企業診断士の経営情報システム科目の受験体験談を通じて、試験勉強の方法や対策についてお伝えしました。私の経験が、これから受験を目指す皆さんの参考になれば幸いです。中小企業診断士の資格取得は、決して簡単な道のりではありませんが、しっかりと準備をすれば必ず道は開けます。皆さんの成功を心から応援しています。
中小企業診断士の経営情報システム まとめ
ここまで見てきたとおり、経営情報システムには
ITに詳しくない人にとっては、イメージすることが難しい
年度により難易度の差が大きい
暗記中心科目だが、2次試験にも関連する
など、苦手意識を持つ方にとっては、扱いが難しい科目と思えるかも知れません。
しかし、この記事で書いたように、
暗記科目と割り切って、重要事項から暗記する
まずは分かりやすいITパスポートのテキストを読み、少しでも科目のイメージを持てるようにする
ことで、短時間で効率的に攻略することは可能です。
ぜひ、苦手意識のある方にも、がんばって頂きたいと思います。
■
経営情報システムの勉強法については本記事で説明しましたが、診断士試験全体の「最速勉強法」ノウハウについては、現在、資格スクールのクレアールが、市販の受験ノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、そちらもチェックしてみてください。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2023年最新版 比較・ランキング
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |