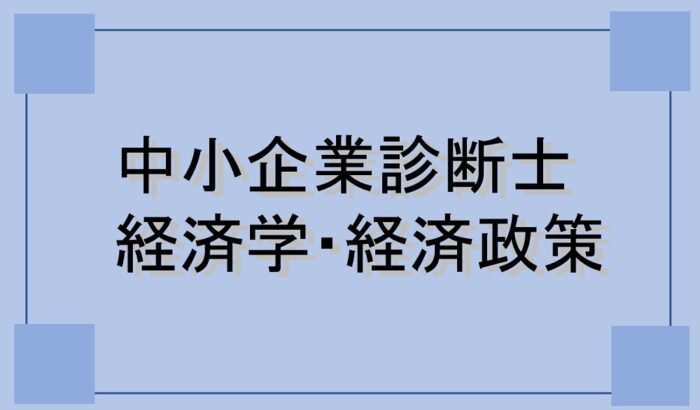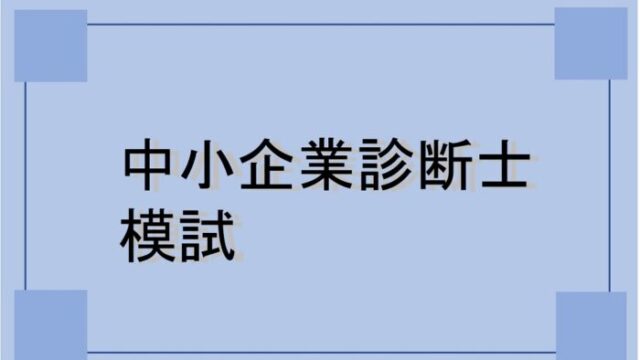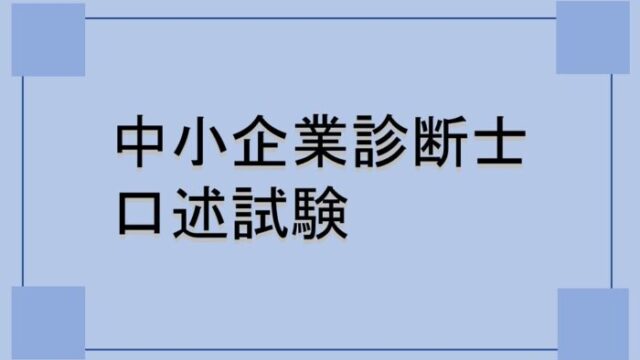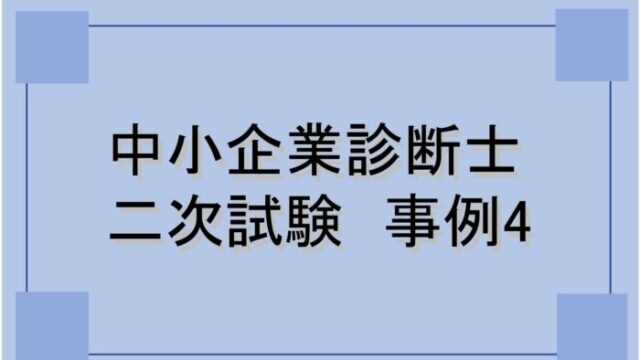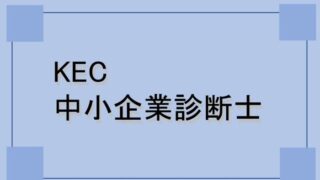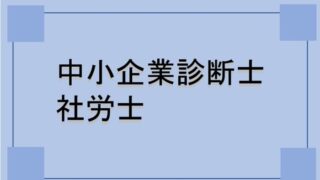経済学・経済政策は、苦手意識のある方が多い科目です。
大学で経済学や商学などを学んだ方以外は、これまであまり縁のなかった科目でしょうし、単純に暗記で乗り切れるものでもありません。
また、文系の科目ですが、数式やグラフを読み解くことも必要です。
以上のようなことが、多くの方が苦手意識を持ってしまう原因ではないでしょうか。
今回の記事では、苦手な方でも攻略できるような、経済学・経済政策の勉強法について書いていきます。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
経済学・経済政策 科目設置の目的(概要)
(科目設置の目的)
企業経営において、基本的なマクロ経済指標の動きを理解し、為替相場、国際収支、雇用・物価動向等を的確に把握することは、経営上の意思決定を行う際の基本である。また、経営戦略やマーケティング活動の成果を高め、他方で積極的な財務戦略を展開していくためには、ミクロ経済学の知識を身につけることも必要である。このため、経済学の主要理論及びそれに基づく経済政策について、以下の内容を中心に知識を判定する。
世の中の経済状況は、中小企業を取り巻く外部環境でもあります。中小企業診断士は経営コンサルタントとして、中小企業の経営に影響を与える経済状況をきちんと理解し、必要に応じて予測・分析できなければいけません。
それが、中小企業診断士試験に経済学・経済政策が設置されている目的と言えるでしょう。
経済学・経済政策 科目の内容
経済学・経済政策では、「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」について学習します。
経済学・経済政策の分野(その1) ミクロ経済学
「消費者や企業の行動が、どのような効果をもたらすのか」という観点から経済の動きを分析します。
中小企業診断協会が公表している「第一次試験案内」に科目の内容が書いてあります。そのうちミクロ経済学の出題範囲の内容の一覧は以下のとおりです。
- 市場メカニズム
- 市場と組織の経済学
- 消費者行動と需要曲線
- 企業行動と供給曲線
- 産業組織と競争促進
引用:令和4年度中小企業診断士第1次試験案内
経済学・経済政策の分野(その2) マクロ経済学
国全体や国同士の経済活動といった大きな(マクロな)観点から、経済状況を分析します。
中小企業診断協会が公表している「第一次試験案内」に科目の内容が書いてあります。そのうち、マクロ経済学の出題範囲の内容の一覧は以下のとおりです。
- 国民経済計算の基本的概念
- 主要経済指標の読み方
- 財政政策と金融政策
- 国際収支と為替相場
- 主要経済理論
引用:令和4年度中小企業診断士第1次試験案内
試験時間と配点
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
経済学・経済政策 科目免除
経済学・経済政策の科目免除には、次の2通りがあります。
他資格等保有による免除
- 大学等の経済学の教授、准教授・旧助教授(通算3年以上)
- 経済学博士
- 公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者
- 不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者
引用:令和4年度中小企業診断士第1次試験案内
科目合格による免除
前年または前々年に経済学・経済政策の科目を受験して合格している場合、科目免除を申請することができます。
※科目合格による科目免除の詳細は、以下をどうぞ。

経済学・経済政策 学習のポイント(勉強法など)
一次試験の経済学・経済政策 勉強法
経済学・経済政策は、単なる暗記の科目ではありません。順番に知識を積み上げて定着させることにより、初めて全体が理解できます。
そうした理由から、テキストで勉強する方は、きちんと順番にテキストを読み込んでいく必要があります。なかには、統計のグラフの読み方など難しい論点もあるので、できれば、通学や通信講座の講師が行う講義を受講(聴講)するほうが良いでしょう。
最初にテキストや講義でインプットした後は、過去問の問題集などを使用してアウトプット学習をすることが重要です。特に、比較的に頻出の傾向がある問題を繰り返し解けるようになることが、実力をアップさせるために必須です。
低い点数で悩み、得点を高く獲得できない人のほとんどが、アウトプット演習の不足によるものです。
高い得点での合格を目指している人は、アウトプット学習での解答を徹底的に繰り返し進めることが重要です。
しかし、独学だったり、どうしても理解できない場合は、下記の書籍などを参考にしてみてください。
「中小企業診断士のための経済学入門」
以下のアマゾンレビューが、この本のポイントを的確に表現しています。
診断士受験校の最大手TACで、長年「経済」を指導されている先生が書かれた本です。通年で学ぶ大学と違い、1ヵ月強でド素人を合格レベルに引き上げる訳ですから、「なぜ苦手に感じるか」をベースにした、「わかりやすい説明」なので安心です。
引用:Amazonカスタマーレビュー
中小企業診断士試験の受験プロが、「どうすれば診断士試験で合格できるか」を念頭において、最短で経済学のベースを仕上げる内容になっています。まず、本書で経済学の全体像をイメージして、それから詳細な論点をテキストで潰していくことが時短のポイントになります。
試験攻略入門塾 速習!マクロ経済学
こちらは、マクロ経済学の基本を、図表を使って非常に分かりやすく説明しています。さらに、無料の動画講義も視聴できるため、しっかり理解することが可能です。
アマゾンのレビュー37件中、81%が★5であり、診断士受験生の方もレビューを書いていました。こちら、以下に引用します。
某資格学校のテキストでは説明が不足しており、「なぜこうなるのだ?」という疑問を解決することができず、諦め気味で受験したH29試験。当然に不合格でした。
その後、こちらのレビューを見て『速習!マクロ・ミクロ経済学』のことを知り、両方とも購入のうえYouTube授業を受けました。石川先生の話し方はとてもわかりやすく、前年までの疑問が「なるほど」に変わったのを実感できました。おかげさまでH30試験では経済学合格でした。
H30試験では貯蓄投資バランスが出題されましたが、試験の最中、石川先生がお話されていた内容が頭に思い浮かび、迷うことなく正答を選ぶことができました。
レビューという形ではありますが、石川先生には感謝申し上げます。診断士試験を受験される方にはおすすめの本です。出典:Amazonカスタマーレビュー
試験攻略入門塾 速習!ミクロ経済学
前項の「試験攻略入門塾 速習!マクロ経済学」のミクロ版です。
こちらは、アマゾンレビュー33件中、79%が★5でした。もちろん、講義動画も視聴可能です。以下レビューから。
初版から約6年経っているが、今尚内容に不足は全くありません。
WEB動画視聴でのサポートも、
内容が理解できない=それは自分がどこかで諦めているだけ。と理解しても良いくらい充実しています。入門編とされていますが、本書を一通り理解することが出来れば、
再現は難しくとも、基本的な資格や大学試験の択一問題は確実に対応できる。そんな本です。
マクロも拝読しましたが、同様に素晴らしい。初版は2011年。
原発問題などが盛んに議論された年ですが、石川先生は今に至る経過や未来も一部言い当てています。
それもまた今読む(見る)と面白い。私自身、本書に出会ってから色んな学問に興味が出て、様々な学問に触れるたび
例えば今の生産工学もマーケティングも、基礎基本の考え方の源泉は経済学にある気がします。
購入以来繰り返し読んでいますが、そんな源泉の経済”学”とはなんたるかを知ることができます。マクロと併せてオススメです。間違いなく購入して勉強するに値します。
出典:Amazonカスタマーレビュー
経済学・経済政策 勉強時間
苦手な方が多い科目と言っても、二次試験に直接関係ない科目ですし、あまり時間をかけてはいられません。
ただし、前述のとおり、丸暗記で対応できる科目ではなく、知識を少しずつ積み重ねていく必要がありますので、それなりに時間がかかることも事実です。
中小企業診断士の経済学・経済政策の勉強時間は150時間を上限と考え、勉強する際は集中して理解できるように取り組みましょう。
なお、中小企業診断士の勉強時間の詳細については、以下の記事をチェックしてみてください。

経済学・経済政策 難易度
経済学・経済政策の過去8年の科目合格率は以下のとおりです。
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| 2.1% | 19.4% | 15.5% | 29.6% | 23.4% | 26.4% | 25.8% | 23.5% |
最近は安定していますが、実際には平成25年のように、年度により急激に難易度が上がることがあります。
たとえ、1次の各科目のなかで経済学・経済政策が得意だとしても、得点源と考えることには危険性があります。
足切りを避けることは前提として、60点取れればまずまず、と考えたほうがよいでしょう。
※中小企業診断士の難易度について詳細は、次の記事をご参考ください。
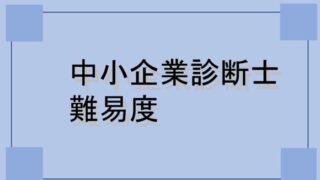
経済学・経済政策 学習時の注意事項
経済学・経済政策に力を入れ過ぎない
経済学・経済政策には、数学的な面白さがあります。
一部の方は、経済学・経済政策を勉強しているうちに、その面白さにハマってしまい、「経済学・経済政策を極めてみたい」と考えるようになります。
しかし、より上位の目的は「中小企業診断士の試験に合格すること」です。
経済学・経済政策で高得点を取れるのは喜ばしいことですが、必要以上に経済学・経済政策の学習に力をいれ、他の教科の学習がおろそかになっては本末転倒です。
経済学・経済政策の面白さにハマってしまっても、「極めるのは、中小企業診断士の取得後にしよう」と考え、受験勉強の時間を適切に配分してください。
一次試験の経済学・経済政策と、二次試験との関連
前述のとおり、経済学・経済政策は中小企業診断士の2次とは関連がありません。1次の突破だけを考え、できるだけ効率的な学習が必要といえます。
中小企業診断士の経済学 コンサルティングにどう役立つか?
この記事の最後に、中小企業診断士の資格取得を目指している方々に向けて、「経済学」科目がコンサルティング業務にどのように役立つかを私なりに分析した結果を詳しく解説します。経済学の知識は、ビジネスの現場で非常に重要であり、適切に活用することで企業の成長をサポートすることができます。
改めて経済学の重要性
経済学は、中小企業診断士の試験科目の一つであり、ビジネスの基盤を理解するために欠かせない知識です。
「経済学・経済政策の知識なんて経営コンサルティングでは使えないよ」
と思っている方がいるかも知れません。しかし、そんなことはありません。
経済学の知識を身に付けることで、市場の動向や経済政策の影響を理解し、企業の経営戦略に反映させることができます。これは、コンサルティング業務において非常に重要です。
経済学の実務への応用
中小企業診断士としての実務では、経済学の知識を活用する機会が多々あります。例えば、企業の収益性を分析する際には、需要と供給の関係や価格の弾力性を理解することが重要です。また、経済政策の変更が市場に与える影響を予測することで、企業に適切なアドバイスを提供することができます。
収益性の分析
企業の収益性を評価するためには、基本的な経済学の知識が役立ちます。需要曲線と供給曲線の交点で市場価格が決まるという基本的な概念を理解することで、価格設定や生産量の最適化を図ることができます。さらに、価格の弾力性を計算することで、価格変更が売上に与える影響を予測し、戦略的な意思決定をサポートします。
経済政策の影響
経済政策の変更は、企業のビジネス環境に大きな影響を与えます。例えば、2023年に実施される税制改革が企業に与える影響を分析する際には、経済学の知識が必要です。税制改革が消費者行動や企業の投資活動にどのような影響を与えるかを理解し、企業に対して適切な対応策を提案することが求められます。
試験準備のポイント
中小企業診断士の試験において、経済学は1次試験の重要な科目です。試験対策として、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
過去問題の活用
過去問題を解くことで、試験の出題傾向や問題形式を把握し、自分の弱点を見つけることができます。直前には、過去問題を繰り返し解いて、知識の確認と理解の定着を図ります。
セミナーの参加
経済学に関するセミナーに参加することで、専門家から最新の情報や実務に役立つ知識を得ることができます。また、他の受験生との情報交換を通じて、勉強の進め方や効果的な学習方法を学ぶことができます。
計算問題の練習
経済学の試験では、計算問題が出題されることが多いです。例えば、需要の価格弾力性や総費用の計算など、基本的な計算問題をしっかりと練習することが重要です。計算問題を解く際には、公式の暗記だけでなく、その背景にある理論を理解することが求められます。
経済学の知識を活用したコンサルティング
経済学の知識を活用することで、企業に対してより効果的なコンサルティングを提供することができます。例えば、市場分析や競争環境の評価、価格戦略の策定など、経済学の理論を基にした分析を行うことで、企業の経営戦略をサポートします。
市場分析
市場分析では、需要と供給の関係や市場の構造を理解することが重要です。経済学の知識を基に、市場の動向を予測し、企業が取るべき戦略を提案します。これにより、企業は市場での競争力を高め、持続的な成長を実現することができます。
競争環境の評価
競争環境の評価では、ポーターの五つの力モデルなどの経済学の理論を活用します。市場の競争強度や新規参入の脅威、代替品の圧力などを分析し、企業の競争力を評価します。これにより、企業は自社の強みと弱みを把握し、競争優位を築くための戦略を策定することができます。
終わりに
中小企業診断士の経済学科目は、コンサルティング業務において非常に重要な役割を果たします。経済学の知識を身に付けることで、企業のビジネス戦略を効果的にサポートすることができます。試験対策としては、過去問題の活用やセミナーの参加、計算問題の練習が重要です。皆さんの成功を心から応援しています。経済学の知識を活用して、企業の成長をサポートし、中小企業診断士としてのキャリアを築いてください。
中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 まとめ
ここまで見て来たとおり、経済学・経済政策は、苦手意識を持つ方が多い一方、面白くなってハマる方も出てくるような、ちょっと特徴のある科目と言えるでしょう。難解なパズルに近い、と表現できるかも知れません。
必要以上に怖れることなく、また必要以上に乗めり込むこともありません。スケジュールを決めて、ある意味、淡々と取り組むことが、この科目を攻略する近道と言えるでしょう。
■
経済学・経済政策の勉強法については本記事で説明しましたが、診断士試験全体の「最速勉強法」ノウハウについては、現在、資格スクールのクレアールが、市販の受験ノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、そちらもチェックしてみてください。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2024年最新版 比較・ランキング
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |