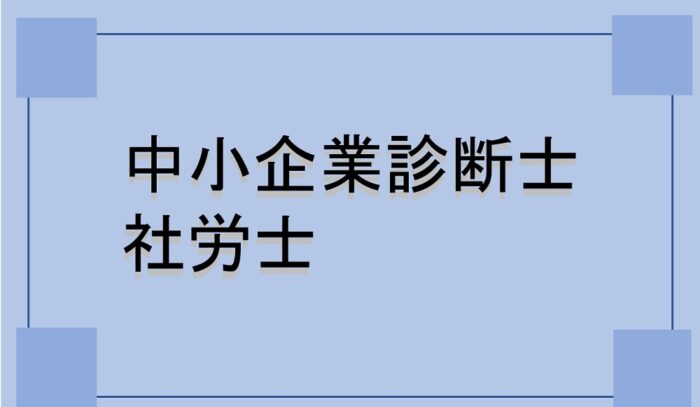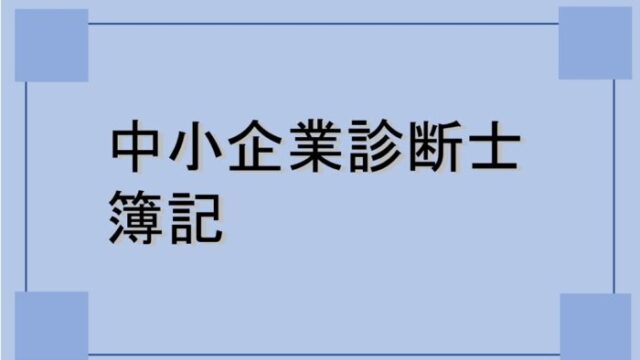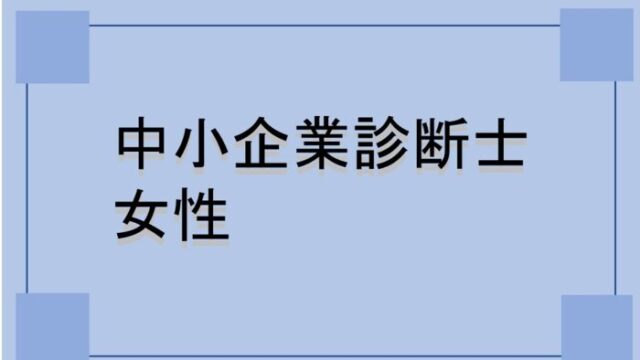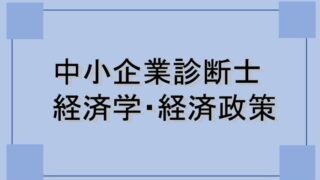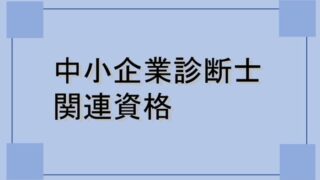今回は、中小企業診断士と社労士のダブルライセンスに関する記事です。
中小企業診断士は、経営の課題解決に関するプロフェッショナルですが、顧問先の経営者に、組織や人の問題で相談を受けることが良くあります。
経営者にとって「ヒト」の悩みは尽きないため、これは「中小企業診断士あるある」の体験でしょう。
そんなときに役に立つのが、社労士(社会保険労務士)の資格です。
社労士は「労働関連法令、および労働保険・社会保険に関する専門家」です。
就業規則や社会保険の手続きに関する書類の作成や提出は、社労士にのみに許された独占業務です。
人事部門でのキャリア(勤務経験)のある方が中小企業診断士資格に加え、社労士も取得すれば、組織と人のマネジメントに関するコンサルティグ能力を更に高めることができるでしょう。
経営だけでなく人事や労務に精通した経営コンサルタントして差別化できますし、前述のとおり独占業務もありますので、社労士とのダブルライセンスは非常に有効です。
この記事では、中小企業診断士と社労士のダブルライセンスのメリットなどについて、詳しく見ていきたいと思います。
気になる方はチェックしてみてください。
目次
社労士(社会保険労務士)と中小企業診断士の仕事内容 違いは?
社労士と中小企業診断士は、どちらもビジネスパーソンに人気のある国家資格です。
両方の資格とも、企業が抱えている課題や問題点を解決するためのライセンスであり、将来性とニーズは極めて高いものです。
まず最初に、社労士と中小企業診断士の仕事内容がどのように違うのか見ていきましょう。
- 中小企業診断士は中小企業の経営者やクライアントに対して、経営面の相談や課題解決の手助けを行う仕事
- 社労士は労働関係の法律を領分とする国家資格で、労働社会保険に関する書類や帳簿書類の作成、人事労務コンサルティングを行う仕事
企業へのサポートやアドバイスを行う点では、社労士も中小企業診断士も一緒です。
社労士と中小企業診断士の試験内容や試験範囲 どう違う?
社労士と中小企業診断士は、試験内容や試験範囲に違いがあります。
中小企業診断士の1次試験は、下記の7つの科目で構成されています。
- 経済学/経済政策
- 財務会計
- 企業経営理論(経営戦略論、経営組織論、マーケティング論)
- 運営管理(生産管理、店舗・販売管理)
- 経営法務(知的財産権、商法・会社法他)
- 経営情報システム
- 中小企業経営/中小企業政策
科目数は社労士よりも少ないですが、中小企業診断士の試験は上記の1次試験(マークシート方式)に加え、4科目の記述試験と口述試験(面接)からなる2次試験もあります。
一方、社労士の試験科目は次の10分野です。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
労働・社会保険関連法規に特化しているのが分かりますね。
どちらも簡単に取得できるほど甘い試験ではありません。資格取得を目指している方はスケジュールを練って学習に取り組みましょう。
社労士と中小企業診断士のダブルライセンス どんなメリットがある?
社労士と中小企業診断士は、非常に相性のよい資格であり、片方の資格しか持たない人と比べて、ダブルライセンス者は自分のアピールポイントが高まります。
中小企業診断士のダブルライセンスのメリットについて、詳細に見て行きましょう。
顧客に高付加価値なサービスを提供できる
顧客やクライアントに対して高付加価値なサービスを提供できるのは、社労士と中小企業診断士のダブルライセンスの大きなメリットです。
まず、社労士主な業務は以下の3点となります。
- 1号業務:労働社会保険諸法令にもとづく提出すべき申請書類の作成や手続きの代行など
- 2号業務:就業規則や労働者名簿など労働社会保険諸法令にもと基づく帳簿書類等の作成など
- 3号業務:会社の人事や労務管理上の相談業務に応じて適切なアドバイスやコンサルティングを行う
社労士の3号業務は独占業務ではありませんが、コンサルティング業務に特化した社労士事務所は増えました。
もし社労士に加えて中小企業診断士の資格も持っていれば、更に多くの内容のコンサルティングができます。
2つの資格の知識を活かしたアドバイスや指導ができれば、顧客やクライアントの満足度も高まるわけですね。
コンサルティング業務をメインで行おうと考えている社労士は、中小企業診断士とのダブルライセンスは大きな武器になります。
独立開業で大きな強みになる
他の資格との組み合わせにも該当しますが、社労士と中小企業診断士のダブルライセンスは独立開業で大きな強みになります。
中小企業診断士として独立するに当たって魅力的なポイントはあるものの、企業勤務とは違って収入が安定しないのがデメリット…。
顧客を確保しないと利益を出せないため、常に営業活動を続けないといけません。
独立開業して失敗している中小企業診断士は少なくありません(例:サラリーマンに戻るなど)。
しかし、社労士の資格も持っていれば他者と差別化を図れますので、生き残りやすいといえます。
自分のアピールポイントが増えれば顧客からの信頼も勝ち取ることができますので、独立開業して契約を結びやすくなるわけです。
試験内容で被る部分がある
社労士と中小企業診断士は、試験内容で少なからず被る部分があります。
最初に社労士の試験に合格した人であれば、他者よりも有利に中小企業診断士の勉強を進められるわけです。
以下では、社労士と中小企業診断士の試験で重複する内容を解説していきます。
- 中小企業診断士の1次試験で出題される企業経営理論の組織論では、社労士の出題範囲でもある労働関係の法律問題が出題される
- 中小企業診断士の2次試験で出題される組織の事例(事例1)では、社労士の得意分野である組織人事の知識や実務が役立つ
中小企業診断士の試験で得点源科目にできる確率が他の受験生よりも高いため、その分、社労士とのダブルライセンスは狙いやすいと言えます。
AIによる代替に対応できる
AI技術の進展により、士業の資格を持っている方でも仕事が減っていくと考えられています。
以下では、士業別でAIによる代替の確率についてまとめてみました。
| 士業 | 主な業務 | AIによる代替の可能性 |
|---|---|---|
| 中小企業診断士 | 中小企業へのコンサルティング | 0.2% |
| 弁護士 | 訴訟代理などの法律事務 | 1.4% |
| 司法書士 | 登記や供託に関する手続き | 78.0% |
| 社会保険労務士 | 労務や社会保険に関する書類の作成 | 79.7% |
| 公認会計士 | 財務書類の監査や証明 | 85.9% |
| 行政書士 | 官公署に提出する書類の作成 | 93.1% |
参考:https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc/2015/151202_1.pdf
社労士の独占業務の就業規則や賃金台帳の作成は、AIに代替される可能性があります。
しかし、コンサルティング業務がメインの中小企業診断士は人と人とのコミュニケーションで成り立っていますので、AIに代替されにくい将来性の高い仕事です。
かと言って、独占業務のない中小企業診断士だけでは仕事を獲得するのは難しい部分もあります。
社労士とのダブルライセンスが強いのは何となくイメージできるのではないでしょうか。
社労士と中小企業診断士を試験の難易度で比較!
社労士と中小企業診断士の試験のどちらが難しいのか気になるところですよね。
そこで、まずは社労士の試験の合格率を見ていきましょう。
| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 51,960人 | 3,650人 | 7.02% |
| 平成25年度 | 49,292人 | 2,666人 | 5.41% |
| 平成26年度 | 44,546人 | 4,156人 | 9.33% |
| 平成27年度 | 40,712人 | 1,051人 | 2.58% |
| 平成28年度 | 39,972人 | 1,770人 | 4.43% |
| 平成29年度 | 38,685人 | 2,613人 | 6.75% |
| 平成30年度 | 38,427人 | 2,413人 | 6.28% |
合格率が3%を切る年度もありますので、社労士は難易度の高い試験だとわかります。
次に中小企業診断士の試験の合格率をまとめてみました。
| 試験年度 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格率 | 2次試験受験者数 | 2次試験合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 14,981人 | 23.5% | 4,878人 | 25.0% |
| 平成25年度 | 14,252人 | 21.7% | 4,907人 | 18.5% |
| 平成26年度 | 13,805人 | 23.2% | 4,885人 | 24.3% |
| 平成27年度 | 13,186人 | 26.0% | 4,941人 | 19.1% |
| 平成28年度 | 13,605人 | 17.7% | 4,394人 | 19.2% |
| 平成29年度 | 14,343人 | 21.7% | 4,279人 | 19.4% |
| 平成30年度 | 13,773人 | 23.5% | 4,812人 | 18.8% |
社労士の試験とは違い、中小企業診断士は1次試験と2次試験の両方に合格しないといけません。
そのため、2つの試験をトータルで考えてみると、中小企業診断士の合格率は4%~5%程度になります。
合格率から見れば、社労士と中小企業診断士の試験は、同じくらいの難易度だと考えて問題ないでしょう。
しかし、社労士の試験がマークシートによる択一式と選択式なのに対して、中小企業診断士の試験には記述式の問題があります。
同じくらいの難易度でも試験対策のやり方は全く違いますので、ダブルライセンスを目指す方は十分に注意してください。
※中小企業診断士の難易度については、下記の記事も参考にしてください。
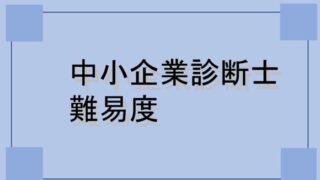
もし片方だけ選ぶとすると、社労士と中小企業診断士はどちらがおすすめ?
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスはおすすめですが、どちらも難易度の高い試験ですので簡単に合格することはできません。
同時並行で勉強を進めるのは現実的ではありませんので、社労士か中小企業診断士か片方を最初に選ぶ形になります。
「どっちの資格がおすすめなの?」と迷っている方は多いのですが、自分が将来何を目指すのかでおすすめは変わります。
一般企業や社労士事務所に転職し、勤務社労士として働きたいのであれば、当然ながら社労士がおすすめ。
もちろん、実務経験をしっかりと積んだ後に、社労士の資格を活かして独立開業する手もあります。
一方、経営プロフェッショナルや経営コンサルタントとしての活動を考えている方は、中小企業診断士資格のほうがおすすめとなります。
中小企業診断士は、ビジネスパーソンが新しく取りたい資格で第1位となっていますので、企業で働くにしても独立するにしても役に立つのは間違いありません。
社労士と中小企業診断士は兼業できる?
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスになれば、兼業して良い部分を活かした業務ができます。
社労士は書類の作成手続きを行う資格だとイメージしている方はいますが、組織と人をマネジメントする能力を発揮できます。
中小企業診断士と似た部分がありますので、この2つの資格は兼業で相性が良いわけです。
人によって資格の活かし方は変わりますが、社労士をメインに中小企業診断士の切り口を加えた人事や労務のコンサルティングに取り組むこともおすすめです。
多くの社員を抱えている中小企業や中堅企業では、人に関するニーズは必ずあります。
社労士と中小企業診断士の知識を持つ人によるコンサルティングは、中小企業からの需要があるのです。
コンサルティング業務はAI等のIT技術ではカバーできない部分ですので、社労士と中小企業診断士のダブルライセンスは強力にアピールできるのです。
まとめ
社労士と中小企業診断士のダブルライセンスになるメリットについておわかり頂けましたか?
転職したり独立開業したりするに当たり、この2つの資格は大いに役立ちます。
どちらも難易度の高い試験ですが、あなたの将来ビジョンに合うようでしたら、社労士と中小企業診断士の資格取得を検討してみてください。
【参考】本記事の執筆にあたり、以下の社労士事務所のWebサイトを参考にさせて頂きました。