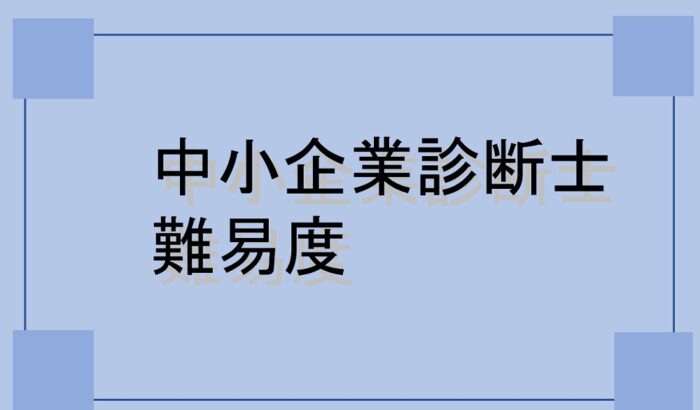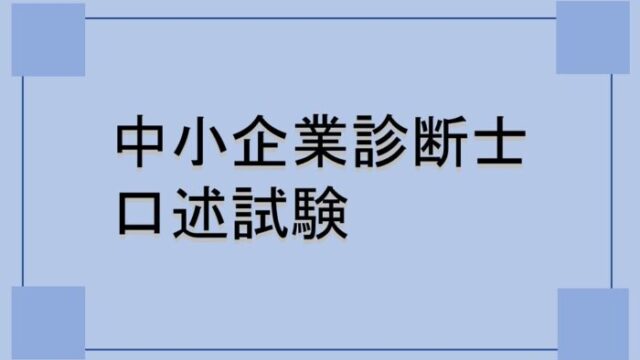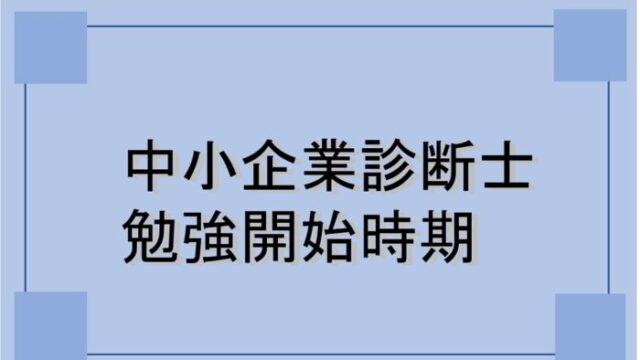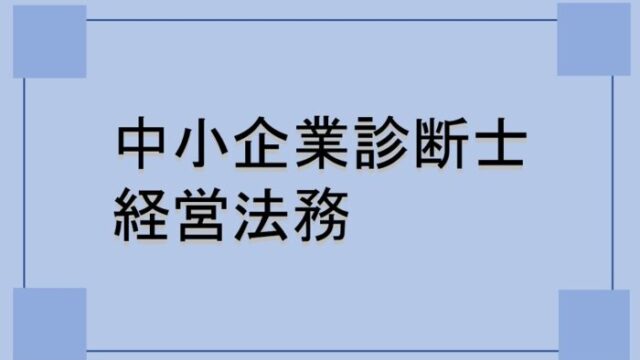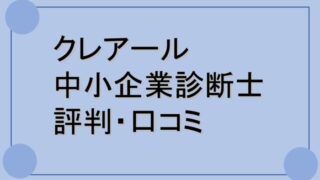こんにちは、トシゾーです。
民間の経営コンサルタントを認定する唯一の国家資格が中小企業診断士です。
弁護士や税理士・会計士、不動産鑑定士などの超難関資格の士業と比べると中小企業診断士の知名度は低いですが、
それでも現在、経営コンサルティングのニーズの高まりとともに、中小企業診断士の資格に、少しずつ注目が集まるようになって来ました。
この記事を読んでいる方のなかには、
「中小企業診断士を目指したい」
「中小企業診断士の勉強を始めたい」
と考えている方も多いでしょう。
そこで気になるのは、中小企業診断士の難易度。一体、どの程度なのでしょうか。
今回の記事では、「中小企業診断士という資格が気になる方」、「中小企業診断士の受験を考えている方」に向けて、以下の内容をお伝えします。
<この記事で分かること>
- 合格率から見た難易度は(一次試験、二次試験、科目別)
- 他資格と比較した場合の難易度
- 統計(数字)データから考察する難易度
- 中小企業診断士になるために必要な偏差値は?
- 結局、難易度に見合うメリットはあるのか?
以上のように、多角的に中小企業診断士の難易度を分析してみたいと思います。
下の目次からチェックしたい項目だけ読むのもオススメです。
よろしくお願いします!
目次
中小企業診断士試験 合格率からみた難易度
中小企業診断士の合格率(総合)の目安は4% ~ 8%
中小企業診断士試験には、一次試験と二次試験があり、両方の試験をクリアしないと合格という結果を手にすることはできません。つまり、
- 中小企業診断士試験の合格率 = 一次試験の合格率 × 二次試験の合格率
となります。具体的には、次のとおりの目安になります。
| 試験の種別 | 合格率(目安) |
|---|---|
| 中小企業診断士 一次試験 | 20% ~ 40% |
| 中小企業診断士 二次試験 | 20% |
| 総合(中小企業診断士試験 全体) | 4% ~ 8% |
以下、中小企業診断士の一次試験と二次試験について詳しく見ていきましょう。
中小企業診断士 一次試験(マークシート方式)総合的な難易度
一次試験の受験者数・合格者数・合格率(全科目総合)
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| H25 | 14,252 | 3,094 | 21.7% |
| H26 | 13,805 | 3,207 | 23.2% |
| H27 | 13,186 | 3,426 | 26.0% |
| H28 | 13,605 | 2,404 | 17.7% |
| H29 | 14,343 | 3,106 | 21.7% |
| H30 | 13,773 | 3,236 | 23.5% |
| R1 | 14,691 | 4,444 | 30.2% |
| R2 | 11,785 | 5,005 | 42.5% |
| R3 | 16,057 | 5,839 | 36.4% |
| R4 | 17.345 | 5,019 | 28.9% |
注)受験者数は、欠席した科目がひとつもない者の人数です。
一次試験の合格率の推移は上のとおり。令和2年度は大幅に合格率が上がっていますが、これはコロナ禍のため、あまり自信のない方が受験を見送った影響もあるかと想定されます。
年度により差はありますが、おおむね20% ~ 40%程度の合格率といえるでしょう。
一次試験の科目
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
中小企業診断士一次試験は、例年8月の第1週の週末(土日)に実施されます。
診断士の一次試験に受験資格はありませんが、上のように幅広いカリキュラムを学ぶ必要があり、決して簡単な試験ではありません。
1日目は4科目、2日目は3科目で、いずれも配点は100点満点。
ただし、表をよく見ると分かるように、「企業経営理論」「運営管理」「中小企業経営・政策」の3科目は制限時間が90分ということで、他の科目(60分)より1.5倍も長くなっています。
その分、問題が多く出題されますが、その一方で、1問あたりの配点は小さくなります。
いずれにしても、2日間で上記7科目というのは、かなりボリュームがあり、実際に受験する際には、体調管理も合格に大きく関係してくると言えるでしょう。
さて、肝心の合格ライン(合格の基準)ですが、各科目100点満点で7科目合計700満点中、420点を取れば合格となります。つまり、平均60点以上取れば合格ということです。
ただし、もう1つ条件があります。それは、1科目でも40点未満の科目があっては駄目だということ。いわゆる足切りの基準です。40点未満の科目があると、他の科目の点数がどんなに良くとも、一次は不合格となります。
そのため、中小企業診断士の一次では、苦手科目を作らないことが重要となります。この点はぜひ確認しておいてください。
中小企業診断士 一次試験 科目別の難易度
ここからは、各科目の過去の合格率を見ながら、それぞれの科目の難易度を考えてみます。
経済学・経済政策の難易度
経済学・経済政策のこれまでの科目合格率は次のようになっています。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 19.4% | 15.5% | 29.6% | 23.4% | 26.4% | 25.8% | 23.5% | 21.1% |
経済学・経済政策は科目合格率だけ見ると、他の科目より易しそうに思えるかも知れません。
しかし、単純な暗記型科目ではなく、知識積み上げ型科目のため、学習には時間がかかります。
他の資格との関連で言えば、「経済学検定試験(EREミクロ・マクロ)」と内容が近いでしょう。
実際、資格スクールの会社である「資格スクエア」の経済学・経済政策の科目は、「経済学検定試験(EREミクロ・マクロ)」のテキストを利用して学習します。
財務・会計の難易度
財務・会計のこれまでの科目合格率は次のとおり。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 6.1% | 36.9% | 21.6% | 25.7% | 7.3% | 16.3% | 10.8% | 22.4% |
財務・会計は、年度により大きく合格率が変動しています。
この科目を苦手とする方も多いですが、中小企業診断士試験にとっては、中核科目の1つ。
財務会計の数値を読む力は経営コンサルタントとして最も大切で役立つ能力ですから、中小企業診断士を目指す以上、きちん習得できるよう対応しなくてはなりません。
前述の資格スクエアでは、財務・会計の科目をマスターするために、
日商簿記検定3級/ビジネス会計検定3級・2級/経営学検定(中級・経営財務)
以上の検定試験を学習します。
上記には出ていませんが、管理人としては、「簿記2級」が難易度・内容とも、財務・会計の科目に一番近い、と考えています。
企業経営理論の難易度
企業経営理論のこれまでの科目合格率は次のとおり。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 13.4% | 16.7% | 29.6% | 9.0% | 7.1% | 10.8% | 19.4% | 34.7% |
こちらも、中小企業診断士試験にとって中核科目の1つです。
積み上げ型科目、かつ範囲が「経営戦略論・経営組織論・マーケティング論」と広いですから、時間が必要な科目です。
同等資格としては、「経営学検定試験(初級・中級)」が挙げられます。
運営管理の難易度
運営管理のこれまでの科目合格率は次のとおり。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 17.8% | 20.5% | 11.8% | 3.1% | 25.8% | 22.8% | 9.4% | 18.5% |
運営管理は、「生産管理」と「店舗/販売管理」の異なる2科目から構成されます。
店舗/販売管理の関連資格としては「リテールマーケティング(販売士)検定3級・2級」があります。
生産管理には、一般的な関連資格はありません(資格スクエアでも、独自のテキストや資料を使うようです)。
経営法務の難易度
経営法務のこれまでの科目合格率は次のようになっています。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 10.4% | 11.4% | 6.3% | 8.4% | 5.1% | 10.1% | 12.0% | 12.8% |
こちらは暗記科目であり、二次試験にも関連が薄い(=中核科目ではない)ため、中小企業診断士としては、効率よく対処したいところです。
ただ、この経営法務の平成30年度の難易度の高さが話題(問題?)となりました。
平成30年度の科目合格率は5.1%と非常に低いですが、これは、なんと得点調整したあとの数字なのです。もし得点調整しなかったら、2~3%という数字になっていたと推測されます。
なお、経営法務の関連資格としては、 ビジネス実務法務検定試験の3級・2級があります。
経営情報システムの難易度
経営情報システムのこれまでの科目合格率は次のとおり。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 15.0% | 6.4% | 8.5% | 26.6% | 22.9% | 26.6% | 28.1% | 9.28% |
経営情報システムは、ITに携わる業務をしている方とそうではない方で、得意不得意の差が大きくでる科目です。
難易度としては、情報処理技術者試験のITパスポート試験と同等レベルでしょう。
ITが不得意な中小企業診断士受験者は、先にITパスポートを勉強しておくと良いかも知れません。ITパスポート試験はCBT(コンピュータを利用した試験形態)を採用しており、毎月、各地で試験が行われているため受験日の確保がしやすく、受験の敷居も低くなっています。
中小企業経営・政策の難易度
中小企業経営・政策の、これまでの科目合格率は次のようになります。
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 31.1% | 12.2% | 12.5% | 10.9% | 23.0% | 5.6% | 16.4% | 7.1% |
中小企業経営・中小企業政策は、7科目の中で唯一、毎年出題内容が大きく変わります。
というのも、毎年、前年度版の中小企業白書が出題範囲となるため、テーマがガラっと変わってしまうからです。
つまり、あまり過去問の学習が役に立ちません。
特に関連資格はありません。暗記科目であり、他の科目と比べ難易度も相対的に低くなっています。
中小企業診断士 二次試験(筆記)に見る難易度
二次試験の受験者数・合格者数・合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| H25 | 4,907 | 910 | 18.5% |
| H26 | 4,885 | 1,185 | 24.3% |
| H27 | 4,941 | 944 | 19.1% |
| H28 | 4,394 | 842 | 19.2% |
| H29 | 4,279 | 828 | 19.4% |
| H30 | 4,812 | 905 | 18.8% |
| R1 | 5,954 | 1,088 | 18.3% |
注)受験者数は、欠席した科目がひとつもない者の人数です。
前にも書いたとおり、二次試験はおおむね20%程度の合格率です。といっても、こちらは上位20%程度を選抜していると考えられますので、純粋な得点による判定ではありません。言ってしまえば、中小企業診断協会の胸三寸ということです。
二次試験の科目
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 1.組織・人事の事例 | 80分 | 100点 |
| 2.マーケティングの事例 | 80分 | 100点 |
| 3.生産・技術の事例 | 80分 | 100点 |
| 4.財務・会計の事例 | 80分 | 100点 |
二次試験は、10月の第3日曜日に実施されます。
上記の4つのテーマについて問題文を読み、そこに書かれたターゲット企業の問題点や経営戦略の改善ポイントなどを筆記で回答していきます。まさに記述式で経営診断をするようなイメージです。
80分と言う限られた時間で経営診断を一通り完了する、ということを4回繰り返すわけですから、内容的にも体力的にも、かなり難易度の高い試験と言えます。
こちらの合格ラインは、公式には「総得点の平均が60%以上、かつ40点未満の科目がないこと」とされています。
ただし、実態は総受験者のうち上位20%程度を合格とする相対選抜試験と言われています。つまり、同じ出来栄えでも、周りの受験生の優劣によって、合格か不合格が決まってしまう、ということです。
また、こちらの試験は中小企業診断協会から正解の発表がありません。このことも、中小企業診断士の二次試験の難易度を高くしている要素の1つと言えるでしょう。
二次試験 合格率
例年20%程度
※「二次筆記試験の対策」については、下記記事を参考にしてください。

二次試験(口述試験)に見る難易度
筆記に無事合格すると、口述試験を受けることになります。
「口述試験」というと難しそうなイメージがありますが、実は、ほとんど落ちることはありません。10分ぐらいの面接のような試験であり、試験官が2次試験の出題に関連する質問を4問程度行いますので、それに答える形式となります。
質問内容はそんなに難易度の高いものではなく、また、迷ったりすると助け舟を出してくれる場合もあります。
おそらく口述では、「経営コンサルタントにふさわしい一般常識がある人物かどうか」を見ているだけのような気がしますので、普通の受け答えがでければ、まずは大丈夫でしょう。
「口述試験の詳細」は、下記記事を参考にしてください。
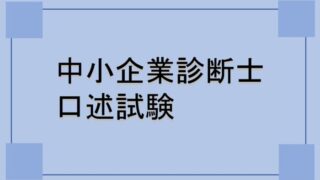
高い難易度を避けるための逃げ道も多い
中小企業診断士の受験科目を見て、「相当難しいな」と弱気になってしまった方も多いのではないでしょうか。
しかし、上手く使えば合格をグッと近づけることができる「逃げ道」もいくつかあります。
まずは「科目合格制度」です。
これは、一次試験に不合格だった場合、60点以上の得点を獲得した科目は、最大で3年間の受験の免除を受けることができる、というものです。
つまり、3年以内に、7科目を個別に合格すれば1次合格、となります。
また、一次に合格すると、その年と翌年、二次を受験できる資格が得られます。一次に受かった年に二次を受けて万が一失敗しても、翌年もチャンスがもらえるわけです。
ただし、翌年も不合格になってしまうと、また一からやり直しとなるので、注意が必要です。
なお、一次試験の科目合格制度については、適切に戦略を練って利用しないと、逆に不利になってしまうこともあります。
「科目合格制度を有利に使いこなす方法」については、以下の記事を参考して欲しいと思います。

二次を受けない手もある ~養成課程へ進む難易度は?
中小企業診断士として経済産業大臣に登録し、活動するためには、口述試験まで全て合格した後、実務補習と呼ばれる計15日の診断実習を行うことが必要です。
しかし、一次だけ受験して合格すれば、、あとは試験ではなく、養成課程または登録養成課程に進む手もあります。
実施元により、受講料は100万円~300万円台、実施期間は半年~2年と幅があります。平日の昼間に講義が実施される機関も多く、金額的・時間的制約から、養成課程の道を選べる方は限られるのではないでしょうか。
養成課程については、下記の記事も参考にしてください。
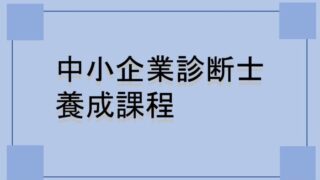
統計データからみる中小企業診断士の難易度
ここでは、中小企業診断協会が公表している統計データを見ながら難易度を考えてみたいと思います。
合格者の傾向 ~男女別から見る難易度
一次試験の男女別の合格者数(難易度)
| 申込者数 | 試験合格者数 | |
| 男性 | 17,733 | 2,281 |
| 女性 | 1,711 | 123 |
| 合計 | 19,444 | 2,404 |
二次試験の男女別の合格者数(難易度)
| 申込者数 | 試験合格者数 | |
| 男性 | 4,289 | 777 |
| 女性 | 250 | 65 |
| 合計 | 4,539 | 842 |
女性の合格者の割合は、は1次で全体の5%程度、2次は7%程度となっています。
そもそも、女性の受験生が少ないのが原因と言えます。現在では、女性の起業家や経営者も増えていますし、女性の中小企業診断士が活躍できるフィールドはこれからも増えるでしょう。
実際のところ、中小企業診断士の業界はまだまだ男社会ですが、受験科目を見てもわかるとおり、「女性だから不向き、不可能」ということは一切ありません。
むしろ、女性ならではのきめ細かいサポート力を活かし、男性以上にコンサルタントとして活躍することも十分に可能です。
ぜひ、中小企業診断士を目指す女性も増えて欲しいと思います。
合格者の傾向 ~年齢別から見る難易度
一次試験 年齢層別の合格者数
| 申込者数 | 試験合格者数 | |
| 20歳未満 | 67 | 3 |
| 20~29 | 3,198 | 385 |
| 30~39 | 6,502 | 898 |
| 40~49 | 5,614 | 693 |
| 50~59 | 3,116 | 350 |
| 60~69 | 854 | 74 |
| 70歳以上 | 93 | 1 |
| 合計 | 19,444 | 2,404 |
(合格者の最年長:75歳、最年少:19歳)
二次試験 年齢層別の合格者数
| 申込者数 | 試験合格者数 | |
| 20歳未満 | 1 | 0 |
| 20~29 | 490 | 122 |
| 30~39 | 1,587 | 360 |
| 40~49 | 1,454 | 233 |
| 50~59 | 817 | 106 |
| 60~69 | 180 | 21 |
| 70歳以上 | 10 | 0 |
| 合計 | 4,539 | 842 |
(合格者の最年長:69歳、最年少:20歳)
どちらも、30代の合格者が最も多く、続いて40代、20代、50代、60代・・・となっています。
これは、中小企業診断士試験が、
「ある程度実務が分かった方が有利」
「ある程度長期間にわたって受験勉強をすることが必要(集中力・体力が必要)」
というような特性を持つことに関連しているのではないでしょうか。
なお、人数は少ないものの、一次試験には10代と70代の合格者もいるようです。これは素直に凄いことだと感じます。
合格者の傾向 ~勤務先別から見る難易度
社会人合格者の傾向
一次・二次とも、民間企業勤務の方がダントツトップ、続いて金融機関勤務(政府系以外)となっています。その後、税理士・公認会計士と公務員の方がほぼ同数、といった状況です。
実際に中小企業診断士の資格を取得しても、独立される方は2割程度、と言われています。
そのため、民間企業の社内業務や、金融機関の融資先の経営指導に、中小企業診断士のノウハウを活用していると想定されます。
税理士や公認会計士の方は、財務諸表のチェックだけでなく、経営コンサルティング全般のノウハウを手に入れて、クライアント業務の高度化を図ろう、と考えているのでしょう。
大学生の合格者も多い
職業の内訳には「学生」もあり、合格者も出ています。
令和3年の学生の一次試験合格率は18.4%、二次試験合格率は21.3%となっています。一般的には「中小企業診断士の試験科目は社会で働いた経験がある人のほうが有利だ」と考えらえれていますが、なんと二次試験は全体の合格率より学生のほうが上回っています。
試験の統計には「学生」としか書いていませんが、さすがに大学生以上でしょう。おそらく、東京大学・京都大学・早稲田大学・慶応大学・上智大学など、難関の大学が多い気がするのですが、どうなのでしょうか?
なお、大学生のうちに中小企業診断士の資格を取れば、就活に大きなメリットがあることは確実です。この点については、次の記事を読んでみてください。
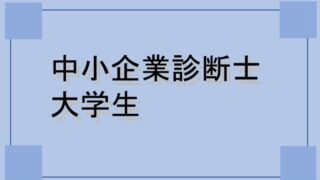
偏差値のランキングから見た、中小企業診断士の難易度
厳密には、資格試験に偏差値は存在しません。
ただし、ネット上では独自の手法でまとめた「資格試験の偏差値」が複数公表されています。
正式な根拠はありませんが、資格同士の相対的な難易度のポジションを知るには、一定の参考にはなると考え、少し言及します。
中小企業診断士の偏差値ランキングは60、難関国家資格の中では平均的
裁判官・検察官・弁護士などになるための司法試験は難易度が非常に高く、偏差値67~70とされています。極めて難しいものといえます。
よく中小企業診断士は社労士や行政書士などと共に「働きながら取れる資格としては一番難しい」などと言われます。
仕事と試験勉強を両立して学べる資格は中小企業診断士試験等までで、それ以上の難関資格は専業で勉強しないと合格は難しい、という意味です。
確かに、中小企業診断士・社労士・行政書士のいずれも偏差値59~60と難易度は同じぐらいと言えますね。
また、不動産系で著名な宅建士、マンション管理士等は、中小企業診断士等よりも難易度は低いとされています。
総合的に見てみると、中小企業診断士の難易度は、難関な国家資格である士業の中において、中程度と言えるのではないでしょうか。
中小企業診断士試験の学歴に見る難易度
偏差値の話が出たところで、よく聞かれる「学歴」について言及します。
中小企業診断士試験に学歴は関係ない
そもそも、主に社会人を対象とした試験ですので、建て前としては「学歴や出身大学は関係ない」ということになるのですが。
とは言え、私の知り合いの先生方(中小企業診断士)を見回しても、高学歴の方が多いのも事実です。
すぐに思い出せるだけでも、東京大学・京都大学・大阪大学・北海道大学などの旧帝大、早稲田大学・慶応大学・関西学院大学・立命館大学などの難関私立大学、と大変有名な大学名が並びます。さらに、それらの大学院卒の方もいます。
すごい高学歴ですが、ただ、それらの先生方が、中小企業診断士として、みんな優秀かと言えば、そうではない気もします。
大学受験に成功された方のなかには、いわゆる「ガリ便」タイプが多いのかも知れません。「実務より勉強が好き」という感じの方も散見されます(すいません、完全に私の偏見です。。。)
一方、六大学や日東駒専などを卒業された先生方も多くいらっしゃり、みなさん優秀な印象です。
また、知り合いの抜群に仕事ができる先生の中には、高卒の方もいらっしゃいます。
ですので、「出身大学は、まったく関係ない」というのが、私の超個人的な見解です。
ただ、きちんと勉強を継続しないと絶対に受からない試験ですから、「勉強グゼがついている人」が受かりやすいのは、間違いないかも知れません。
中小企業診断士の難易度を大学の偏差値と比較
中小企業診断士の偏差値ランキングは60とのことで、これが大学の場合、どの程度になるのでしょうか。東進ハイスクールが作成した大学の入学試験における偏差値一覧より偏差値60の大学を見てみました。
- 和歌山大学(教育)
- 埼玉大学(教育)
- 宇都宮大学(地域デザイン)
- 富山大学(人文)
- 山口大学(経済)
- 岡山大学(教育)
- 島根大学(法文)
- 新潟大学(法)
など
ざっと見ると中堅どころの大学というイメージですが、「難関国家資格の中では平均的な難易度」である中小企業診断士とイメージが近いかも知れませんね。
中小企業診断士の勉強時間から見る難易度
中小企業診断士の合格に必要な勉強時間は1000~1,200時間前後かかると言われます。
もし、あなたが1年でストレート合格を狙うとしたら、毎日どれぐらいの勉強が必要でしょうか。
1年を50週として、単純計算すると、
1,000時間÷50 = 20時間/週
1週間に20時間の学習が必要になります。
ただし、実際には1年間でのストレート合格される方は少ないのが現状です。
勉強時間について詳しくは、下記の記事をチェックしてみてください。

中小企業診断士の勉強期間(合格に必要な年数)は?
中小企業診断士の平均受験回数は3回
中小企業診断士試験では、平均受験回数は約3回です。毎年1回しか試験は開催されないため、平均的な受験生は3年間勉強していることになります。
ただ、実際には合格できないまま諦めてしまう人も少なくありません。
数年もの間、地道に努力を続けることができれば決して無理な目標ではありませんが、モチベーションを維持して勉強を継続することが如何に難しいことであるか、心に留めておく必要があるでしょう。
資格のランキングからみる中小企業診断士の難易度
TACの2021年度(令和2年度)版 資格ランキングによる難易度
資格の学校TACでは、様々なビジネス系の資格の難易度をランキングにしています。
2021年度版のTAC資格ランキングから、中小企業診断士と比較されることが多い他の士業の難易度ランキングをみてみましょう。
| 公認会計士 | ★★★★★ |
| 税理士 | ★★★★★ |
| 社会保険労務士 | ★★★★ |
| 中小企業診断士 | ★★★★ |
| 司法書士 | ★★★★★ |
| 行政書士 | ★★★★ |
| 宅建(宅建士) | ★★★ |
このように、TACの難易度ランキングでは、中小企業診断士と社会保険労務士・行政書士は難易度4で、同程度と位置付けています。
勉強時間から見た各資格試験(国家資格)の難易度
続いて、各資格試験(国家資格)の合格までに必要な勉強時間を比較してみましょう。
- 弁護士(司法試験):6,000時間
- 公認会計士:3,000時間
- 司法書士:3,000時間
- 弁理士:2,500~3,000時間
- 税理士:2,500時間
- 社会保険労務士(社労士):1,000時間
- 行政書士:500~800時間
- 宅地建物取引士(宅建士):300時間
- 管理業務主任者:300時間
中小企業診断士の勉強時間は1,000~1,200時間ですから、勉強時間で比較しても、社労士や行政書士が近い状態であるのが分かります。
社労士や行政書士の難易度との比較
社労士や行政書士の難易度は、中小企業診断士の難易度と同程度と言っても、人によって様々な意見があるようです。
と言うのも、受験科目が全然異なる上に、
広く浅い知識を問われる中小企業診断士
に対して、
狭い範囲の深い知識を問われる社会保険労務士・行政書士
というように、そもそも試験制度の考え方がまったく異なるので、単純に難易度を比較できないからです。
以下に、それぞれの受験科目をみてみましょう。
中小企業診断士試験の1次試験科目に見る難易度
まず、中小企業診断士です。
中小企業診断士試験の1次科目では、会計、法律系、情報システム、戦略論やマーケティング、経済学、そして工場のオペレーションである生産管理まで、ありとあらゆる企業の経営に必要な知識が全て問われます。
経済産業省では、中小企業診断士を「日本版MBA(経営学修士)」と位置づけているため、経営のプロフェッショナルに必要な知識は全部マスターさせよう、ということなのでしょう。
いずれにしても、この膨大とも言える範囲の広さが、中小企業診断士の難易度の高さの一端と言えます。
社会保険労務士 受験科目に見る難易度
社会保険労務士の試験科目は、「労働保険」と「社会保険」の2つに大きく分けられます。
その中から、全10科目として出題されます。これは、労働保険と社会保険に関する法律の1文1句と解釈を全て理解する必要がある、ということです。
重箱の隅をつつくような出題は当たり前ですし、徹底的に深堀するという意味で、中小企業診断士とは、また違った難易度があります。
このある狭い分野を極めるという点が、社会保険労務士の難易度を高くしている、と言えるでしょう。
行政書士 受験科目に見る難易度
こちらは法令と一般知識の2つのジャンルから出題されます。社会保険労務士ほどは狭くありませんが、ビジネスに関わる法規全般を押さえる必要があります。
こうして見てみると、徹底的に法律を理解・暗記する社会保険労務士や行政書士に比べ、中小企業診断士の出題範囲の広範さが、ますます目立ちますね。
どちらの難易度が高いと感じるのかは、
1つのことを、じっくりと極めたいタイプ
いろいろなことに手をだしてみたいタイプ
というように、その人本人の性格によるところが、もっとも大きいのではないでしょうか。
管理人の個人的な意見としては、
「中小企業診断士と社労士・行政書士のどちらの難易度が高いか(≒どちらをとるべきか)」
と考えるよりは、ダブルライセンスとして、資格を組み合わせて使うことを考えるほうが、より強みを発揮しやすい、と考えています(もちろん、ダブルライセンスを取得するのは簡単ではありませんが)。
なお、「中小企業診断士のダブルライセンス」の詳細については、下記記事を参考にしてください。
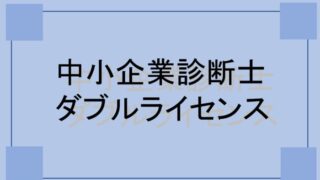
中小企業診断士試験は、難易度に見合った合格のメリットはある?
結論から言えば、
中小企業診断士に、難易度の高さに見合った合格のメリットがあるかどうかは、自分次第
ということです。
しかし、これでは、あまりに元も子もないですので、 以下に補足します。
難易度の割には、中小企業診断士の知名度は低い?
まず、中小企業診断士は、資格の難易度に比べて知名度が低い、という実態があります。
たとえば、「中小企業診断士と同程度の難易度の士業として、社会保険労務士(社労士)や行政書士がある」という話を先に書きましたが、
一般的な知名度では、社労士や行政書士の方が上でしょう。
そのため、転職時に中小企業診断士の資格が有利に働くかと言うと、あまり期待できません。
転職のことを考えるのであれば、社会保険労務士の方が断然アピールできると思います(ただし、総務・人事系の部門に限ります)。
中小企業診断士の転職事情については、下記記事を参考にしてください。
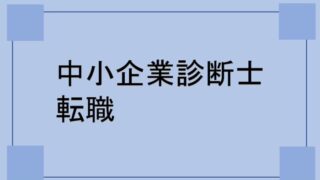
社労士や行政書士より知名度が低いのは、独占業務がないから?
社労士や行政書士より知名度が低い要因の一つに、「中小企業診断士は独占業務がないから」ということが考えられます。
基本的に中小企業診断士資格を取得していなくとも、中小企業に対する経営コンサルティングを実施することはできます。
そのため、中小企業診断士資格は、以前から、「取っても食えない」と揶揄されてきました。
しかし、最近では、少しずつ状況が変わって来ているようです。
徐々に「中小企業診断士の認知度が低い」という状態は変りつつあると同時に、人気も高まっているようなのです。
たとえば、2016年、日本経済新聞が発表した「社会人が新たに取りたい資格ランキング」において、中小企業診断士がトップを飾りました。
なぜ、独占業務がないのに人気が高まっているのか?
それは、中小企業診断士が
「ビジネス全般の能力を高める試験内容であり、コンサルタントだけでなく、全ビジネスマンに必要な知識と視野の広さを与えてくれる試験だから」
ということだと考えられます。
また、別の新聞記事では、「もっともAIに置き換えられにくい士業」として紹介されていました。
多くの士業が、書類などの作成代行業務を主としていますが、このような業務は、AIに置き換えられやすいのは明らかです。
それに比べ、中小企業診断士のコア業務は、
「中小企業経営者と対峙し、コミュニケーションを取り、その右腕として、経営の成功へ導く」
というものです。AIが最も苦手とする分野であることは明らかです。
これまで「知名度が今一つ」、などとも言われていましたが、着実に世間の知名度・そして人気も上がってきています。
「資格ランキング1位」や「AIに置き換えられにくい仕事」など、中小企業診断士の将来性に関する記事はこちらからご覧ください。
難易度に見合った年収はあるの?
企業勤務の場合は、年収にもあまり影響がないケースが多いようです。前述のとおり、中小企業診断士は独占業務もないですし、「資格を持っている」ぐらいで給料はなかなか変わりません。
一方、独立系の中小企業診断士の場合は、年収は300万未満~3,000万円以上と開きがあります。ただし、これは営業力や人脈、専門分野によって異なりますので、一概には語れません。
「中小企業診断士の年収事情」については、下記記事を参考にしてください。

最大のメリットは、中小企業診断士同士のつながり(診断士ネットワーク)
私個人的には、中小企業診断士同士の繋がり(診断士ネットワーク)には、非常に多くのメリットがある、と感じています。
ただし、これも「正しいアプローチで積極的に動く限り」という注釈が入ります。
結局は自分次第なのですが、中小企業診断士に合格後、各都道府県の中小企業診断協会などに所属することにより、他の多くの中小企業診断士とのネットワークができます。
そのネットワークを最大限に活かすことにより、様々な仕事につながりますし、それ以外にも、先輩諸氏から営業の仕方など、様々な示唆を頂くことが出来ます。
「中小企業診断協会」を通じて構築するネットワークなどに関しては、以下の記事をご覧ください。
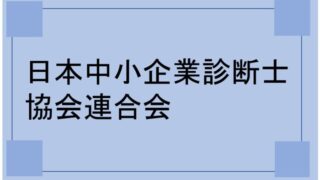
中小企業診断士は独学でも合格できる?
以下の記事にも書きましたが、完全な独学だと、
- 「自分で一から学習計画を立てる」
- 「テキストを読んで理解する(ベテラン講師の噛み砕いた講義を聴けない」
ところから始める必要があるので、どうしても効率が悪いのです。
■<関連記事>
中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2023年最新版 比較・ランキング
1年間でストレート合格を狙うためには、受験校の通学講座で講師に教えてもらったり、通勤講座のように隙間時間を利用してスマホ動画で学習したりするなど、効率化の工夫は欠かせない、と思います。
中小企業診断士の難易度 まとめ
いかがでしたでしょうか。
中小企業診断士は、難易度はかなり高いものの、他の士業のように独占業務があるわけではありません。
また、少しずつ知名度を上げているものの、今一つ世間に浸透している、とは言いにくいところがあります。
ですが、「中小企業の経営をサポートする」というニーズは非常に大きいものがありますし、その学習内容は「日本版MBA」と言われるとおり、とても充実しています。
そのようなことから、最近少しずつ人気も上がってきているように感じます。
また、前述のとおり、「AIに置き換えられる可能性が低い仕事」として報道されていたように、将来性の高い仕事でもあります。
今回の記事でみたとおり、難易度も相応に高く、簡単に取得できる資格ではありませんが、チャレンジに値する資格であると言えるでしょう。
■
最後に、これから中小企業診断士試験に挑戦したい方におすすめな情報です。
中小企業診断士試験に最短合格するための市販の勉強法書籍が、今だけ無料で手に入るので、ぜひ入手してください。
というのも、現在、難関資格の予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしているのです。
中小企業診断士の資格に少しでも興味・関心のある方にはメリットしかないので、もらわない理由はありませんよね。要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
参考:中小企業向けコンサルとは?大手企業一覧からランキング、魅力まで徹底解説
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |