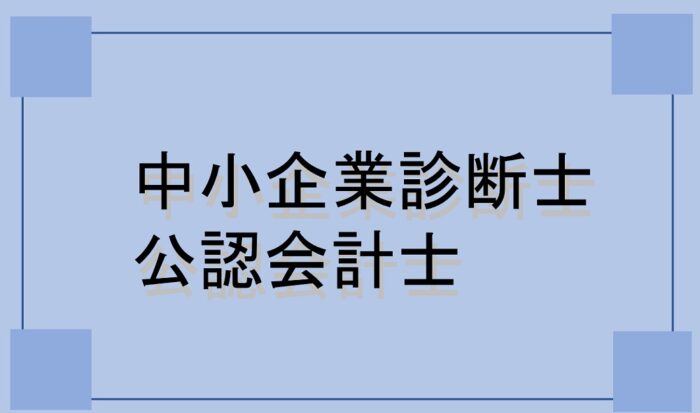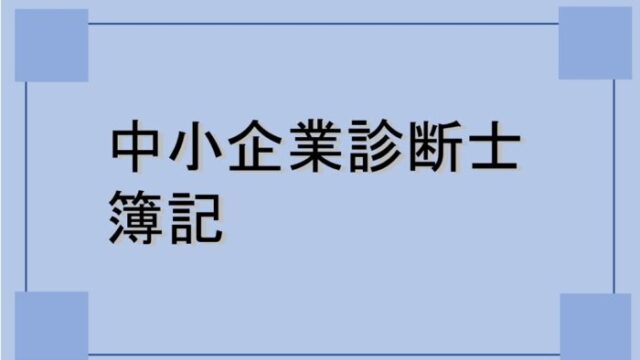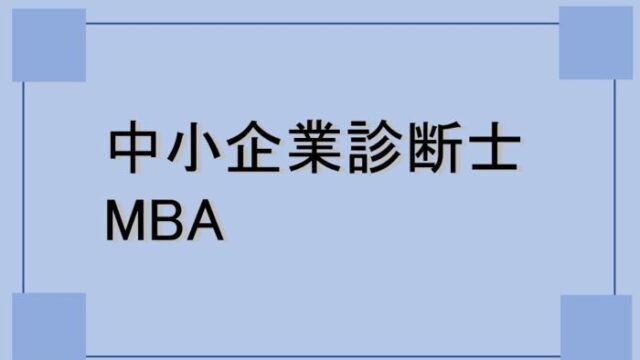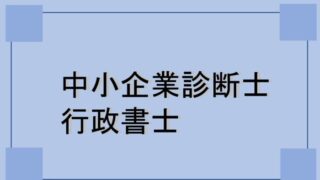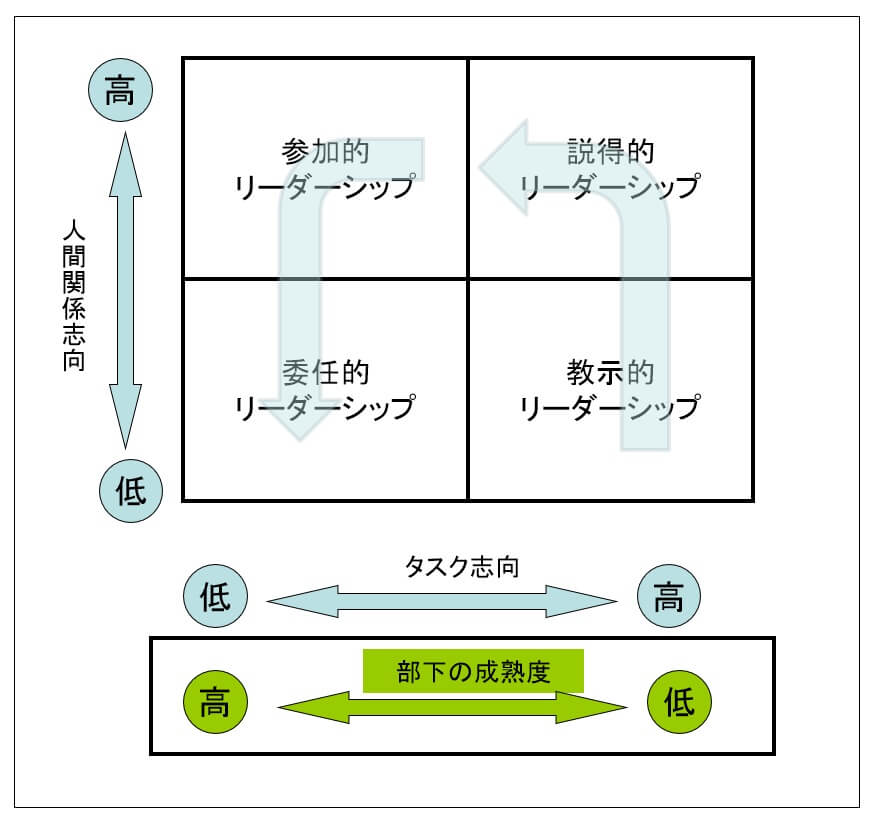目次
中小企業診断士と公認会計士の業務内容の違い
今回は、中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスについて、考えてみたいと思います。
士業の中でも、中小企業診断士と公認会計士は人気の資格です。特に公認会計士は、医師/弁護士等と共に「三大国家資格」と呼ばれたりしますね。
どちらも難易度が高いですが、その分、就職・転職活動でアピールしたり独立開業したりするに当たって役立ちます。
まずは中小企業診断士と公認会計士の業務内容の違いから見ていきましょう。
- 中小企業診断士は中小企業の経営に関する相談の対応やアドバイスをクライアントに提供する
- 公認会計士は企業の会計監査や財務状況のチェック、コンサルタントがメインの業務
以上のように、業務内容は異なるものの、どちらの資格も、顧客やクライアントの依頼を受けて業務を提供し、様々な面から企業活動をバックアップします。
そのため、顧客や企業からは、非常に頼りにされる存在です。
【結論】中小企業診断士と、公認会計士のダブルライセンスはおすすめ! ただし、向かないケースもある!
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスは価値が高く、シナジーもあるため、基本的にはおすすめできる組み合わせです。
ただし、両資格の難易度・合格までに必要な勉強時間・受験者の状況などを考慮すると、「一概に、すべての人に向くとは言えない」という結論になります。
以上のことを詳しく説明するため、まずは両資格の難易度から見て行きましょう。
中小企業診断士と公認会計士の資格を試験の難易度で比較
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスを考えるに当たり、資格試験の難易度は気になるところですよね。
試験の難易度をはかる1つの指標として、両試験の合格率をチェックしてみましょう。
| 中小企業診断士の合格率 | 1次試験と2次試験を合わせると4%~5%程度 |
| 公認会計士の合格率 | 10~11%程度 |
合格率だけみると、中小企業診断士の方が低いですが、実際は、中小企業診断士よりも公認会計士の方が遥かに難しい資格になっています。
前述のとおり「三大国家資格」と言われるほど、公認会計士試験は国家資格試験の中でも最上級のもので、ちょっとした勉強で取得できるものではありません。
とはいえ、中小企業診断士も合格率の低さから分かるとおり、かなり難易度が高いと心得ておかないといけません。
※中小企業診断士の難易度については、下記の記事も参考にしてください。
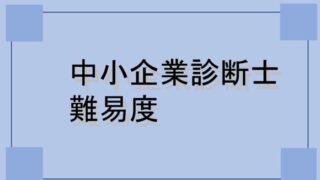
中小企業診断士と公認会計士を資格取得までの勉強時間で比較
今までのスキルや学習法によって変わりますが、中小企業診断士と公認会計士は資格取得までにかかる勉強時間に違いがあります。
以下では、中小企業診断士と公認会計士を資格取得の勉強時間で比較してみました。
- 中小企業診断士の試験に合格するまでは1,000~1,200時間程度の勉強が必要
- 公認会計士の試験に合格するまでには3,000時間~3,500時間の勉強が必要
このように、中小企業診断士と比べ、公認会計士は3倍以上の勉強時間を費やさないといけません。
公認会計士の試験の方が遥かに難易度が高いわけです。
※中小企業診断士試験の勉強時間については、下記の記事も参考にしてみてください。

中小企業診断士と公認会計士の試験を受験者層で比較
中小企業診断士の受験者層でもっとも多いのは、30~40代のビジネスマンです。企業での仕事を一通り覚え、さらにステップアップ・キャリアアップを目指している層といえるでしょう。
中小企業診断士試験はビジネス領域全般から出題されますから、社会人の方が対処しやすいということもありますし、現実問題として、働きながら合格を目指せるのは、1,000時間程度で取れる資格まで、という考え方もあります。
※この考え方でいくと、働きながら目指せるのは、中小企業診断士の他、行政書士・社労士ぐらいまでが現実的となります。
一方の公認会計士ですが、こちらの受験者でもっとも多いのが20代~30代と、中小企業診断士と比べて若年層が中心となっています。さらに公認会計士受験者には、大学生や受験勉強に専念する方も多く、多大な時間を使って公認会計士に合格するわけです。
そして、公認会計士に合格した若年層の多くは、まずは監査法人の入社を目指します。後々独立するにしても、まずは公認会計士の独占業務である「監査業務」を実践することが重要だからです。
若年層が公認会計士となり、その後、中小企業診断士取得を目指すのは有望
中小企業診断士と公認会計士の受験者層の違いから、ダブルライセンスが向く人・向かない人が明らかになります。
まず、学生や受験専念者が長時間かけて公認会計士になった後、公認会計士の仕事をしながら、中小企業診断士を目指すのは、現実的ですし、おすすめです。
独占業務の「監査業務」だけでなく、経営コンサルティング能力を磨くことで、様々な企業案件に対応できます。中小企業診断士は、働きながらでも最短1年程度で取得できますから、さらなるキャリアアップに適しています。
先に中小企業診断士を取り、その後、公認会計士を目指す人は少数派
一方、中小企業診断士の受験者層は30~40代のビジネスマンが中心でした。彼らは企業で働きながら、専門能力を磨くために中小企業診断士を狙います。
合格後は、従来から務めている企業で能力を活かしたり、転職したり、独立したりと様々なルートがあります。しかし、その時点から、さらに働きながら公認会計士を目指すのは現実的ではないでしょう。
もちろん、大学生などの若手のなかには、将来を見据えて「中小企業診断士と公認会計士、両方取ろう」と考えている人もいるかも知れません。そのような場合は、ぜひダブルライセンスを目指して欲しいと思います。
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスのメリット
ここからは、中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスのメリットについて、より詳しく解説していきます。
お互いの資格の能力を補うことができる
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスのメリットは、お互いの資格の能力を補えるところです。
中小企業診断士と公認会計士は、下記のように得意分野と不得意分野があります。
<中小企業診断士>
得意分野:メインの業務がコンサルティングであり、戦略立案や組織運営、オペレーションなどの実務に強い
不得意分野:財務分析や数字の管理については、会計士や税理士ほどには強くない
<公認会計士>
得意分野:経理・財務データを分析し、改善案を策定する監査や税務に圧倒的に強い
不得意分野:戦略・組織・オペレーションなどの実務は学んでいない
つまり、中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスがあれば、財務面と経営面(実務面)の両方の視点から企業活動をサポートできるわけです。
公認会計士としてのスキルを活かして財務データの数字を分析して問題点を把握し、中小企業診断士の問題解決能力を活かせばより高度なレベルで経営のアドバイスができるようになりますよ。
企業の経営者も安心して相談できるようになりますので、顧客やクライアントの満足度が高まるのは間違いありません。
経営コンサルタントとしての活躍の場所を広げられる
中小企業診断士も公認会計士も、普段の業務でコンサルティングを行うことがあります。
例えば、公認会計士が行うコンサルティング業務は次の3つが代表的です。
- 適切かつスピーディな財務諸表作成を支援する会計アドバイザリー業務
- 企業同士の合併や組織再編が行われる場合に支援するM&Aアドバイザリー業務
- 経営状況の悪化した企業に対して再生を図る支援を行う事業再生アドバイザリー業務
もし中小企業診断士の資格も取得してダブルライセンスになっていれば、経営コンサルタントとしての活躍の場所を広げられます。
中小企業診断士の経営面に関する深い知識は、公認会計士のコンサルタント業務にも役立つわけです。
科目免除制度を受けられる
科目免除制度を受けられるのは、中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスのメリット。
中小企業診断士の試験を受けるに当たり、次の資格保有者は一部の科目の免除申請ができます。
- 経済学・経済政策:「大学等の経済教授」「准・旧助(通算3年以上)」「経済学博士」「公認会計士試験合格」「不動産鑑定士」
- 財務・会計:「公認会計士」「公認会計士試験合格者」「税理士」「会計士補となる有資格者」
- 経営法務:「弁護士」「司法試験合格者」「旧司法試験第2次試験合格者」
- 経営情報システム:「技術士(情報工学部門登録者に限る)」「情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者」
参考:1次試験受験案内
公認会計士の資格を持つ方は、中小企業診断士の「経済学・経済政策」と「財務・会計」の試験科目が免除される仕組みです。
試験免除の特例措置を受ければ、できる限り勉強時間を短縮してダブルライセンスを目指せるでしょう。
※中小企業診断士試験の科目免除について詳しくは、下記の記事も参考にしてください。
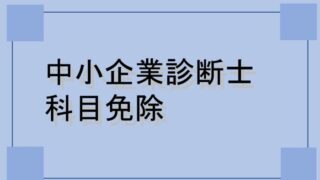
独立開業で役立つ
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスは、独立開業で役立てることができます。
実際のところ、中小企業診断士の資格を取得するだけで独立開業してすぐに稼ぐのは難しいのが現状です。
他の士業の資格とは違い、中小企業診断士には資格保有者しかできない独占業務がありません。
そのため、中小企業診断士の資格を取得する方の多くは、就職や転職で活かす形になります。
しかし、中小企業診断士に加えて公認会計士の資格も同時に持っていれば、独立開業して他の士業と差別化を図れるのがメリットです。
中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスになり、公的機関のコンサルタントの仕事をこなしたり人脈ネットワークを広げたりすれば、独立開業の成功率をグンと高められるでしょう。
まとめ
中小企業診断士と公認会計士の業務内容や試験の違い、ダブルライセンスのメリットについておわかり頂けましたか?
「関連する資格ではないのでは?」とイメージしている方はいますが、中小企業診断士と公認会計士のダブルライセンスになるとお互いの資格の能力を活かしてコンサルティング業務で役立てられます。
特に若手の方で先に公認会計士の資格を取得された方は、中小企業診断士とのダブルライセンスも検討してみてください。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |