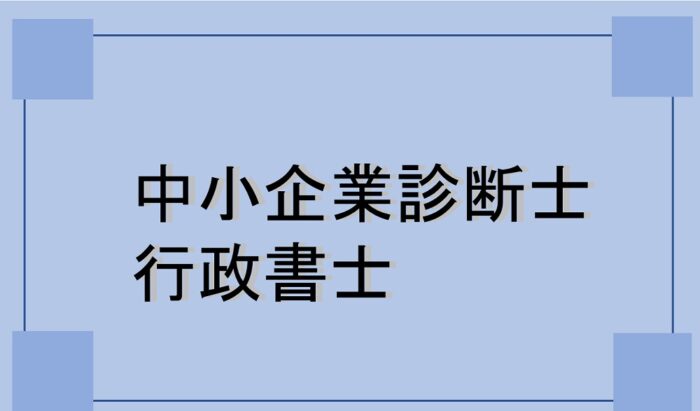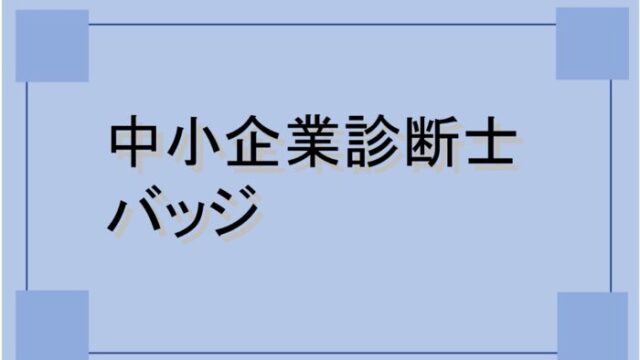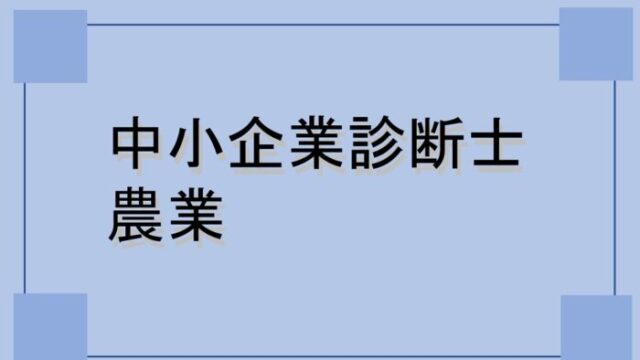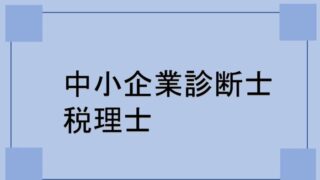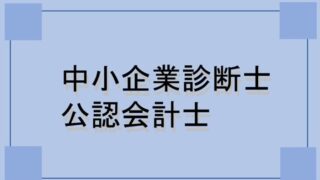目次
中小企業診断士と行政書士の業務内容の違い
中小企業診断士と行政書士は、どちらも人気の国家資格です。
下記のデータを見ればわかる通り、中小企業診断士の受験者数は年々増えています。
| 試験年度 | 中小企業診断士の受験者数(一次試験) | 行政書士の受験者数 |
|---|---|---|
| 2015年 | 15,326名 | 44,366名 |
| 2016年 | 16,024名 | 41,053名 |
| 2017年 | 16,681名 | 40,449名 |
| 2018年 | 16,434名 | 39,105名 |
| 2019年 | 17,386名 | 39,821名 |
行政書士の受験者数は減っていますが、中小企業診断士よりも多いと考えると人気なのは間違いありません。
そもそも、中小企業診断士と行政書士はどう違うのか、それぞれの業務内容を見ていきましょう。
- 中小企業診断士は問題を抱えている中小企業に対して、経営面の相談や課題解決の手助けを行う
- 行政書士は会社設立や店舗開業を中心に、許認可に関する公的書類の作成や提出代行を行う。その他、権利関係・事実関係の書類作成代行など
中小企業診断士と行政書士の業務内容は、そこまで似通っているわけではありません。
しかし、どちらも経営者(事業者)にとって必要なサービスを提供する国家資格であり、相乗効果も高いので、2つの資格を保有するダブルライセンスはおすすめですよ。
中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスのメリット!
この項では、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスにどのようなメリットがあるのか解説していきます。
それぞれの資格を単体で取得するよりも、両方持っている方が効果が高まります。
2つの資格の保有で普段の仕事や業務に活かすことができますので「中小企業診断士と行政書士のどちらが良いの?」と悩んでいる方は参考にしてみてください。
経営コンサルタントを行う企業に許認可のアドバイスができる
中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスのメリットは、経営コンサルタントを行う企業に許認可申請に関するアドバイスも同時に行えるところです。
クライアントの立場に立ってみると、別々の専門家に依頼する手間と費用を省くことができます。
行政書士が作成できる書類は、次の3つが代表的です。
- 官公署に提出する書類の作成とその代理(飲食店などの営業許可証)
- 権利義務に関する書類の作成とその代理(会社の定款や遺言書)
- 事実証明に関する書類の作成とその代理(車庫証明など)
これらの業務は、行政書士に許可された独占業務です。
資格保有者にしかできない独占業務ですので、中小企業診断士の資格だけを持つ人と比べて業務の幅が広がるわけですね。
中小企業診断士の能力を活かして経営サポートやコンサルティングを行い、同時に書類の作成や申請も請け負えば企業から大きな信頼を得られるでしょう。
就職や転職で強い武器になる
行政書士の資格があれば、以下への就職・転職に有利です。
- 書類の作成や通常の業務を行う「法務事務所」
- 法律事務員として法令の調査を行う「弁護士事務所」
- 一般企業の正社員として法律的な文書作成を行う「会社の法務部」
資格を持つと自分のアピールポイントが増えますので、他者と差別化を図ることができます。
しかし、行政書士自体は就職や転職で強い資格とは言えません。
もし中小企業診断士とのダブルライセンスになれば、あらゆる職場で活躍できる知識を身につけられます。
サラリーマンとしての市場価値を高められますので、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスは転職の強い武器になるわけです。
「転職して年収をアップしたいけど、どうやって自分をアピールすれば良いのかわからない…」と悩んでいる方は、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスを目指してみてください。
※中小企業診断士資格を活かした転職については、下記の記事も参考にしてみてください。
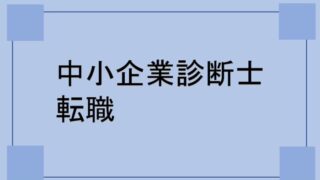
独立開業する際に役立つ
独立開業は、「顧客を獲得できれば年収がアップする」「働く量やタイミングを自由に決められる」「自分のやりたい仕事を追求できる」という3つが大きなメリットです。
しかし、中小企業診断士には独占業務がありませんので、独立開業して利益を出し続けるのはハードルが高いと心得ておかないといけません。
そこで役立つのが中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスです。
行政書士には役所に届出を行う許認可等の書類作成や権利義務に関する書類の作成など、資格保有者にしか認められていない独占業務があります。
行政書士の独占業務を集客のきっかけにして、中小企業診断士の知識を活かして多角的なコンサルティングができるようになるのです。
様々な知識や能力をカバーできるのはダブルライセンスの魅力ですので、独立開業を検討している方は中小企業診断士と行政書士の両方を取得してみましょう。
※中小企業診断士の独立開業について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
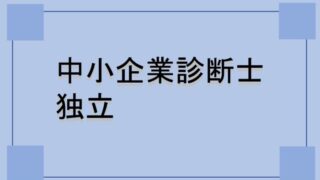
中小企業診断士と行政書士を試験の難易度で比較!
中小企業診断士と行政書士は、どちらも「働きながら取得できる資格としては最難関クラス」の難易度と言われています。
簡単に取得できる国家資格ではありませんが、超難関である司法書士や公認会計士などの士業と比較してみると、そこまで難しくありません。
あまり長い期間を費やさなくても、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスを目指すことができますよ。
まずは中小企業診断士と行政書士の試験の合格率がどのくらいなのか見ていきましょう。
| 試験年度 | 中小企業診断士(1次) | 中小企業診断士(2次) | 行政書士 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 21.7% | 18.5% | 10.10% |
| 2014年 | 23.2% | 24.3% | 8.27% |
| 2015年 | 26.0% | 19.1% | 13.1% |
| 2016年 | 17.7% | 19.2% | 9.95% |
| 2017年 | 21.7% | 19.4% | 15.7% |
| 2018年 | 23.5% | 18.8% | 12.7% |
単純に合格率だけで比較してみると、中小企業診断士よりも行政書士の方が低い傾向があります。
合格率が10%を切る年度もありますので、10人が受験して一人しか受からない計算です。
しかし、行政書士試験とは違って中小企業診断士の試験は、1次試験と2次試験の両方を突破しないといけません。
2つの試験に合格しないといけない点を加味すると、中小企業診断士の方が大変です。
※中小企業診断士の難易度については、下記の記事も参考にしてください。
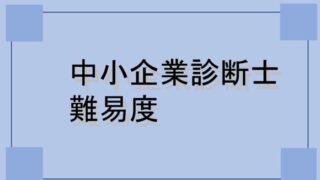
中小企業診断士と行政書士を資格取得までの勉強時間で比較!
司法書士や税理士と比較してみると、中小企業診断士と行政書士の試験は難易度が低くなっています。
それでも、大勢の方が受験する人気の資格ですので、合格するにはある程度の期間に渡って勉強を続けないといけません。
以下では、中小企業診断士と行政書士の資格を取得するまでの勉強時間がどのくらいなのかまとめてみました。
- 中小企業診断士に合格するまでの勉強時間の目安は1,000時間~1,200時間
- 行政書士に合格するまでの勉強時間の目安は500時間~800時間
中小企業診断士と比較してみると、行政書士試験の方が短い勉強時間で合格できます。
1回の試験に合格すればOKですので、短期間で行政書士に合格している方は少なくありません。
しかし、中小企業診断士も行政書士も一緒ですが、試験に合格するまでの勉強時間には個人差があります。
法律の知識のない初学者は当然のように時間がかかりますし、独学よりも予備校や通信講座の方が短い時間で合格可能です。
完全に独学で中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスを目指すのは意外とハードルが高いので、できる限り通信講座を利用して正しいカリキュラムに沿って勉強を継続しましょう。
※中小企業診断士試験の勉強時間については、下記の記事も参考にしてみてください。

中小企業診断士と行政書士の資格を取得する順番は?
中小企業診断士と行政書士の資格を取得する順番は、個人の考えによって大きく変わります。
コンサルティング業務をメインでこなしていく予定の方は、最初に中小企業診断士の資格を取得した方が良いでしょう。
一方で法務事務所や弁護士事務所に転職して将来的に独立開業する予定であれば、最初に行政書士の資格を取得するのがベストです。
自分自身の将来のキャリアを見据えて順番を決めるのが大切です。
まとめ
中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスになることで、どのようなメリットがあるのかおわかり頂けましたか?
中小企業診断士の経営戦略の知識と行政書士の許認可申請の書類作成業務を組み合わせれば、独立開業するのも夢ではありません。
どちらも難易度が激高の資格ではありませんので、ステップアップを考えている方は中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスを目指してみてください。
【参考】本記事執筆にあたり、以下の行政書士事務所のWebサイトを参考にさせて頂きました。
“事業と暮らしの法務サポーター” 高村行政書士事務所(埼玉県桶川市)
自動車登録・行政書士廣澤事務所・長野市
川越行政書士事務所
会社設立代行センター福岡