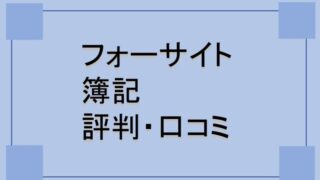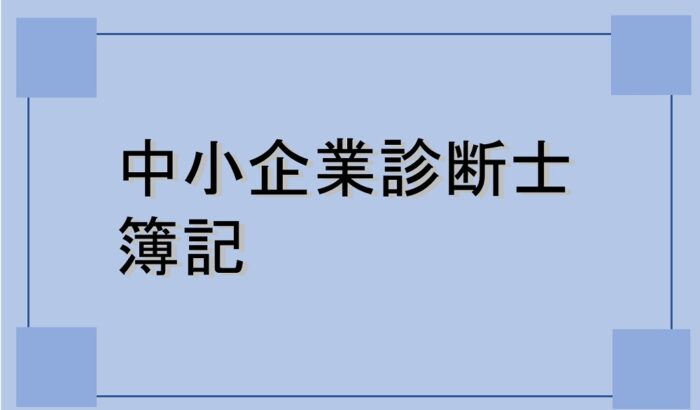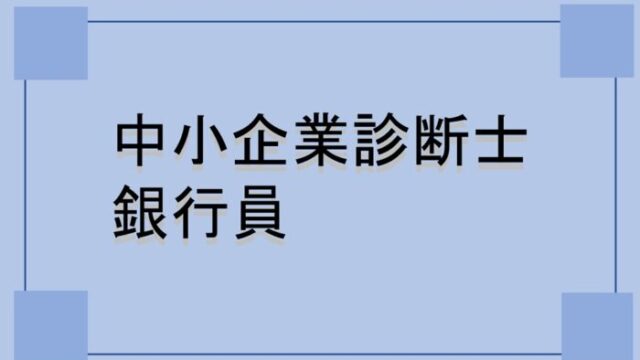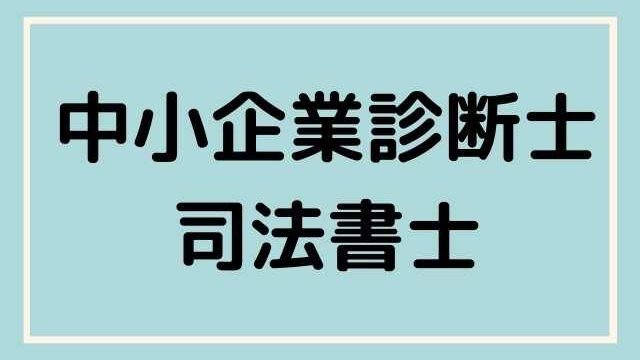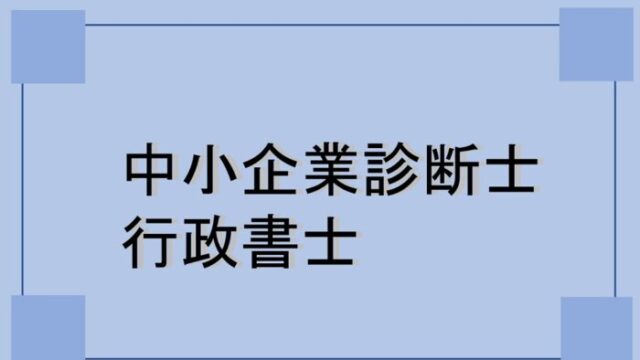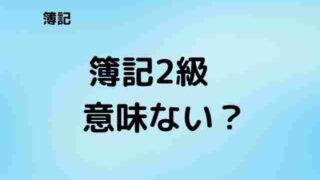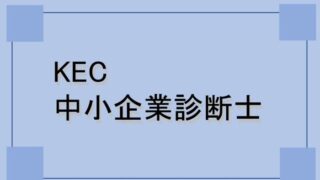目次
中小企業診断士と簿記の違い!
様々な資格の中でも、中小企業診断士と簿記の資格はいずれも人気の資格です。
まずは2つの資格がどのようなものか大まかな違いを見ていきましょう。
- 中小企業診断士は経営コンサルタントを認定する資格で、企業の経営に関わる知識を横断的に身につけた者を指す
- 簿記は日々の経営活動の記録や整理を行い、経営成績と財政状態を明らかにできる技能を指す
中小企業診断士も簿記も、年齢・性別・学歴・職歴などの受験資格は特に設定されていません。
つまり、誰でも中小企業診断士と簿記の試験を受験できますよ。
中小企業診断士と簿記の試験内容の違い!
中小企業診断士と簿記は、試験内容に大きな違いがあります。
中小企業診断士の1次試験の内容は次の7科目です。
- 企業経営理論:戦略・組織・マーケティングなど企業経営の基本的な考え方を学ぶ
- 財務・会計:財務会計や管理会計など企業経営の定量的分析手法を学ぶ
- 運営管理:生産管理や店舗販売管理などものづくりと売り方を学ぶ
- 経済学・経済政策:マクロ・ミクロ経済学を中心に経済活動と政策の原理を学ぶ
- 経営情報システム:情報処理技術や経営情報管理を中心にIT関連を学ぶ
- 経営法務:会社法や知的財産など企業活動に関する法律知識を学ぶ
- 中小企業経営・政策:中小企業の実態と支援施策を学ぶ
資格名からもわかる通り、中小企業の経営に関わる試験科目で占めています。
今度は簿記2級を例にどのような試験内容で構成されているのか見ていきましょう。
- 商業簿記・会計学:「簿記の基本原理(記帳内容の集計や把握)」「諸取引の処理」「株式会社会計」
- 工業簿記・原価計算:「工業簿記の本質」「原価計算」「労務費計算」「製造間接費計算」「標準原価計算」「直接原価計算」
簿記3級の試験内容は商業簿記、簿記2級の試験内容は商業簿記に加えて工業簿記も加わります。
簿記検定と聞き、経理や財務を担当する人に必要な資格だとイメージしている方は少なくありません。
しかし、実際にはビジネスパーソンに欠かせない基礎的な知識を身につけられますので、簿記はあらゆる業種や職種で役立ちます。
中小企業診断士と簿記のダブルライセンスのメリット!
更なるステップアップを図るために、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスはおすすめ!
異なる複数の資格を保有している方をダブルライセンスと呼びます。
中小企業診断士と簿記は関連性の深い資格ですので、2つを持っていれば普段の業務や転職に役立てられるわけです。
この項では、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスのメリットについてまとめてみました。
試験の関連性が高い
中小企業診断士と簿記のダブルライセンスがおすすめな主要な理由の1つは、試験の関連性が高いことです。
先に簿記3級や簿記2級の資格を持っていると、中小企業診断士の勉強をスムーズに進められますよ。
中小企業診断士試験の中では、財務・会計が簿記との関連性が非常に高い科目です。
財務・会計は中小企業診断士1次試験と2次試験の両方で出題されますので、合格のためにはきちんと押さえておくことが必要。
なお、中小企業診断士の2次試験は、次の4種類の試験科目にわかれています。
- A:事例Ⅰ(組織や人事に関する内容)
- B:事例II(マーケティング関連)
- C:事例III(生産管理の関連)
- D:事例IV(財務会計の関連)
このうち、事例IVが、財務・会計に関する出題となります。
簿記2級を持っていると商業簿記・工業簿記の関する幅広いスキルを獲得できますから、中小企業診断士の1次試験・2次試験の両方におおいに役立つわけです。
転職で他者よりも有利になる
転職で他者との差別化を図りたいのであれば、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスを目指しましょう。
中小企業診断士の資格だけでも、広範な知識を保有するため幅広い視点でクライアント企業の経営に関わることができます。
しかし、簿記2級や簿記1級と組み合わせることで、更に専門分野を明確にできるわけです。
転職する気がない企業勤めの方でも、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスでキャリアアップに繋がりますよ。
他の資格と比べると学習時間が短い
中小企業診断士と相性の良い資格は、「税理士」「公認会計士」「宅建士」「不動産鑑定士」と様々!
自分の専門分野を見極めてダブルライセンスを目指せば普段の業務で大いに活かせますが、国家資格を取得するまでにかなりの時間がかかります。
一方で簿記検定の合格までの学習時間は下記のように、比較的短いのが特徴です。
- 簿記3級は100時間程度が目安
- 簿記2級は250時間程度が目安
1日の学習時間を長くすれば、2週間~1ヵ月で簿記3級の試験に合格するのも不可能ではありません。
税理士や公認会計士と比べて試験が簡単なのは、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスのメリットです。
独立開業する際に役立つ
独立開業する予定の方は、中小企業診断士と簿記のダブルライセンスは特におすすめ。
中小企業診断士のライセンスのみでも独立・開業はできますが、次の3つの理由で簿記検定も取得したほうがよいのです。
- 日々の経理ができていれば毎年の確定申告が楽になる
- 取引の記帳を行うことで日々のお金の流れを正確に把握できる
- 複式簿記で正確な財務諸表を作成できると経営分析に役立つ
中小企業診断士だけでも財務・会計の科目があるので経理・帳簿はある程度できます。
しかし、簿記を学習しながら仕訳実務に徹底的に馴れることで、独立開業時の経理・帳簿作業に自信を持って取り組むことができるようになります。
中小企業診断士と簿記を試験の難易度で比較!
「中小企業診断士と簿記では、どの程度難易度が違うの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
そこで、この項では中小企業診断士と簿記の難易度を比較するために、受験者の合格率で比べてみました。
まずは中小企業診断士の1次試験と2次試験の合格率のデータから見ていきましょう。
| 1次試験の年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 14,252人 | 3,094人 | 21.7% |
| 平成26年 | 13,805人 | 3,207人 | 23.2% |
| 平成27年 | 13,186人 | 3,426人 | 26.0% |
| 平成28年 | 13,605人 | 2,404人 | 17.7% |
| 平成29年 | 14,343人 | 3,106人 | 21.7% |
| 平成30年 | 16,434人 | 3,236人 | 21.7% |
| 2次試験の年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 4,907人 | 筆記915人、口述910人 | 18.5% |
| 平成26年 | 4,885人 | 筆記1,190人、口述1,185人 | 24.3% |
| 平成27年 | 4,941人 | 筆記944人、口述944人 | 19.1% |
| 平成28年 | 4,394人 | 筆記842人、口述842人 | 19.2% |
| 平成29年 | 4,279人 | 筆記830人、口述828人 | 19.4% |
| 平成30年 | 4,978人 | 筆記906人、口述905人 | 18.8% |
今度は簿記2級の受験者数や合格者数、合格率のデータを見ていきます。
| 試験年度 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月(第145回) | 78,137人 | 60,238人 | 15,075人 | 25.0% |
| 2017年6月(第146回) | 58,359人 | 43,767人 | 20,790人 | 47.5% |
| 2017年11月(第147回) | 63,757人 | 47,917人 | 10,171人 | 21.2% |
| 2018年2月(第148回) | 65,560人 | 48,533人 | 14,384人 | 29.6% |
| 2018年6月(第149回) | 52,694人 | 38,352人 | 5,964人 | 15.6% |
| 2018年11月(第150回) | 64,838人 | 49,516人 | 7,276人 | 14.7% |
| 2019年2月(第151回) | 66,729人 | 49,766人 | 6,297人 | 12.7% |
| 2019年6月(第152回) | 55,702人 | 41,995人 | 10,666人 | 25.4% |
簿記の試験は一度受験すればOKですが、中小企業診断士は1次(マークシート)と2次(筆記、口述)の2つの試験の突破する必要があります。1次と2次のストレート合格率は4~8%程度と狭き門ですし、合格した後、実務にも従事しないと資格登録できないのです。
さらに、合格までの勉強時間を比較すると、簿記2級が約250時間、一方の中小企業診断士は1,000時間以上も必要です。
すなわち、中小企業診断士と簿記では、大きく難易度のレベルが異なると言えるでしょう。
中小企業診断士を簿記の級に置き換えると?
前述のとおり、中小企業診断士試験において、一次試験の財務会計の科目、および二次試験の事例IVにおいては簿記の知識が必須です。
診断士試験と被る出題分野については、簿記2級が40%程度、簿記1級は65%ほどとされています。
「診断士試験のレベルは簿記の何級?」という質問にはカンタンに応えられませんが、少なくとも、簿記2級レベルがあれば、かなり有利だといえます。
※中小企業診断士の難易度については、下記の記事も参考にしてください。
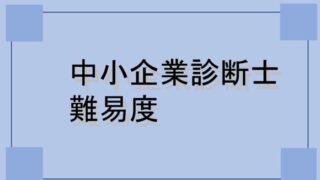
中小企業診断士と簿記のどちらの資格がおすすめ?
中小企業診断士と簿記は、ダブルライセンス者がいるほど相性の良い資格です。
しかし、どちらの資格も持っていない方は、中小企業診断士と簿記のどちらが良いのか迷ってしまいますよね。
今の仕事内容によって変わりますが、次の基準で中小企業診断士の資格を取得するのか簿記の合格を目指すのか決めましょう。
- 財務や経理のスペシャリストを目指すなら簿記1級がおすすめ
- 経営やビジネス全般の専門家を目指すなら中小企業診断士がおすすめ
中小企業診断士と簿記1級は、両方ともそれなりに難易度の高い資格です。
今の仕事や転職で大いに活かすことができますので、中小企業診断士や簿記を目指してみてください。
中小企業診断士と簿記の資格を取る順番は?
中小企業診断士と簿記のダブルライセンスを目指すに当たり、まずは比較的勉強時間が短くて済む簿記2級を取得し、その後に中小企業診断士を目指す方法がおすすめです。
ある程度の簿記の知識を持っている方であれば、中小企業診断士の勉強も進めやすくなります。
まとめ
以上のように、中小企業診断士と簿記の試験内容の違いについて解説しました。
難易度で比較してみると簿記2級よりも、中小企業診断士の方が難易度が高くなっています。
簡単に合格できる資格ではありませんが、普段の業務や転職で中小企業診断士と簿記のダブルライセンスはおおいに役立ちます。
一部の試験内容も被っていますので、簿記2級を取得した後に中小企業診断士の合格も目指してスキルアップしましょう。