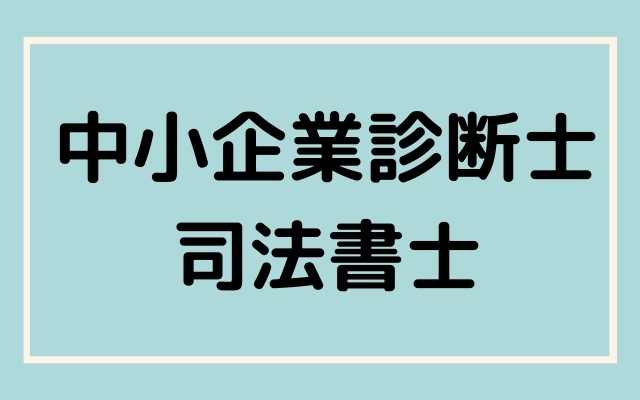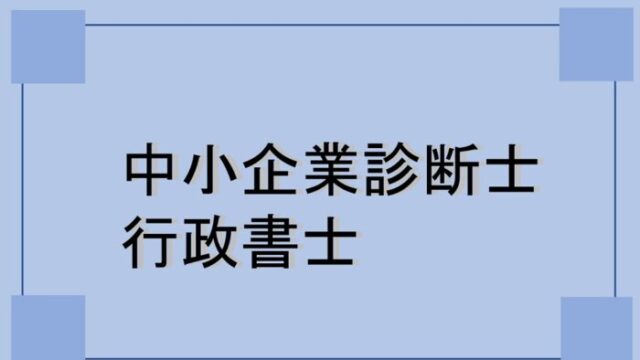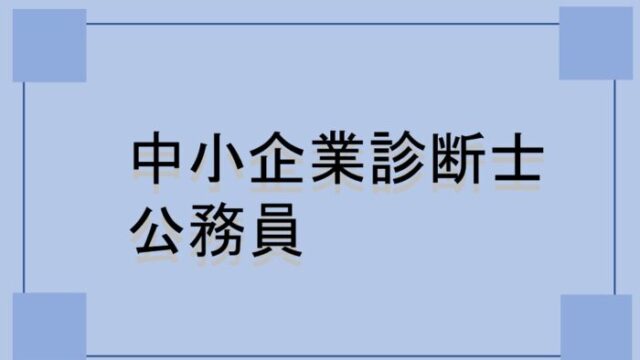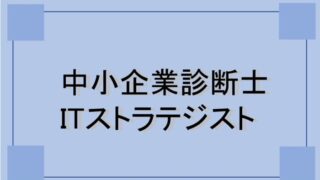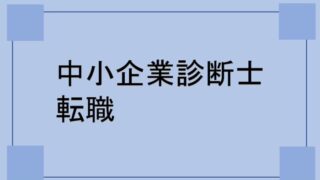こんにちは、トシゾーです。
今回は中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスについての記事です。
司法書士の主業務は登記申請、一方、中小企業診断士の主業務は経営コンサルティングなので、一見シナジーは小さいように思えます。
しかし、診断士業務の種類によっては、司法書士の業務が大きく関わってきます。
たとえば、中小企業の事業承継やM&Aなどを実施する場合、会社の登記である商業登記の変更は避けて通れません。
また、シナジーが小さいということは単純に業務の幅が広がるということでもあります。
「不動産登記や商業登記に強い経営コンサルタント」という方は、そうそう居ないので、独自のポジションを築くことができるかも知れません。
ただし、中小企業診断士と司法書士、いずれも取得までに時間のかかる難易度の高い試験のため、ダブルライセンスを狙うかどうかは慎重に検討すべきでしょう。
以下の記事では、ダブルライセンスの詳細や具体的なメリットなどについて説明していますので、興味のある方はチェックしてみてください。
なお、中小診断士試験の「最速勉強法」ノウハウについて、現在、資格スクールのクレアールが、市販の受験ノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
もし、あなたが中小企業診断士の資格取得を目指しているのでしたら、無料【0円】なので、そちらもチェックしてみてください。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
中小企業診断士と司法書士の業務内容の違い
数多くの士業の中でも、中小企業診断士と司法書士は人気の資格です。
同じような資格なのではとイメージしている方はいますが、中小企業診断士と司法書士は業務内容や業務範囲で大きな違いがあるのが特徴です。
そこでまずは、中小企業診断士と司法書士の業務内容の違いを大まかに見ていきましょう。
- 中小企業診断士は、中小企業の経営状況の分析や改善策の提案を中心に、コンサルティング業務をメインで行う。しかし、中小企業診断士は経営に関して幅広く対応するため、人によって活動している領域や内容は様々。
- 司法書士が取り扱う業務は、登記または供託に関する手続きの代理や簡易裁判所での代理人業務など
以上、2つの資格の違いが理解できましたでしょうか。
中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスのメリット
現在では顧客やクライアントからの依頼にワンストップで対応するために、複数の士業の資格取得を目指す方が増えました。
関連する2種類以上の資格を保有している方をダブルライセンスと呼びます。
2つの資格試験に合格しないといけませんので大変ですが、中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスは、小さくないメリットがあります。
この項では、中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスのメリットをいくつか挙げてみました。
両方の資格の「良いとこどり」した強みが持てる
司法書士の行う登記には、大きく「不動産登記」と「商業登記」に分かれます。
このうち、中小企業診断士の業務と相性がよいのは「商業登記」。しかし、「不動産登記」がダブルライセンスに全く使えないのか、と言えばそうではありません。不動産を扱う中小企業をターゲットにすれば、「不動産登記」の知識実務も役に立つはずです。つまり
- 商業登記・経営法務に強い経営コンサルタント
- 不動産系企業に特化した、不動産登記もできる経営コンサルティング
上記2つの立ち位置が考えられるわけです。
一般的に、司法書士のダブルライセンスと言えば、行政書士がメジャーですが、あまり競争の激しい道もどうかと。
中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスはニッチな分、独自の強みが光りますよ。
行政書士と司法書士のダブルライセンスを目指すに当たり、一番のメリットは業務の幅が広がることです。
独立開業での成功率がアップする
中小企業診断士や司法書士の資格は、独立開業を視野に入れて取得します。
就職や転職でも役立ちますが、どちらかと言うと独立に向けた国家資格です。
もし中小企業診断と司法書士のダブルライセンスになれば、独立開業の成功率は大きくアップします。
難しい資格を2つも取得している事実や業務範囲の拡大で、顧客やクライアントをしっかりと確保できるようになるわけです。
もちろん、国家資格を持っているだけで全ての問題が解決するわけではありません。
中小企業診断と司法書士のダブルライセンスで満足するのではなく、「得意分野の業務を見つける」「士業間の人脈を広げる」「営業力&集客力を身につける」といった努力を積み重ねてください。
中小企業診断士と司法書士のダブルライセンスのデメリット
つづいて、デメリットを見てみましょう。
試験範囲が被らない
司法書士の試験科目は法令11科目。具体的には以下のとおりです。、
民法、不動産登記法、商法・会社法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、刑法、憲法
このうち、中小企業診断士試験の出題科目と被るのは、「商法・会社法」と「民法」が「経営法務の一部」として出題されるのみ。
中小企業診断士試験と司法書士試験は、ほぼ受験科目が被らないと考えたほうがよいでしょう。
両方の試験ともに難易度が高い
まず、中小企業診断士と司法書士の合格までに必要な勉強時間を見てみましょう
- 中小企業診断士試験に合格するまでの勉強時間は、1,000時間~1,200時間が目安
- 司法書士試験に合格するまでの勉強時間は、2,000時間~3,000時間が目安
司法書士は士業の中でもトップクラスで難易度が高いだけあり、とてつもなく長い勉強時間が必要だとわかります。
1日に3時間のペースで毎日勉強したとしても、合格までに2年~3年はかかる計算ですね。
中小企業診断士の試験の場合は、ある程度の法律の知識があれば1年間で合格するのも不可能ではありません。
しかし、司法書士は中小企業診断士よりも難易度が明らかに上ですので、数倍以上の勉強時間が必要だと覚悟しておくべきです。
以上、司法書士と中小企業診断士のダブルライセンスの取得は、最短でも3~4年以上はかかります。
本当にそれだけのコストを掛けて、あなたがやるべきことなのかを、十分に検討しましょう。
まとめ
以上のように、司法書士と中小企業診断士の「仕事内容」「勉強時間(難易度)」「ダブルライセンスのメリット・デメリット」を見て来ました。
他にはない、尖った強みを構築するのには、両社のWライセンスは向いています。
ただ、Wライセンスを取得するまでの投資も半端ないので、本当にこの2つの資格のダブルライセンスを取得すべきか、検討することが必要です。
【参考】本記事の執筆にあたり、下記の司法書士事務所のWebサイトを参考にさせて頂きました。