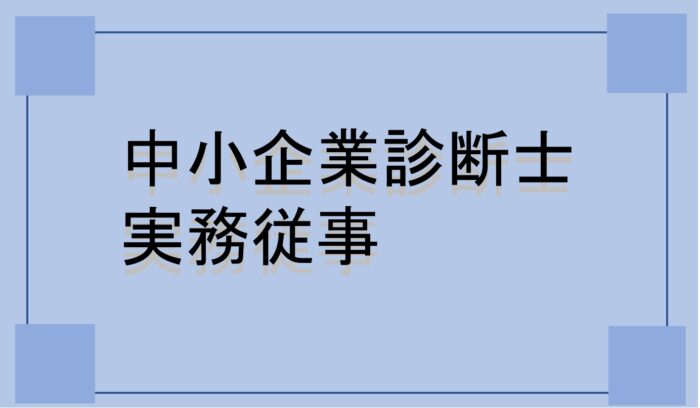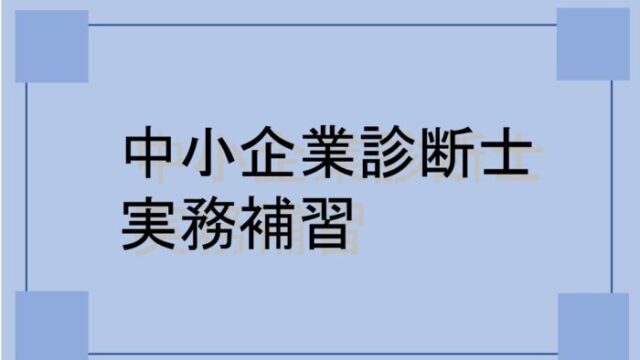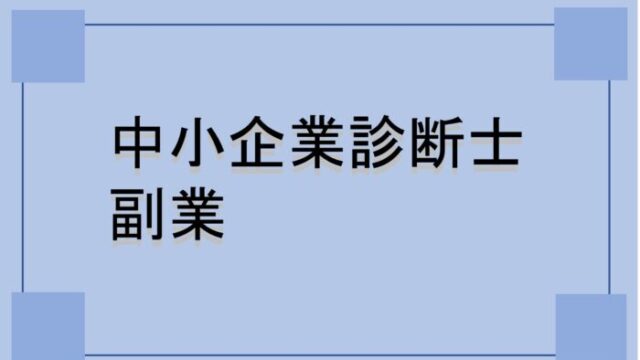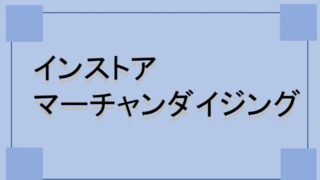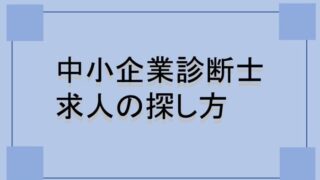目次
中小企業診断士の実務従事(診断実務)について
こんにちは、トシゾーです。
今回は中小企業診断士の実務従事(診断実務)について、ご説明します。
まず、中小企業診断士は、中小企業の経営者に対し「経営の診断及び経営に関する助言」を行うことが本来の仕事・実務で、これができる人に与えられる資格です。
その中小企業診断士の新規登録・更新の際に「診断及び助言の実務」を行ったかどうかを問われるのが実務従事。※実務従事は診断実務とも呼ばれます。
平素よりコンサルとして活動している方は、自分で実務従事の診断先を探せばよいのですが、一般企業に勤務している人など、自ら診断先を探せない人も多くいます。
そのため、日本中小企業診断士協会連合会などが実務従事の機会を提供してくれるのが実務補習です。
ざっくりと言ってしまえば、実務従事は中小企業診断士としての新規登録・更新のための要件のひとつであり、実務補習は実務従事の代わりの手段という感じになるでしょうか。
この中小企業診断士の実務従事をどう捉えておけばいいのかを見ておきましょう。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
中小企業診断士・新規登録と更新登録の実務従事要件
中小企業診断士の一次試験(マークシート)、二次試験(筆記)をクリアし、ほぼ全員合格の口述試験の終了後、中小企業診断士として登録するには、
- 実務補習を15日以上、受講する
- 診断実務に15日以上従事を行う
上記いずれかの登録要件を充たし、新規の登録申請をしなければなりません。
また、中小企業診断士として登録して以降、資格保持者としての能力を維持していることも担保されていないと資格制度としての中小企業診断士制度は成り立ちません。
そのために、中小企業診断士の登録有効期間は5年に限られ、資格を維持するためには更新要件をクリアすることが求められるシステムになっています。
中小企業診断士資格の更新登録の要件のひとつとして、
「診断助言業務に従事等30日以上」
という項目が定められています(他には理論政策研修の受講など)。
中小企業診断士の更新については以下の記事もご覧ください。
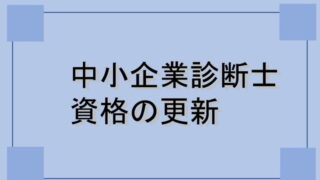
コンサルティング会社に勤めている人が中小企業診断士として新規登録する場合、あるいは、中小企業診断士として独立しコンサルティング業務を行っている人が更新登録する場合などは、実際に「診断及び助言の実務」、つまり実務に従事しているわけですから、申請書(診断助言実績証明書)に診断先企業の社長から判子をもらって申請すれば登録要件を満たすことができます。
それに対し、
多くの二次試験合格者や企業内診断士となった人は「診断及び助言の実務」、いわゆるコンサルティング業務に従事したことはないし、従事していないのでなんとかして実務従事の機会を作って欲しいと思うわけです。
2次試験合格後の実務補習
あたりまえですが、2次試験合格者はこれから中小企業診断士になろうとする人なので、既に資格を手にし日本中小企業診断士協会連合会に加入するなどして実務従事のチャンスを得られる資格ホルダーとは立ち位置が違います。
なので、2次試験合格者のほとんどは日本中小企業診断士協会連合会が実施する実務補習を受けて「実務従事15日以上」という要件を満たした上で、中小企業診断士登録申請を行うことになります。
日本中小企業診断士協会連合会が実施する実務補習は、15日間で2社、または8日間で1社の経営コンサルティングの実務を行います。
※以前は15日間で3社、または5日間で1社でしたが、令和6年度冬季実施分より変更されています。
※実務補習は平日も行われるため、一般企業等に勤務する参加者は、実務補習に参加するスケジュールの調整が非常に大変です。
1社分行う8日間の日程のコースと、2社分行う15日間の日程のコースがあり、費用がそれぞれ約10.5万円と約21万円かかります。
8日コースを選択した場合は、新規登録の実務従事要件の規定の日数である15日に満たないため、3年以内にあと1回、8日コースを受講することが必須となります。
2015年より、民間の企業も登録実務補習機関に認定されるようになりました。普段は研修事業を実践しているような企業が認定され、中小企業診断協会に準ずる実務補習のカリキュラムをサービスとして提供しています。
実務従事の代替といえる実務補習の中身とは
実務補習は指導員の指導・監督のもとに、実際に診断先となる中小企業に赴いてコンサルティングを行います。
数名のグループの受講者それぞれの担当を決め、診断先企業からのヒアリングを行った上で診断業務を行い、報告書を作成。
最終日に診断先企業への報告会を設定し、開催するというのが流れです。
二次試験合格後の実務補習は中小企業診断士の資格取得を目指す人が初めて経験するコンサルティング業務ということになります。
初めて会う他の受講者とチームを組み、短期間のなかで報告書と提案のプレゼンを完成させなければならない密度の濃い経験です。
ドキドキの初体験ですが、中小企業診断士試験合格者は志とポテンシャルがもともと高いためか、受講者それぞれにしっかりと何かを掴み取りその後の糧にしている方が多いように思います。
※実務補習については、より詳しく以下の記事で解説しています。実際に実務補習に参加した管理人の感想なども書いていますので、良かったら参考にしてください。
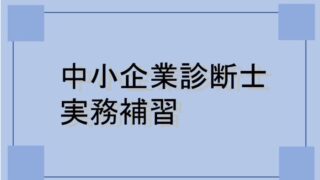
更新の際の実務従事
前に触れましたが、コンサルティング会社に勤務している中小企業診断士やコンサルティングを行っている独立診断士は、従事する仕事が実務従事ポイントに直結するため、5年に一度の更新登録に際し、別に何の問題もありません。
コンサルティングを仕事にしていない多くの企業内診断士が「実務従事の機会をどうやって作るか…」に苦労するケースが多いようです。
現実的には、
- 中小企業診断協会に加入して各種研究会に所属したり、様々な中小企業診断士のコミュニティに参加することで実務従事案件への応募・紹介を受ける。
- 知人や親戚のつてで知り合いの中小企業の診断をやらせてもらう。
- あるいは、これらと中小企業診断協会や民間の実務従事支援企業の費用のかかる実務補習を組み合わせて、5年間で30日分の実務従事ポイントを確保しています。
以前は少なかったのですが、最近では多くの民間の企業や実務従事支援のサポートをビジネスとして行っています。
Webで「実務従事」などのキーワードで検索すれば、さまざまな企業が案内や募集をしています。気になる方は確認したり相談したりしてみるのがよいでしょう。
注意点としては、民間の実務従事支援サポートは、一言で言えば『玉石混合』です。もしあなたが申し込みを考えるならば、可能な限り複数の候補を調べてください。ポイントは講師のスキルや知識、日程や計画などの点です。
費用を払って体験するわけですから、しっかり活用してあなたのスキル向上に役立つものを選ぶべきです。ぜひそういった課題の意識を持って取り組んでほしいと思います。
なお、中小企業診断士の資格の更新について、詳細は下記記事を参考にしてください。
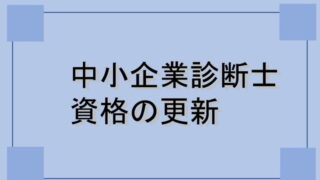
実務従事の証明書の提出
更新のために実務従事ポイントを30日分確保したら、その旨を証明することが必要です。
具体的には、申請書をダウンロードして必要事項を記入し、診断先等の判子を貰ったうえで、中小企業診断協会に提出することになります。
その際に使う申請書が「中小企業診断士関係様式」の「様式第18(診断助言業務実績証明書)」あるいは「様式第19(診断助言業務実績証明書)」のいずれか。
様式第18と様式第19の違いは以下のとおりです。
- 様式第18:公的機関等から派遣されて診断を行った場合に利用(公的機関等が発行)
- 様式第19:診断先から証明書の発行を受ける場合に利用(自らの顧問先など)
様式は日本中小企業診断士協会連合会の様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
まとめ
中小企業診断士が「何のための資格か」ということを考えると、実務従事が新規登録や更新登録の要件となっているのは、制度として納得のいくことではないでしょうか。
これから中小企業診断士になる人にとっての実務補習は、この資格の重みとやりがいの大きさを知ることができる貴重な機会です。
無事に一次、二次の難関試験を突破して、実務補習でコンサルタントの醍醐味とその感動を、是非、経験して欲しいと思います。
中小企業診断士の勉強法については、下記記事も参考にしてください。
中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2025年最新版 比較・ランキング
【おすすめオンライン講座】


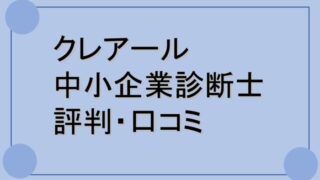
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |