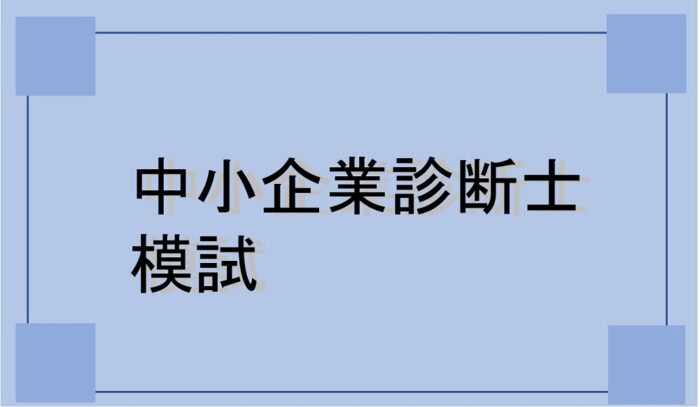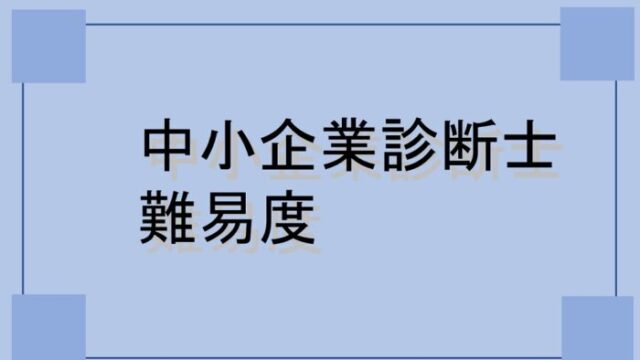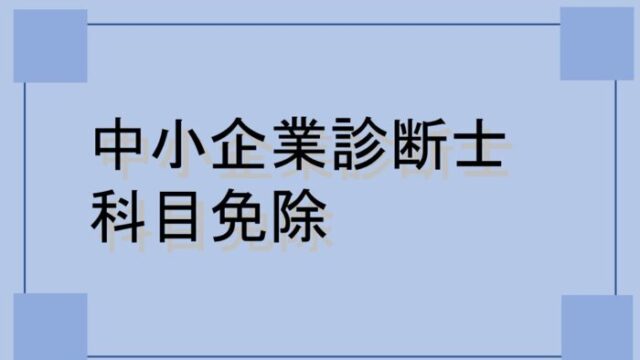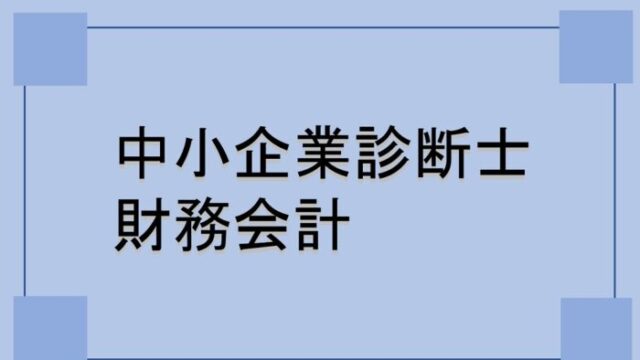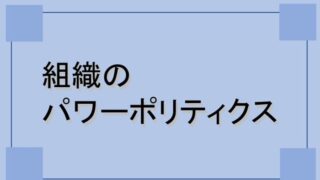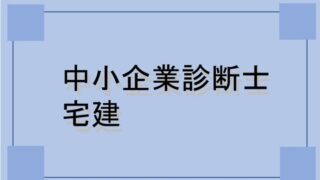こんにちは、トシゾーです。
今回は、中小企業診断士試験の模試(模擬試験)について、お伝えします。
本試験前に模試を受験することは、メリットは多いですが、少なからずデメリットも存在します。
どうせなら、メリットを最大化して、できるだけデメリットを避けたいですよね。
私は、中小企業診断士の合格まで、3年(3回)かかりましたが、毎年、模試を受験しました。
そのなかで、失敗したこともあれば、成功したこともあります。
まずは、そんな私の体験談をご紹介します。
続いて、成果を最大とするための、戦略的な模試(模擬試験)受験法について、お伝えしたいと思います。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
中小企業診断士試験の私の体験談(成功例と失敗談)
ここでは、受験年度別に、私の模試の体験談をお伝えします。
1年目
私は、まったくの初心者(初学者)だったので受験経験が無く、そこで、
「本番で緊張しないように、できるだけ模試を多く受けよう」
と考えました。
会場で3回、自宅で2回ほど受験の申込をしたのです。
結果的に、数が多すぎて大失敗でした。
受験1年目ということで、本試験前の直前期では、本来、集中して勉強に取り組むことにより、大きく実力が伸びるものです。
そんな大切な時期にも関わらず、会場受験(1次×3回)で6日間、復習時間もカウントすると、さらにプラス1週間弱も費やしてしまいました。
まったく時間が足りないことに私自身も焦ってしまい、直前期の学習も模試の答案の内容の復習も、どちらも中途半端になってしまいました。
なお、自宅用に注文した模試は、ほとんど手をつけられませんでした。
このような調子で、費用(料金)だけがかさみ、本試験でも散々の結果となり、一次試験で終了(敗退)となりました。
※1年目は密かにストレートでの合格を目指していたのですが、それどころではない悲惨な結果になってしまいました・・・
2年目
前年の失敗を教訓として、1次試験の模試は「会場受験1回+自宅受験1回」としました。
個人的には、これが一番よいバランスだったと思います。
この年は、1次試験にも見事合格。2次試験の模試は会場受験を2社受験しました。
しかし、2次試験の模試は2社とも合否判定が厳しい結果となり、かなりショックだったのを覚えています。
「模試の成績は関係ない」とは言われますが、その後、受験した二次試験の結果は不合格でした。
3年目
この年は一次試験は受験せず、ニ次試験一本に絞りました。
受験したのは会場模試2回。前年度と同じ回数です。
この時も、模試の結果はあまりよくありませんでした。
前年度よりも少しマシになったレベルです。
正直、「この一年間、何を勉強していたんだろう」と思わないこともありませんでしたが、
それ以上に
模試と本試験は違う。模試は答案の内容をしっかり復習して、本試験に合格するためにある
と考えていました。
もう受験3年目でしたから、多少なりともメンタルが鍛えられていたのかも知れません(笑)
結果的に、本試験は合格しました。
中小企業診断士試験の模試を活用するメリット&デメリット
上記の私の模試の体験談も踏まえて、模試のメリットとデメリットを整理しました。
まず、メリットは以下のとおりです。
・本番の試験と類似の環境で試験を受けるので、本試験に対する絶好の予行演習になる
・他の多くの受験生と一つの試験会場に集合して受験するため、本番に向けて馴れることができ、本番当日のプレッシャーや緊張が低減される
・実際に、解答する順番や時間配分を試してみることができる
・「知識が出てこない」「暗記していたはずなのに覚えていない」など、模試ならではの課題が見えてくる
・自分が得点できなかった部分の苦手科目を分析し、得点アップに繋げることができる
・模試を予想問題と位置付けて、解けなかった部分を集中して補強することが可能
・予備校で実施されている模試の中には、自分の弱点の傾向を診断してくれるサービスがある場合も多い
中小企業診断士の本試験は1次試験で丸2日、2次試験は丸1日。出題範囲や科目数の多い、かなりハードな資格試験です。
これだけの試験を、ぶっつけ本番で挑戦するより、模試でポイントを抑えておいた方が有利なのは間違いないでしょう。
本番と同じ条件で慣れておくことにより、適切な解答を作成できる可能性が高いため、その分、合格に近づきやすいと言えるのです。
それに加えて自分の学習の進み具合を確認したり苦手分野を補強したりといった対策もできますので、中小企業診断士の模試のメリットが大きいのは分かるのではないでしょうか。
しかし、中小企業診断士の模試を受けるに当たり、金銭的な負担が加わるというデメリットがあります。
予備校によって違いがありますが、中小企業診断士の模試の受験料は1回当たり3,000円~6,000円程度です。
また、受験料以外にも、模試を受けすぎると、直前期の大切な勉強時間を削られる、というデメリットもあります。
特に、一次試験は模試も丸二日間かかりますので、復習時間も含めると、多大な時間を費やすことになります。
まさに、初年度の私の失敗原因がコレですね。
必要な勉強時間を削ることになると本末転倒なので、あなたにとって最適な受験回数を検討することが、重要な戦略となるでしょう。
中小企業診断士の模試は会場受験と自宅模試のどっち?
中小企業診断士の模試は、次の2種類に大きくわけることができます。
- 予備校(資格の学校)で実施されている会場受験
- 自宅で問題を解く自宅模試
どちらの方法でも、本番に備えた対策ができる点では一緒ですが、原則として、おすすめは会場模試となります。
会場へ行けるならば、会場模試を選ぶ
予備校で実施されている中小企業診断士の模試は、会場受験だけではなく自宅模試も選択できます。
自宅模試の場合、自宅で受験できますので、「現地が遠くて行くのが大変」と悩んでいる方に向いています。
とはいえ、なぜ会場模試がおすすめかといえば、公開で行われる会場模試には以下のメリットがあるからです。
- 他の受験生もいるので適度な緊張感がある
- 予備校の教室などで、本番の試験の雰囲気を味わうことができる
- 時間配分や解く順番は会場模試でないとわからない
- その後の学習のモチベーションがアップしやすい
本試験までの対策が中小企業診断士の模試を受験する一番の目的ですので、実際に予備校に足を運んで公開模試受験してみてください。
自宅模試を受験するなら図書館で利用しよう!
とはいえ、「予備校まで遠くて時間がかかる」場合など、自宅試験を選ばらざるを得ない場合もあるでしょう。
その場合、自宅模試のデメリットを理解しておくことが必要で、
会場模試のように、実際の本試験を受験しているような雰囲気を味わえない
というのが最大のデメリットとなります。
前述のとおり、会場での公開模試は、本番試験をシュミレーションできる、ということが最大の特長です。
そのため、
本試験と同じような環境で受験する形になるため、本番の直前に予行演習ができる
問題の時間配分や解く順番など、日々の勉強では難しい部分を掴むことができる
以上のような大きなメリットがあるのです。
しかし、模試会場が近くにない場合などは、どうすることもできません。
その場合は、自宅模試を以下のような場所で時間を計りながら解答することがおすすめです。
- 近隣の図書館
- 近隣の有料の自習室
自習室の教室や図書館の静寂な雰囲気の中で模試に取り組めば、多少なりとも、実際の本試験のシュミレーションはできるはずです。
きちんと時間を計って本番のつもりで取り組むことにより、今まで気が付かなかった課題を発見できることでしょう。
自宅模試で注意する点は、提出(送付)の締め切りを守ること。最悪、受付をしてもらえないこともあり得ます。
申込みの後も受講案内を確認するなどして、余裕のある日程で試験実施の予定をいれるよう、明確にしておきましょう。
模試の受験回数、おすすめは?
「中小企業診断士試験対策で、模試は何回ぐらい受けるのが良い?」と考えこんでいる方はいませんか?
私の回答は、
初学者は、最低1回は受ける(出来る限り会場で受験する)
2年目以降の方(本試験受験経験のある方)でスキマ時間を活用したい方は、自宅模試でもOK
模試は答案の内容を復習しないと意味がないので、「模試受験+復習」に費やす時間が、直前期の勉強時間を圧迫しない範囲で受験する
直前期の勉強時間が確保できるなら、回数は多い方がよい
ということになります。
複数回に渡って模試を受けるのであれば、異なるスクールの模試を1度ずつ受験するのがよいでしょう。
予備校によって、予想もかなり異なりますので、それだけ、あなたの弱点を見つけやすくなるでしょう。
模試の受験回数を増やすと、それに比例して費用が掛かってしまいます。しかし、上手く模試を活用して一年でも早く本番に合格できれば、金銭的な負担が大きく解消することは言うまでもありません。
通常の勉強を妨げない範囲で、積極的に模試を活用しましょう。
中小企業診断士の模試受験において押さえておきたいポイント
以下では、模試の受験時に押さえておきたいポイントをいくつか説明しています。
ただ模試を受験するだけで本試験の合格率がアップするわけではありませんので、有効活用法についてきちんとチェックしておきましょう。
結果に一喜一憂しない
模試の結果が良くても悪くても、必要以上に喜んだり落ち込んだりすることはありません。
理解しておきたいのは、模試の結果とは、その時点における、あなたの実力のごく一部であり、模試の結果は本試験の結果と関係ない、
ということです。
そもそも、本試験で模試と同じ問題が出るとしても、ごく一部。
実際、模試の結果が散々だったのに本試験に合格した人も多いですし、結果が素晴らしかったのに不合格となった方も知っています。
模試とは、受験した後にきちんと復習をして自分の実力をアップさせるツール
ということを念頭に置き、変に気持ちを乱されないようにしましょう。
模試が終わった後に必ず復習する
繰り返しになりますが、戻ってきた答案は必ず復習をしましょう。
模試は高得点を取るのが目的ではなく、自分の弱点や苦手分野を知るために受験します。
苦手分野をそのまま放置していると本番の試験で合格することはできませんので、模試の結果を見た後に「○○○の勉強にもっと力を入れた方が良いのか~」と復習すべきです。
具体的にどのような方法で復習をすれば良いのか、概要は以下のとおりです。
- 自分が解いた問題冊子を見返して、判断に迷った設問や理解できなかった設問をピックアップする
- 解説冊子と問題冊子を照らし合わせて、どうすれば解けたのか把握する
- 後から思い出すことができるように、間違った問題と解説をノートに残しておく
仮に模試の結果が良くなくても、本番で似たような失敗をしないよう、しっかり復習をするように学習計画を立てていれば、本番の試験で合格できます。
最近では動画の配信でわかりやすい解説をしてくれる模試も増え、以前よりもグッと復習がしやすくなりました。ぜひ手を抜かずに復習をしっかりやりましょう。
今年(2022年)の模試の日程 一覧 ~大手予備校編
※2023年の模試スケジュールが確定次第、更新します。
ここでは、代表的な資格スクール(大手予備校)の模試の日程を記載します。大手スクールのコースは実績が豊富なものが多く、安心感があります。各スクールの公式サイトのアドレスも掲載しますので、詳細はそれぞれの公式サイトでご覧ください。
【TAC】の日程 2022年度
- TAC 2次実力チェック模試:4/30(土) or 5/1(日)
【LEC】の日程 2022年度
- LEC 1次ステップアップ全国模試:2022/4/30~5/1
- LEC 1次ファイナル全国模試:2022/6/25~6/26
- LEC 2次ステップアップ全国模試:2022/5/8
- LEC 2次ファイナル全国模試:2022/9/4
【大原】の日程 2022年度
- 大原 1次公開模擬試験:2022年6月実施予定
今年(2022年)の模試の日程 一覧 ~2次試験専門校編
2次専門校のコースは大手に比べると知名度では劣りますが、さすが専門校だけあって事例も充実している印象です。
【TBC】の日程 2022年度
毎年8月頃実施されます。
【MMC】の日程 2022年度
年4回実施されます(4月、6月、8月、9月)。
よくある質問
Q 「中小企業診断士の模試は、いらない」と合格者に言われたのですが?
「模試は、いらない」と言われた合格者の方は、「どのような意図で、そのような発言をしたのか」を確認してみましょう。
この記事でも説明してきたとおり、模試には大きなメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。
- 模試を受験しても復習しなければ意味がない(身につかない)
- 模試に時間を費やし、本来最も重要な日々の勉強がないがしろになるようでは本末転倒
以上のような状態を懸念したうえでの発言であれば、仰るとおりだと思います。
重要なのは、あなたが「一番重要な日々の勉強の時間を十分確保」したうえで、計画的に模試をツールとして使いこなすことです。
経営コンサルタントの国家資格を目指す訳ですから、ぜひ戦略的に模試の受験を進めて頂きたいと思います。
最後に(まとめ)
模試を上手く活用すれば、合格へ向けて大きく実力を伸ばすことにつながります。
模試の受験には、多くのメリットがあることを、お判り頂けたのではないでしょうか。
模試を受けた後の復習を重視していれば合格率を高めることができますので、是非一度試してみてください。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |