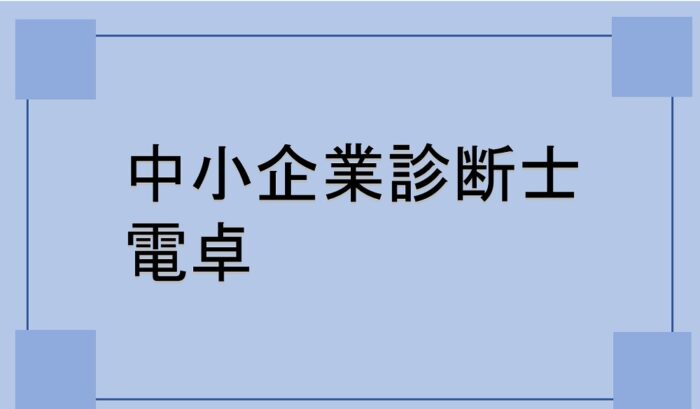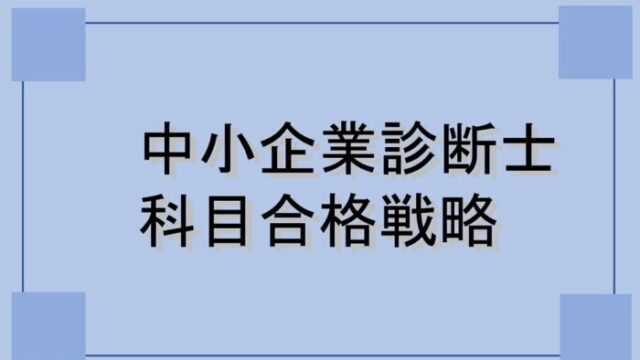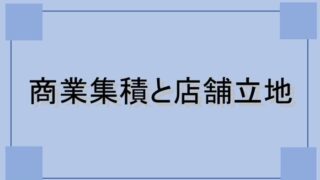今回は、中小企業診断士試験で使う電卓についてです。
中小企業診断士の1次試験では電卓は使えませんが、2次試験では、会場に電卓(計算機)を持ち込むことができます。
あなたは、もしかして「たかが電卓」と思っていませんか?
2次試験の事例Ⅳ(財務・会計)においては、よほどの財務・会計のプロでない限り、時間との勝負になります。
そんな時、適切な電卓を使用し、適切な機能を使い、適切な打ち方ができれば、驚くほど時間を効率的に使えます。一例を挙げれば「電卓を、利き手(鉛筆を持つ手)と反対の手で使う」ことができれば、鉛筆を置く手間が全て省けますよね。
1つ1つは僅かなことですが、「塵も積もれば山となる」のことわざどおり、あらかじめ準備をしておくことで非常に有利に試験に挑むことができます。
ぜひ、この記事を読んで、2次試験の財務・会計で電卓を徹底的に使いこなし、1点でも多く得点を稼いで欲しいと思います。
目次
中小企業診断士の試験で使える電卓の種類!
2次試験に持ち込むことができる電卓の種類については、試験案内に記載されています。
電卓
1)使用できる電卓はいわゆる携帯用電卓で、右の図に例示する機能のような四
則計算(加減乗除)、√、%、数値メモリなどの単純な計算機能を持つもの
です(サイズはおおよそ縦180ミリ、横100ミリ、高さ30ミリ以内程度)。机
上に1台だけ置くことができます。2)次のような電卓の使用は禁止します。
a.関数電卓
b.プログラムの入力機能や記憶機能を持つもの。
c.電子手帳・携帯電話などに付属する電卓。
d.記録紙の出るもの。
e.他の受験者の妨げになるような音の出るもの。
f.電源コードを使用するもの。引用:令和3年2次試験試験案内
イメージとしては、100円ショップで販売されているようなシンプルな電卓であれば、中小企業診断士2次試験で使えます(ただし、100円ショップで販売されてる電卓を実際に使うことは推奨できません。おすすめのメーカー等は後述します)。
税込みや税抜きの計算ができるボタンが付属されていたとしても特に問題はありません。
一方で「sin」や「cos」など、ボタンが大量に搭載されている関数電卓は中小企業診断士の試験ではNGです。
「せっかく用意したのに試験で使えなかった…」といったトラブルを避けるためにも、どの種類であればOKなのか確認しておきましょう。
中小企業診断士2次試験で使う電卓の選び方!
市販されている普通の電卓であれば、中小企業診断士の試験で使えます。
しかし、あまりにも種類が多すぎて迷ってしまう方はいますので、ここでは中小企業診断士の試験で使う電卓の選び方で押さえておきたいポイントをまとめてみました。
数字の表示桁数が12桁ある
数字の表示桁数が8桁しかない電卓は、中小企業診断士の試験で苦労する可能性があります。
金額の大きな問題を計算する際に、桁数が足りなくなるのが理由です。
そのため、中小企業診断士の試験で使う電卓は最低でも10桁、できるなら12桁まで表示される製品を選びましょう。
また、以下のような演算機能は搭載されていてもOKです。
- √・%・定数計算
- 消費税に係る税込・税抜
- 売上に係る原価(MD)
- 日数・時間計算
- マルチ換算についてのキー
- メモリー(M)機能(計算結果を1つだけ記録できる)
- GTキー
これらの機能はほとんどの電卓に付いていますので、使いこなせれば中小企業診断士の試験で有利になるかも知れませんね。
大手のメーカーの製品
電卓の耐久性や機能性を加味し、大手のメーカーから製造されている製品を中小企業診断士の試験で使うべきです。
無名なメーカーから販売されている電卓は、「非常に壊れやすい」「ボタンが打ちづらい」といったデメリットがありますので注意しないといけません。
中小企業診断士の試験の最中に使えなくなる恐れがありますので、次の3つのメーカーから選びましょう。
- CASIO(カシオ):国内でのシェア率第一位で電卓の基本的な機能が搭載されている
- SHARP(シャープ):CASIO(カシオ)と比較して低価格で電卓を購入できる
- CANON(キャノン):電卓の機能は上記の2つのメーカーと比べても遜色ない
電卓のコーナーに行けば、大手メーカーの製品が数多く販売されています。
手の平よりも少し大きいサイズ
中小企業診断士の試験で使う電卓の選び方で、全体的な大きさも忘れてはいけません。
あまりにも大きいサイズの電卓だと机の上で邪魔になりやすいですし、逆に小さいサイズだと打ち間違いの確率が高くなります。
そこで、手の平よりも少し大きいサイズを目安にして、中小企業診断士の試験で使う電卓を購入しましょう。
繰り返しになりますが、中小企業診断士の試験では時間が勝負になりますので、打ちやすい電卓なのかどうかは大事なポイントです。
お手頃な価格で販売されている
中小企業診断士試験で使う電卓は、高ければ高いほど良いわけではありません。
高価な電卓を購入しても、中小企業診断士の試験で使えない機能が搭載されていては全く意味がないですよね。
明確な基準はありませんが、家電量販店で1,000円~2,000円の価格で販売されている電卓であれば、中小企業診断士の試験で困ることはないでしょう。
ネット通販では電卓のサイズがわかりにくいため、できる限り実店舗に足を運んで実際に手に取って大きさを確認するのがベストです。
自分の利き手ではない方で打てる
中小企業診断士の試験会場に持ち込む電卓は、自分の利き手ではない方で打てる製品を選びましょう。
右利きの人は左手でキーを打つ、左利きの人は右手でキーを打つというスタイルで中小企業診断士の試験を解くと、利き手で文字を書けるので時間のロスがありません。
時間がなくなって基本問題を取りこぼしたりミスが多くなったりするのは避けたいので、右手か左手かどうかも電卓を選ぶコツです。
中小企業診断士試験でおすすめの電卓3選!
このページでは、中小企業診断士の試験でおすすめの電卓を3つ紹介しています。
有名なメーカーの計算機であれば安心して使えますので、中小企業診断士の受験を考えている方は選び方の参考にしてみてください。
カシオ スタンダード電卓 MW-12GT-N
カシオ スタンダード電卓 MW-12GT-Nは、大手メーカーのCASIO(カシオ)から販売されている電卓です。
通販サイトのAmazonでは1,344円という価格で購入できますので、コストパフォーマンスは抜群!
キーが大きめで打ちやすいため、中小企業診断士の試験で選んで失敗することはありません。
電卓の価格と使いやすさの両方に拘っている方は、カシオ スタンダード電卓 MW-12GT-Nを選んでみましょう。
シャープ 一般電卓 EL-VN82
シャープ 一般電卓 EL-VN82は、電卓事業50周年を記念して大手メーカーのSHARP(シャープ)が作りました。
コンパクトなサイズですので、中小企業診断士の試験会場に持ち運んでも邪魔になる心配はありません。
小さなサイズの割には、液晶部分が大きくて数字が見やすく、数字の書き間違いの心配はなしです。
定番の早打ち機能(2キーロールオーバー)も搭載されていますので、シャープ 一般電卓 EL-VN82も選択肢の一つに加えてみてください。
キャノン HS-1220TUG
キャノン HS-1220TUGは一回り大きな電卓で、「少し大きめが良い」「自分は手が大きい」という方におすすめです。
ボタンのサイズもそれなりに大きいため、中小企業診断士の試験で打ち間違えのリスクはありません。
千万などの大きな単位を一発入力できる便利な機能も、キャノン HS-1220TUGの魅力的なポイントです。
知っておきたい電卓の機能や打ち方
電卓には、一般の方が意外と知らない機能が搭載されています。
全てを挙げるとキリがないので、中小企業診断士の試験で役立つ電卓の機能や打ち方をまとめてみました。
- メモリーボタン:M+(メモリープラス)やM-(メモリーマイナス)など、電卓に表示されている数字を記憶できる
- 早打ち機能:先に押したキーから手が離れる前に次のキーを押しても、両方のキーがしっかりと入力される
- サイレント機能:キーを入力する際に発生するカタカタというタッチ音を抑えられる(操作性には影響なし)
中小企業診断士の試験で出てくる計算は、基本的に「+、-、×、÷」があれば十分に対応できます。
しかし、数字を記憶できるメモリーボタンやキーを入力しやすい早打ち機能を持つ電卓があれば、更に便利なのは間違いありません。
また、利き手とは反対の手で電卓を使えるようにすれば、文字を書きながら計算ができますので、時間を短縮したい方は中小企業診断士の試験前に練習しておきましょう。
中小企業診断士試験で電卓以外に忘れてはいけない持ち物!
中小企業診断士2次試験の当日には、電卓だけではなく「受験票」「筆記用具」「時計」も必須の持ち物です。
その他、必須でないものの、
- 「定規/マーカー/カラーボールペン」
- 「お弁当・飲料」
- 「参考書/ノート類」
- 「上着」
- 「ハンカチ/ティッシュ」
- 「 目薬」
- 「メガネ拭き(メガネをかけている方)」
なども、あったほうがよいでしょう。
中小企業診断士2次試験に必要な持ち物、当日気を付けることなどについては、下記の記事を参考にしてください。

まとめ
以上のように、中小企業診断士二次試験(事例Ⅳ)で使える電卓(計算機)の種類は限られています。
関数機能やローン機能、プログラムの入力機能が搭載されている電卓の使用はNGです。
ケースによっては電卓を使えないだけではなく受験が無効になることもありますので、このページで中小企業診断士試験におすすめの電卓や選び方をチェックしておいてください。