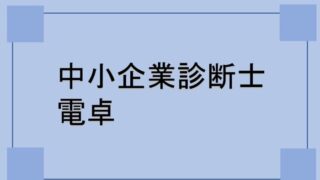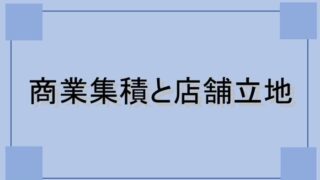この記事は、中小企業診断士試験の「運営管理」科目に関するものです。運営管理についてくわしくは、下記記事をご覧ください。
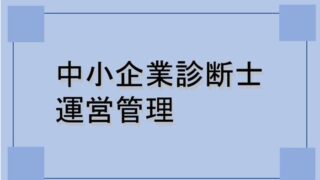
目次
まちづくり三法とは?
いわゆる「まちづくり三法」とは、「大規模小売店舗立地法」と「中心市街地活性化法」、および「都市計画法」の3つの総称です。
以下、それぞれの概要を確認していきましょう。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
平成10年に定められた法律です。それ以前の大規模小売店舗法(大店法)に代わるものとして定められました。
大店法が「大型店舗から中小小売業を保護する」という意味合いが強いのに対し、規制緩和の観点から大店立地法では、そのような狙いはなくなりました。
その目的は、周辺住民の生活環境に考慮すること、となっており、交通渋滞、駐車・駐輪、騒音、防災などに配慮することを定めています。
中心市街地活性化法
平成10年に施行されました。当時、大店法の廃止に伴い、大型店舗が郊外に加速度的に増加することが予想されました。
このことにより中心市街地の機能低下や空洞化という問題を引き起こすことが懸念され、その問題に対処するために、中心市街地の整備改善、活性化を推進するために制定されました。
都市計画法
都市計画法とは、都市計画の内容や決定手続きなどを定めることにより、バランスのとれたまちづくりを推進するための法律です。
まちづくり三法の制定に合わせ、改正により、市町村が自分たちの判断で都市計画地域の用途を決めることが可能なように変更されました。
まちづくり三法の改正
平成18(2006)年、まちづくり三法は大幅に改正されました。
改正の理由ですが、当初のまちづくり三法が狙った効果である「大型店と共存しながらも、中心市街地を活性化させる」ということが上手くいかず、さらに空洞化が進んでしまった、ということが挙げられます。
今後、我が国は少子高齢化時代を迎えるため、モータリゼーションに頼らずに済む中心市街地を中心としたコンパクトシティーの実現が強く求められています。
まちづくり三法の改正は、まさにそこにあると言えます。
中心市街地活性化法の改正概要
- 法律の名称を「中心市街地の活性化に関する法律」と改めた。
- 基本理念の創設
- 国、地方公共団体および事業者の責務規定を創設
- 国による中心市街地活性化本部の創設
- 中津市街地ごとに中心市街地活性化協議会を組織し、多様な民間主体が参画することを明文化
- 市町村が作成する基本計画を内閣総理大臣が認定する制度を創設し、やる気のある市町村を手厚く支援するスキームの開発(国による選択と集中)
- その他、支援措置の充実
都市計画法の改正概要
都市計画法の改正のポイントは、ひと言でいうと、「これまで大規模集客施設としての土地利用は広く許容されていたが、今後は一旦制限を大きくし、適正な手続きのもと、許可を与えて設置可能とする」、つまり地方公共団体のコントロールがしやすくなったことである、と言えます。
建築基準法
建築基準法の目的は以下のとおり(法第1条)。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
内容については、
- 個々の建物の構造や材質などに関する安全性や居住環境の向上のための規定(単体既定)
- 建物の集団化による防災や環境への影響に関する規定(集団規定)
などが定められています。
<店舗・販売管理 関連記事>
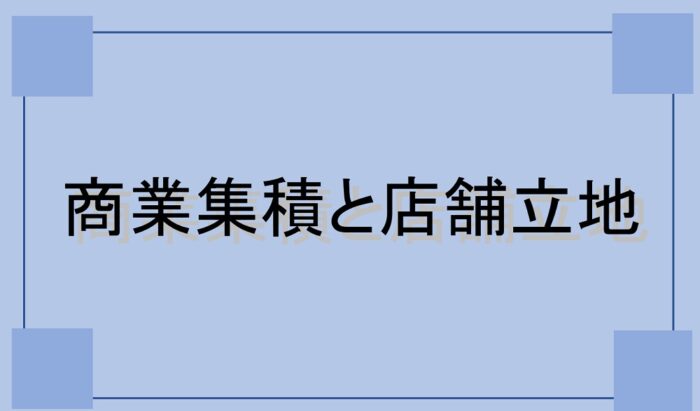
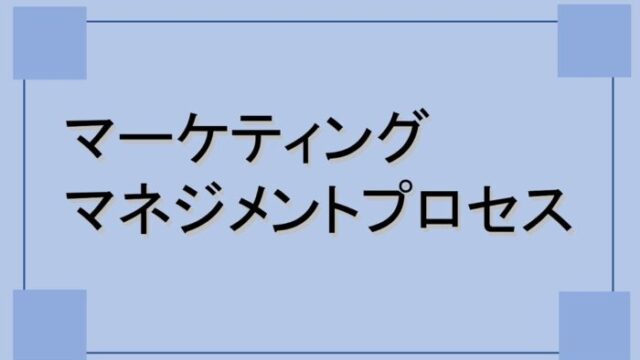
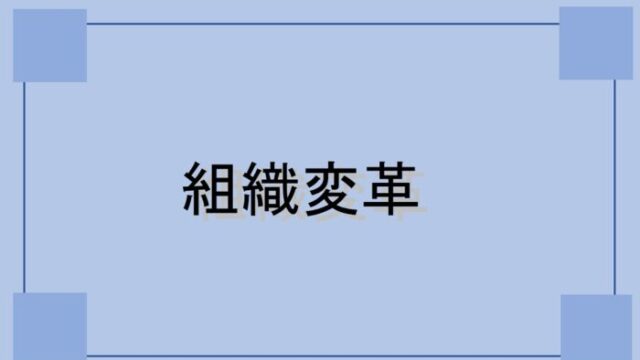
![企業の社会的責任[CSR]](https://shindan-model.com/wp-content/uploads/2021/10/S858-001-002-640x360.jpg)