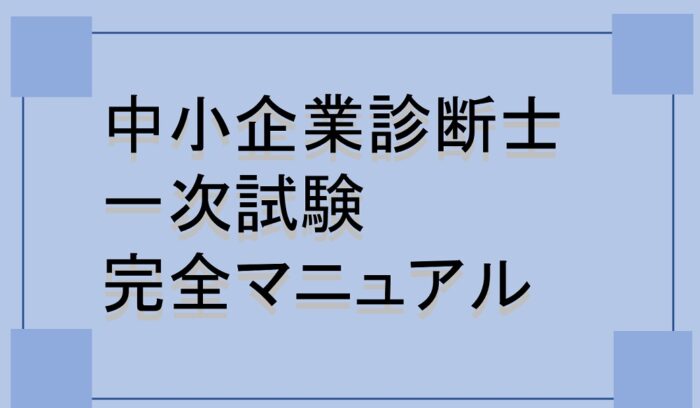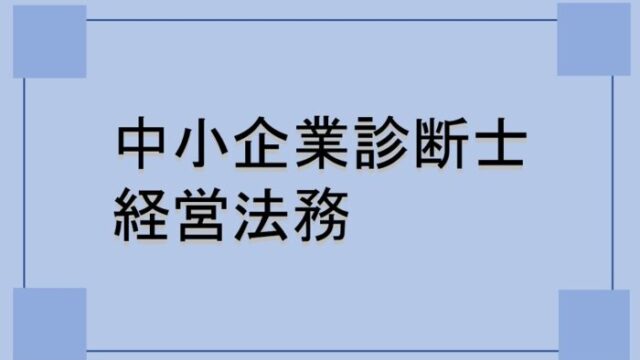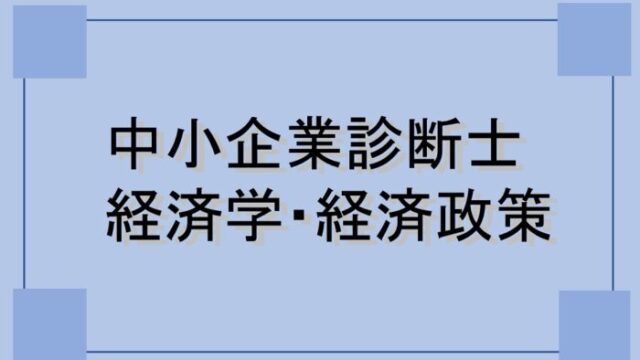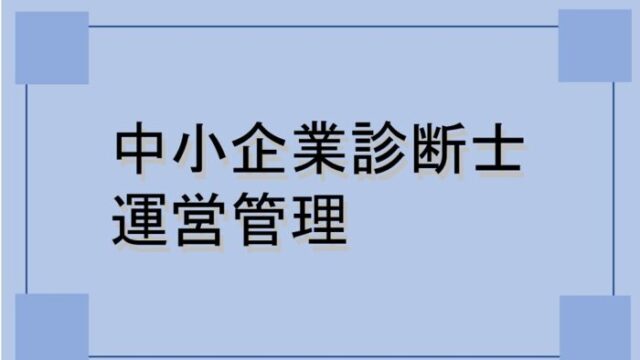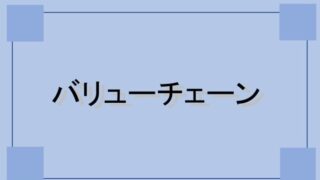現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
書店で購入すると1,500円もする書籍が、なんと無料【0円】です。歴史と実績のあるクレアールの授業を受講をしなくても、そのノウハウが手に入るので、独学をされる方をはじめ、全ての受験生にオススメの書籍です。
デメリットは一切ないので、もらわない理由はありません。
中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
■
こんにちは、トシゾーです。
これまで、中小企業診断士一次試験の勉強法や対策に関し、多くの記事を書いてきました。
それらを「完全版マニュアル」として、一つにまとめたのが、この記事になります。
本サイトにおける一次試験の勉強法や試験対策に関する情報は、この記事からすべてアクセスできますので、
ぜひ、この記事を効率的に活用して頂き、実力を養成して一次試験の合格を勝ち取って欲しいと思います。
目次
中小企業診断士の一次試験の概要
日本版MBAとも言われる中小企業診断士資格。まず、一次試験の概要を確認し抑えておきましょう。
一次試験の特色
中小企業診断士一次試験の目的は、中小企業診断士となるために必要な学識を有していいるか、を確認することです。
合計7科目もある広範な試験分野が最大の特徴で、また、難易度の高さでもあります。
一次試験の受験資格
一次試験の受験資格は、年齢、学歴などを問わず、誰でも受験可能。
一次試験の試験形式
マークシートによる択一方式。
一次試験の受験料(費用)
1万4,500円
一次試験 試験科目
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
上の一覧のとおり、制限時間は60分か90分の違いはあるものの、基本的に7科目全て100点満点となります。
一次試験 実施スケジュール
申込受付、出願:例年5月~6月上旬
試験実施日程:例年8月上旬に実施(土曜日・日曜日の2日間)※第1土日曜日が多い
解答発表:例年、一次試験終了後、数日後に中小企業診断協会のホームページで公開
一次試験合格発表:例年9月上旬
一次試験 実施地区
札幌をはじめ、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、および那覇、以上の全国八地区にて実施されます。
一次試験 合格基準
①合格基準は、総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。
②科目合格基準は、満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。
なお、中小企業診断士の制度・定義などについては、下記記事を参考にしてください。

また、中小企業診断士の資格試験の試験制度(一次、二次)の詳細については、下記記事を参考にしてください。

令和6年度の第一次試験の申し込みについて
令和6年の試験案内の配布・受験申し込みを開始いたしました。期間は令和6年4月25日(木)から5月29日(水)です。申込方法は一般社団法人中小企業診断協会のWebページをご覧ください。
※上記Webサイトに詳しく書いてありますが、申込みに必要な試験案内の入手は、郵送による請求、または窓口での配布となります。
※東京・銀座の中小企業診断協会本部(東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル)では、試験案内の請求受付/配布とも行っておりません。ご注意ください
中小企業診断士 一次試験の難易度
つづいて、中小企業診断士一次試験の難易度について、多角的に見てみます。
中小企業診断士 一次試験の合格ライン
中小企業診断士の一次試験は、2日間で7科目を受験します。
各科目の配点や合格ラインについては、以下のとおりです。
- 配点:各科目100点満点、7科目合計で700満点
- 合格ライン(基準点):420点(平均して60点以上)
ただ、すべての科目に対して、最低獲得点(いわゆる足切り)が設定されており、それが40点となります。40点未満の科目が1つでもあると不合格になります。
つまり、極端な苦手科目を無くし、いずれも科目も一定以上得点が見込めるようにする必要があります。
中小企業診断士 一次試験の受験者数・合格者数・合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| H25 | 14,252 | 3,094 | 21.7% |
| H26 | 13,805 | 3,207 | 23.2% |
| H27 | 13,186 | 3,426 | 26.0% |
| H28 | 13,605 | 2,404 | 17.7% |
| H29 | 14,343 | 3,106 | 21.7% |
| H30 | 13,773 | 3,236 | 23.5% |
| R1 | 14,691 | 4,444 | 30.2% |
| R2 | 11,785 | 5,005 | 42.5% |
| R3 | 16,057 | 5,839 | 36.4% |
| R4 | 17,345 | 5,019 | 28.9% |
注)受験者数とは、すべての科目を受験した方のみの人数のことです。
上の一覧のとおり、17~42%程度とかなり年度によって異なることが分かります。近年では30~40%程度と、合格率は上昇傾向にあるのが分かります(令和4年は少し落ち着きましたが)。
※中小企業診断士試験の合格率の上昇には、政府や経済界からの期待が大きいことと関係あるのではないか、と個人的に考えています。よろしければ、以下の記事の第14回経済諮問会議の箇所などを参考にしてみてください。
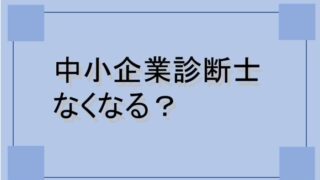
他の資格と比較した場合の難易度
大手資格予備校のTACは、毎年、難関国家資格の難易度ランキングを作成、公表しています。
以下は、TACによる中小企業診断士を含めた難関国家資格の難易度ランキングです。
| 公認会計士 | ★★★★★ |
| 税理士 | ★★★★★ |
| 社会保険労務士 | ★★★★ |
| 中小企業診断士 | ★★★★ |
| 司法書士 | ★★★★★ |
| 行政書士 | ★★★★ |
一企業の作ったランキングですが、あるていど中小企業診断士の立ち位置が客観的に見えるのではないでしょうか。
※ただし、こちらのランキングは、中小企業診断士の場合、二次試験も含めたものとなっていますので、その点をご了承ください。
その他、中小企業診断士試験の難易度の詳細は、下記記事を参考にしてください。
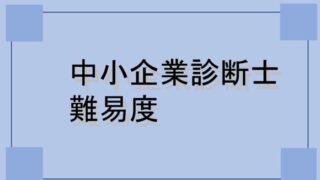
中小企業診断士 一次試験 合格に必要な勉強時間
平均的には、中小企業診断士に合格するための必要な勉強時間は、1,000~1,200時間程度です(一次、二次含めて)。
また、最短では500時間程度でストレート合格(2次、口述試験を含め)された方もいます。
つづいて、中小企業診断士の一次試験7科目、各科目に必要と考えられる勉強時間の目安は以下のとおり。
- 経済学・経済政策:150時間
- 財務・会計:200時間
- 企業経営理論:150時間
- 運営管理:150時間
- 経営法務:100時間
- 経営情報システム:100時間
- 中小企業経営・中小企業政策:100時間
合計:950時間
一次試験全科目で、約1,000時間といったイメージですね。
ただし、社会人の受験生が多い中小企業診断士試験では、人により得意科目・不得意科目が全く異なるため、厳密には、科目毎の必要時間は人によって変わります。
上記の表をベースに、あなたの特性を勘案して調整をしてみてください。
中小企業診断士 一次試験の勉強の順番は
下記は某資格スクールにおける、一次試験各科目の学習の順番です。
- 企業経営理論
- 運営管理
- 財務・会計
- 経済学・経済政策
- 経営法務
- 経営情報システム
- 中小企業経営・中小企業政策
上記のスクールに限らず、多くのスクールにおいても、上記に近い順番でカリキュラムを進めていきます。このような順序になる根拠は以下のとおり。
- 経営コンサルタントの肝である企業経営理論は最初に学習
- 一歩ずつ理解の積み上げが必要な科目ほど、早期に学習開始する
- 暗記科目は後期に学習する
あなたが独学をするとしても、上記の考え方は非常に参考になるでしょう。
その他、中小企業診断士の勉強時間についてくわしくは、以下の記事をチェックしてみてください。

中小企業診断士の試験勉強 いつから始めるべきか?
「中小企業診断士の資格の受験勉強は、いつから開始するのがよいですか?」
という疑問は、多くの方がお持ちのようです。
これには、いろいろな考え方があります。
・9月から10月に、来年のストレート合格を目指して始める
・4月から5月に、科目合格制度を使って翌年の合格を目指す
などが代表的な考え方です。
しかし、私の考える勉強のおすすめの開始時期は「思い立った時に始める!」というものです。
おすすめの開始時期に関しては、それぞれの考え方の根拠などもふくめて、次の記事で詳細に説明していますので、よかったら参考にしてください。
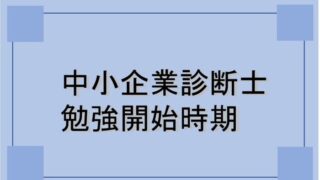
中小企業診断士の一次試験 科目免除について
中小企業診断士の1次試験7科目のうち、一部の科目について受験免除できるのが「科目免除」の制度です。
科目免除制度には2種類あります。
(1)他の国家資格の保持者に与えられる科目免除
(2)過去に「科目合格」した場合の科目免除
以上が、中小企業診断士試験における科目免除制度です。くわしい免除申請の方法などは、次の記事を参考にしてください。
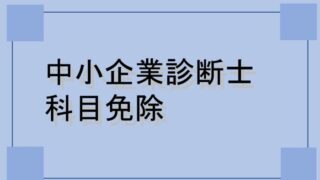
中小企業診断士 一次試験 科目合格の戦略
中小企業診断士一次試験では、7科目合計が420点に届かないと不合格となります。ただし、その場合でも60点以上取れた科目があれば科目合格となります。
科目合格となった場合、その科目については、翌年より2年間、科目免除の申請を行うことが可能です。
しかし、科目合格の利用は、自分にとって必ずしも効率良く進めることができる手段とは限りません。
科目合格制度を利用して、却って不利になるケースも考えられるため注意が必要です。
たとえば、1年目に得意科目だけ60点以上を取り、科目合格をしたとします。翌年、科目合格した科目を免除申請すると、その年の一次試験は、得意科目抜きで全体の6割獲得する必要があるのです。
その他にも、科目合格制度には様々な注意点があります。
そうした注意点や、その注意点を回避するための「最強の科目合格戦略」については、次の記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

勉強法(総合) ~「独学」「通学」「通信」どれがいい?
ここからは、勉強法について見て行きましょう。
中小企業診断士ぐらい難易度が高い試験になると、やはり専門講師の講義を受けた方が効果は上がります。
試験勉強は長期間に渡るため、スケジュールどおりに進めたり、モチベーションを維持したりするためにも、講師の存在は重要です。
おすすめは、次の2つ。
- お金も時間もある方は、生で講義が聴ける「資格スクールへの通学」
- お金や時間をかけたくない方は、スキマ時間でも講義が聴けるスタイルの「スマホ動画対応の通信講座」
「独学」「通学」「通信」など、勉強法の詳しい比較については、以下の記事を読んでみてください。
以上から分かるとおり、オススメは「学校に通う(通学)」または「スマホ対応通信講座」となり、「独学」は推奨していません・・・。
しかし、そうは言っても「独学が一番集中できる」「自分のペースで取り組むことに挑戦したい」などと考える人もいるでしょう。
もし独学を希望される場合は、「あなたに合ったテキストや問題集を選択し購入する」ことが重要になります。
独学向けテキストについては、下記の記事をチェックしてください。

中小企業診断士 一次試験 科目別の勉強法と対策
つづいて、科目別の勉強法です。
一次試験 企業経営理論の勉強法と対策
民間の経営コンサルタントの資格である中小企業診断士にとって、企業経営理論は、まさに中核となる科目です。次の3つの科目に細分化され、出題分野が広範という特徴もあります。
- 企業戦略論
- 経営組織論
- マーケティング論
企業経営理論に関わらず、どの科目でも過去問に当たることは重要です。しかし、そのなかでも特に、企業経営理論は早めに過去問学習をしてほしいと思います。
というのは、企業経営理論の問題文にクセがあるからです。国語の問題では?と思うような出題も珍しくありません。
このような問題文のクセに慣れるためにも、早くから過去問に当たることが重要です。
その他、企業経営理論の勉強法の詳細については、下記の記事を参考にしてください。
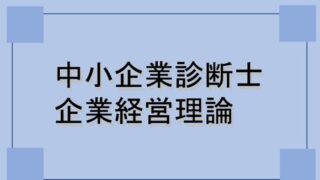
一次試験 財務会計の勉強法と対策
財務会計は、理解を積み上げていくことが必要な科目の代表です。
出来るだけ早い時期から、テキストを読んだり過去問をやったり、一歩ずつ順番に進めていくことが必要な科目です。
また、計算問題も多く出題されるため、実際に筆算や電卓を使いながら問題を解いていく必要があります。
本番で素早く解答するためには、ある程度、計算問題の演習の経験を積み、計算に馴れておく必要があります。
その他、財務・会計の勉強法の詳細については、下記の記事を参考にしてください。
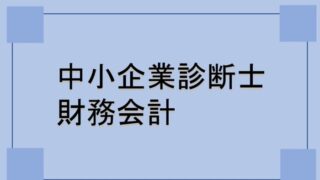
一次試験 運営管理の勉強法と対策
運営管理は、「生産管理」と「店舗・販売管理」の2分野から構成される科目です。
生産管理では、工場を始めとする製造業の業務改善やオペレーションについて学習し、店舗・販売管理では小売業を中心とする店舗業務や販売業務について学びます。
多くの受験生にとって、店舗・販売管理は身近でありイメージ出来やすいと思いますが、製造業経験者以外の方にとっては生産管理は馴染みにくいと思います。
とはいえ、両科目とも、二次試験に関連する科目であり、手を抜くわけにはいきません。
おすすめ参考書の紹介や、運営管理の勉強法の詳細については、下記の記事を参考にしてください。
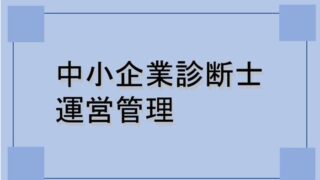
一次試験 経済学・経済政策の勉強法と対策
経済学・経済政策は文系科目であるものの、数式やグラフが出て来ます。そのため、苦手意識を持つ方もいますが、実際に計算が必要な訳ではありません。
それぞれの数式やグラフの見方のポイントを知り、判断できるようになれば十分なので、必要以上に恐れることはないのです。
また、経済学・経済政策は、財務会計と同様に、知識を一歩ずつ積み上げる必要があります。
どうしても理解が難しい方は、書店に行けば初心者向けの「経済学入門」などの書籍が数多く販売されているので、まずは、そうした書籍で経済学の全体像を掴むことがおすすめです。
以下の記事では、経済学・経済政策の勉強法の詳細を説明するとともに、おすすめ書籍についても紹介しています。
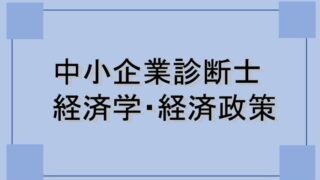
一次試験 経営法務の勉強法と対策
「経営法務」は、法務に関する仕事に関わっている人以外は苦手な人の多い科目です。
法律の試験といえば、「憲法、民法、刑法、・・・」などが頭に思い浮かぶかもしれません。しかし、中小企業診断士試験の経営法務では、企業経営と関係の深い、以下のような分野が出題の中心となります。
- 商法・会社法
- 知的財産権(著作権、特許権、意匠権、商標権など)
- 契約など、民法の一部
経営法務は、法律独特の言い回しで書かれた出題が多くなります。
そのため、初心者のなかには、「テキストを読んでも、全く内容のイメージがつかない・・・」という方も多くいます。
一つの解決策としては、「少しだけテキストを読み、すぐに対応する過去問を解いてみる」というもの。インプットとアウトプットを繰り返すうちに、少しずつ法律用語のイメージができるようになります。
その他、経営法務の勉強法の詳細については、下記の記事を参考にしてください。
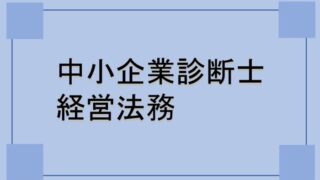
一次試験 経営情報システムの勉強法と対策
エンジニアの方や、企業の情シス(情報システム)部門の方にとっては得意科目である一方、業務でITに関わらない方は不得意と感じることが多い科目です。
この科目が不得意な方は、暗記科目だと割り切ることで、足切り点に引っ掛からない40点以上を取ることだけを考えるのも、戦略の一つでしょう。
最新の用語やトレンドの用語は出題されやすい傾向にあるため、それらに加えて頻出の用語を中心に覚えていきましょう。
その他、経営情報システムの勉強法の詳細については、下記の記事を参考にしてください。
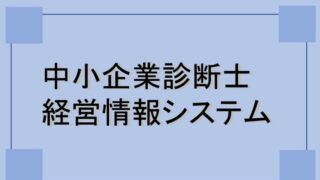
一次試験 中小企業経営・中小企業政策の勉強法と対策
一次試験における最終受験科目であり、もっとも暗記が重要な科目といえます。
暗記すべきものは、「中小企業白書」に掲載される統計情報や、「中小企業施策利用ガイドブック」に掲載されている施策の数々。
すべてを暗記するのは無理なので、テキスト等を参考に、頻出論点を中心に押さえていきましょう。
具体的な中小企業経営・中小企業政策の勉強法については、以下の記事を参考にしてください。
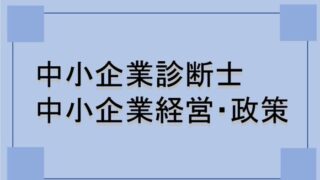
中小企業診断士 一次試験 過去問の活用方法
中小企業診断士一次試験では、8割ぐらいの問題が過去に出題された問題の焼き直しだったり、多少視点を変えて出題された問題だったりします。
残りの2割は難問・奇問の類で、対応する必要はありません。
その解くべき8割の問題を取りこぼさないためにも、過去問を使ったアウトプット学習は重要です。
過去問の活用方法の詳細については、下記記事を参考にしてください。
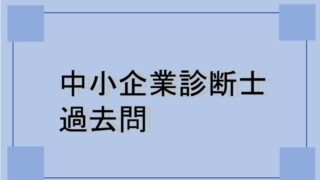
中小企業診断士 一次試験 模試の効果的な活用方法
本試験前に模試を受けることには、以下のようなメリットがあります。
・会場受験をすれば、本番と似た環境で受験できるので、本試験の練習になる
・本試験に近い環境に馴れることで、本番での焦りや緊張が和らぐ
・解答時の時間配分や解いていく順番など、試験形式ならでは確認できることがある
・平素の勉強では見えにくい課題を洗い出せる
・間違えてしまった苦手箇所を分析し、得点アップに繋げられる
中小企業診断士の本試験は一次試験で2日間、二次試験は丸1日であり、試験の範囲や科目はかなりのボリュームがあります。
いきなり本試験に挑むよりも、模試で解き方のコツを把握していれば得点を取れる可能性が高いのです。
ただし、復習だけはキッチリしましょう。復習しなければ、模試の効果は半減します。あと、時間を取られるので受け過ぎは注意です。
模試の活用方法について詳細は、下記の記事も参考にしてください。
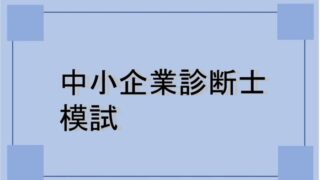
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
あなたが一次試験を受験するにあたり、この勉強法や試験対策の記事がお役に立てれば本望です。
もし、「こんな情報が欲しい」など、ご要望やご意見などありましたら、本サイトのお問合せフォームからご連絡頂ければ嬉しいです。
そして、1次試験を受験されると決心したならば、本記事を参考に、毎日を大切に、しっかり計画とスケジュールを立て、良い戦略と学習を続けて欲しいと思います。
一般的に、中小企業診断士試験は難しく、学習の途中でモチベーションが下がり、それまでの学習自体をつい無駄に感じてしまい挫折することなどが少なくありません。
上のように過ごすことで、必ず結果が出る力を大きく養成できること間違いありません。
また、私のほうでX(Twitter)やYouTubeなどでも継続的に情報発信をしております。質問や相談などありましたら、ぜひそちらのコメント欄にお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。