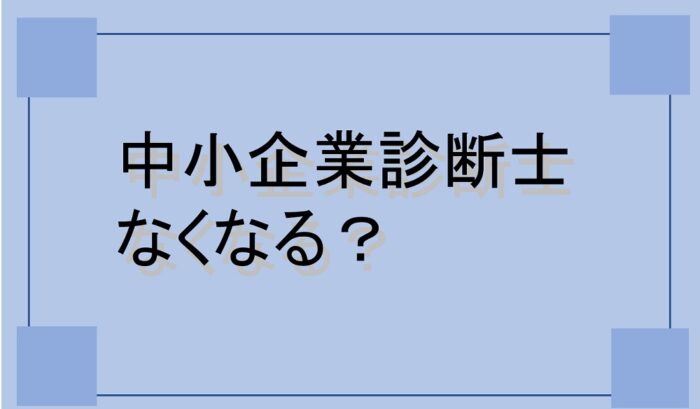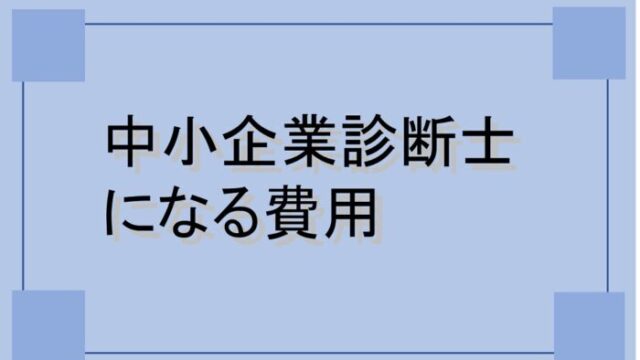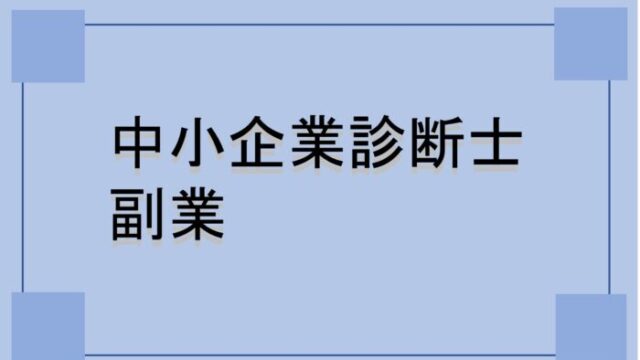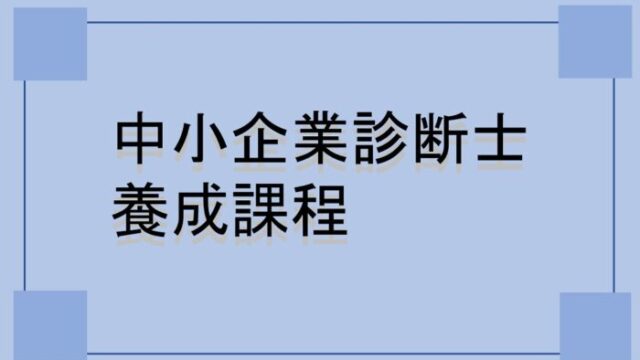=>中小企業診断士の通信講座おすすめランキング&徹底比較記事はこちら
こんにちは、トシゾーです。
最近、なぜか、
「中小企業診断士はなくなるの?(廃止になるの?)」
といった質問を受けることが少なくありません。また、twitterの投稿や、Google検索の関連検索キーワードでも、同様の内容を目にするようになりました。
しかし、結論から言えば「中小企業診断士はなくなる」というのは、全くのガセネタです。
詳しくは当記事の本文で説明しますが、令和2年の菅首相(当時)も出席した経済財政諮問会議で、サントリーの社長が「中小企業診断士の資格者をもっと活用すべき」という趣旨の発言(提言)をされています。
また、「AIに置き換えられにくい資格一位」との研究結果もあり、まだまだ需要や将来のニーズがなくなることはありません。
このとおり、中小企業診断士を取り巻く環境は、実は大変な追い風状態にあるのが実態、といっても過言ではないのです。
というわけで、今回の記事では、以下の3つを解説したいと思います。
- 中小企業診断士がなくなる(廃止)と噂される理由
- 実際には、中小企業診断士がなくなる(廃止になる)ことはないと言い切れる理由
- 「やめとけ」「役に立たない」などのネガティブに関係する意見に対する反論
上記に挙げた内容が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
■
現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
無料【0円】なので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェック。ぜひ検討してみてください。
<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
目次
中小企業診断士がなくなる(廃止)と噂される理由
中小企業診断士は中小企業支援法に記載されている「民間の経営コンサルタントとしての能力を担保する国家資格」であり、俗に「日本版MBA」とも言われています。
最近、「中小企業診断士がなくなる(廃止)」という噂を良く聞くのですが、結論から言えば、全く根拠のないデマです。
しかし何故こんな噂が流れるのか、大きく以下2つの理由が考えられます。
- 独占業務がないから
- 試験に合格して資格を取っても、コンサルタント(コンサル)として使えない(役に立たない)と思われているから
それぞれ解説していきます。
独占業務がないから
難関国家資格の多くは、法律で定められた「独占業務」があります。たとえば、「他人のために法律行為ができる」のは弁護士だけですし、「他人のために税務を行える」のは税理士だけです。
独占業務があれば、世の中の仕事を有資格者だけで独占できるので「仕事を受注しやすい」という考えに繋がります。
一方、中小企業診断士には独占業務がありません。国(経済産業大臣)に登録すれば中小企業診断士を名乗れる「名称独占資格」と言われます。
業務を独占できないということは、すなわち「民間の経営コンサルティング」は、顧客さえ見つければ誰でも行えるということ。
完全に能力主義が中心であり、厳しい競争社会だから「中小企業診断士は無くなる(廃止)」と噂されているようですが、本当でしょうか?
独占業務のある難関資格でも仕事を取るのは大変
実は、独占業務がある国家資格の内でも、食えない有資格者が続出しています。要は、試験勉強だけ出来ても駄目なのです。
- 人脈の構築や無料セミナーの開催など、さまざまな営業活動を効果的に行う
- クライアントの事業会社等に対して、適切なサービスを提供する
- 魅力溢れる人柄でクライアントをサポートし、リピートを作る
独占資格を持つ有資格者ならば実務がきちんと出来るのは当然として、営業・マーケティング能力や人柄・コミュニケーション能力が不足していれば、今は、弁護士や税理士でさえ生き残るのは難しい時代です。
逆に言えば、独占業務のない中小企業診断士でも、経営コンサルティング能力に加えて「営業・マーケティング能力や人柄・コミュニケーション能力」があれば、充分な仕事を確保できます。なぜなら、悩みを抱える経営者は日本にはたくさんいるからです。
また、一般の社会人が中小企業診断士の資格を取って、自分が勤務する会社の事業や業務の改善、実務で活かす、という手も考えられます。
中小企業診断士は経営のプロ(コンサルタント)の資格ですから、どんな事業においても一定の力となりますし、成果を上げることで個人のキャリアを大きく成長させることにも繋がるでしょう。
以上のように、「独占業務がないから中小企業診断士はなくなる(廃止)」というのは適切ではありません。
中小企業診断士は使えない(役に立たない)と思われているから
ここでは、まず中小企業診断士の試験勉強を通じて獲得できる知識やスキルに着目して考えてみましょう。
中小企業診断士の 1次試験では 経営戦略・組織論・マーケティング論・財務会計・生産管理・販売管理・経営に関する法務知識・経営に関する情報システムに関連する知識など、非常に広範なカリキュラムによって経営に関する専門知識を身につけます。
また2次試験では、「様々な事例企業に対する紙上コンサルティング」を通して、コンサルタントとして経営者に適切な助言ができる能力を学ぶことができます。
このような幅広い知識とスキルを習得すれば、どのような企業においても、経営者や社員の支援ができるでしょうし、また様々な職業の初心者に対して、適切なアドバイスも可能でしょう。
もちろん、フリーランスや起業家として、自分のビジネスを効率よくコントロールしていくこともできるはずです。
とはいえ、試験勉強をして資格を取っただけでは、「机上の空論」と言われても仕方ありません。
実際、その分野に経験や実績のある無資格者のほうが、専門外の中小企業診断士より優秀で役に立つ、ということはあり得ることです。
ということは、やはり、中小企業診断士は使えない(役に立たない)のでしょうか?
中小企業診断士は専門分野の確立が必須!
前項の内容を言い換えると、「いくら幅広いと言っても、理論(勉強)だけでは、経験豊富な実践家には勝てない」ということ。
つまり、「理論と実践、両方を備えた方が、本当に使える専門家」と言えるのです。
極論すれば、あらゆる業界で役に立つ中小企業診断士は存在しません。
中小企業診断士に限らず、ある分野で優秀な人は、その分野の経験・実績を持ち、さらに熱心な勉強家。
中小企業診断士の場合でも、豊富な経験がある分野などで、得意とする技術を磨くことで「その分野においては誰からも一目置かれる、優秀で役に立つ人材」となります。
そして一流の人材ほど、現代の変化する社会の中で自分自身を常に教育してアップデートし、長期に活躍できる傾向にあるといえるでしょう。
すなわち、ある経営者の方が中小企業診断士と仕事をした結果、「あの診断士は役に立たなかった」という場合は、残念ながらミスマッチだった、ということです。
適切な専門分野の診断士を選ぶことにより、中小企業診断士が役に立たないということはなくなります。
結論として、中小企業診断士は使えない(役に立たない)から、なくなる(廃止になる)という噂は間違い、ということです。
実際には、中小企業診断士がなくなる(廃止になる)ことはないと言い切れる理由
ここまで、
- 中小企業診断士がなくなる(廃止)と噂される理由
- その噂が間違いの理由
について解説しました。ここからは「中小企業診断士がなくならない、と言い切れる理由」を3つご紹介します。
- 政界・経済界から大きな期待を寄せられているから
- AIにとって代わられにくい仕事だから
- 有益な学習内容で、社会人に人気だから
以上、くわしく解説します。
政界や経済界から、大きな期待を寄せられているから
これは、中小企業診断士がなくなる(廃止になる)ことがない、一番の理由です!
なぜなら、中小企業診断士の生みの親である政府(国)が、「中小企業診断士は必要だ」と認めているからです。
令和2年10月6日に官邸で開催された第14回 経済財政諮問会議(当時の菅首相も出席)の場で、サントリーの新浪社長は次のような発言(提言)をされています。
(前略)そして、経営人材の育成も非常に重要。例えば、中小企業診断士について、非常に意味のある資格だと思うが、提出資料に添付している通り、1次試験では7科目全てに合格しないと試験に通過できないなど、大変難易度が高いものとなっている。中堅・中小企業の経営を担うことのできる人材の裾野を広げていくためにも、例えば、中小企業診断士の科目にデジタル入れるとともに、全ての科目を合格しなくとも、税理士のように一つ一つの科目で合格しても何らかの位置付けを付与することを考えてみてはどうか。(後略)
提言の要旨としては、
「中小企業診断士は価値があり、役立つ資格だ。だから科目合格者の人も、何らかの活躍をしてもらえるような立場を与えてはどうか」
ということです。
なくなる(廃止する)ことはなく、さらなる発展が見込まれる
もし、このことが政策に反映されれば、「中小企業診断士がなくなる」どころか、「診断士資格を目指す受験者が、より活躍しやすいような制度へ変更される」ことが推測されます。
私も診断士の一員として、あらためて、その期待の大きさに襟を正す思いになります。
AIにとって代わられにくい仕事だから
2017年9月、「AI時代のサムライ業(奪われる定型業務)」(日本経済新聞)という記事が掲載されました。
記事には野村総研などの予測が記載されています。今後10〜20年後、各士業がAIに取って変わられる可能性について、以下のデータが推測されています。
<AIによる代替可能性一覧>
弁理士:92.1%
行政書士:93.1%
税理士:92.5%
社会保険労務士:79.7%
中小企業診断士:0.2%
このように、人と向き合って課題を解決する中小企業診断士の仕事(役割)は、AIに代替される可能性は圧倒的に低く、非常に将来性の高い仕事であると感じられます。
当然、手放しで喜べる話ではなく、簡単な経営アドバイスぐらいであれば、AIにもできる時代は来るでしょう。そのためにも、さらに私たちは専門性を高めていく必要はあります。
とは言え、中小企業診断士はAIに置き換えられて、なくなってしまうことはないでしょう。
有益な学習内容で、社会人に人気だから
2016年、日本経済新聞に掲載された「新たに取得したい資格ランキング」において、中小企業診断士が堂々の1位にランクイン。
幅広く経営全般のことが学べるのが魅力で、資格取得後、独立開業するよりもサラリーマン(ビジネスパーソン)として勤務先の企業で能力を活かす方が多いのも特徴。もちろん、就職や転職などのキャリアアップに向けたスキルアップにも役立ちます。
このように有益で人気の高い資格をなくす(廃止にする)、というのは考えられないことです。
まとめ
ここまで、中小企業診断士がなくなる(廃止になる)ことはないと言い切れる理由を3つ解説しました。いずれも、中小企業診断士をなくす訳にはいかない大きな理由だと思います。
これから診断士を目指したい受験生の方は、安心して試験勉強にとりくんで欲しいと思います。
「食えない(儲からない)」「意味がない」という意見に反論してみる
他にも、中小企業診断士に関する噂では「食えない(儲からない)」「意味がない」などがあります。
以下では、実際に中小企業診断士として生活している私が、これらがデマ(嘘)であると反論してみます。
中小企業診断士は食えない(儲からない)?
なぜ、「中小企業診断士は食えない」と言われるのでしょうか? 一つの要因として、中小企業診断士には、弁護士や税理士のような「独占業務」が存在しない、 という点が挙げられます。
確かに、中小企業診断士には独占業務はありませんが、逆に、「独占業務がある資格は必ず食べていけるのか?」というと、それも違います。
実際、難関資格で独占業務のある弁護士や税理士の先生でも、依頼がなく収入(報酬)が少なくて困っている人は一定数います。
中小企業診断士の年収の目安(平均)は?
中小企業診断士の平均年収は500万円~1,000万円程度と言われています。さらに独立診断士に話を限定すれば、2,000万円~3,000万円を超える方も、たくさんいます。
当然ですが、資格を保有しているだけでは全く稼げません。
新人の診断士は、諸先輩に営業活動や仕事のやり方を教わったり、案件(仕事)の紹介を受けたりしながら、少しずつ自分で案件を見つけて行けるようになることが重要です。
つまり営業とマーケティングの能力が必要なのです。きちんと営業活動やマーケティング施策を実行でき、お客様に信頼されるようなコンサルティング実績を積むことで、少しずつクライアントが増え、事業が安定してきます。
世の中には、予想以上にプロの経営コンサルタントを求めている中小企業経営者は多いのです。
食えないなんてことは、決してありません。
中小企業診断士の年収については 次の記事にもありますので興味ある方はチェックして下さい。

中小企業診断士は意味ない(無意味、無駄)?
中小企業診断士の資格には本当に意味があるのでしょうか? 無意味・無駄なんでしょうか?
そもそも、「意味がない」という表現は 少し抽象的ですが、
ここまで見てきたとおり、 中小企業診断士は問題なく食べていけますし、実際に使える資格であり、様々なシーンで必ず役に立ちます。
さらに、資格を取得するための受験科目は次のとおり。
■一次試験科目
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |
| 財務・会計 | 60分 | 100点 |
| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |
| 運営管理 | 90分 | 100点 |
| 経営法務 | 60分 | 100点 |
| 経営情報システム | 60分 | 100点 |
| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |
これらの科目を、1,000~1,200時間もの勉強時間を利用してマスターするわけです。かなりの労力が必要ですが、いずれも経営やビジネスに必須の知識。これらを身に付けることには会社の経営構造を理解できるところから始まり、様々なメリットがあります。無意味なわけがありません。
つまり、意味がないということは決してないのです。
診断士は知名度が低い?
「弁護士や税理士はもちろん、社労士や行政書士より中小企業診断士のほうが知名度が低いのでは?」
そう思う方もいるかも知れません。ただ、そうしたイメージを持つ方のほとんどは、会社員や学生など一般の方。中小企業診断士は社労士や行政書士と違って、一般の方とほとんど接点がないため、そのような方々の印象に薄いのは当然です。
診断士のメインの顧客は、中小企業・小規模企業の経営者。商工会や商工会議所などで多くの診断士が中小事業者を支援しており、そうした方々から大きな信頼を寄せられています。
中小企業診断士はその能力を活かして、事業者の方々を対象に広い範囲で大きな影響を与えています。
そのため、中小事業者のなかには「社労士や行政書士よりも診断士のほうが身近に感じる」という方も多く、一概に「診断士の知名度は低い」と言えるわけではありません。
診断士になると人生変わる?
私自身の話で恐縮ですが、私自身は診断士になるという選択をしたおかげで、人生が変わったと本気で思っています。
現在、診断士の勉強を続けている受験生のみなさんには、正直、不安をお持ちの方も多いでしょう。しかし、是非とも自分を信じて、学びを続けて欲しいと思います。
診断士になり、「自分の強みを機会に活かす戦略」を愚直に実践すれば、必ず道は開けます。
実際、私自身も何とかなりました。参考になるかどうか分かりませんが、下記記事には、私が人生変わったと考えている体験記を掲載しています(そんな大成功した訳ではありません。食べるのには困っていない、というレベルで恐縮ですが)ので、よろしければ参考にしてください。
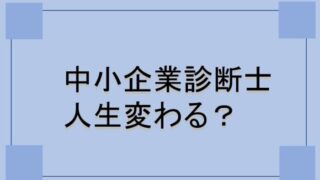
中小企業診断士試験の概要
ここまで読まれて、中小企業診断士の有用性を理解できたかと思います。ここからは、中小企業診断士の資格に興味を持たれた方のために、資格の概要や勉強方法などをお伝えします。
一次試験の特徴
第1次試験は、中小企業診断士となるために必要とされる学識を持っているのか、を判断するための試験です。
経営戦略・経営組織論・マーケティング論・財務会計・情報技術(IT)・ビジネス関連の法令など、合計7科目による試験を実施、広範な経営知識を問われます。
| 受験資格 | 一次試験の受験資格は、年齢や学歴、国籍等に一切制限なく、どなたでも受験可能です。 |
| 試験形式 | マークシートによる四肢または五肢択一方式。 |
| 受験手数料 | 令和4年に改訂が入り、14,500円となりました(令和3年度までは13,000円)。 |
| 実施地区 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇 以上、八地区の会場 |
| 合格基準 | 総得点数の6割以上を取得したうえで、さらに1科目でも4割未満がないことが必要。 また、科目ごとの合格基準は、各科目の満点の6割が必要。 ※いずれの場合も、試験委員会による補正が入る場合があります。 |
| 合格率 | 年によって大きく変動しますが、近年は30~40%程度になっています。 |
一次試験 実施スケジュール(試験日)
- 申込受付(出願):5月~6月上旬
- 試験実施:8月上旬(土曜日・日曜日の2日間)※第1土日曜日が多い ※2021年は東京オリンピック終了後の8月下旬に実施されました
- 解答発表:一次試験終了後、数日以内(診断協会のHP上で公開)
- 一次試験合格発表:9月上旬
一次試験 試験科目の一部免除
一定の条件を充たした場合、科目免除を受けることができます。科目免除には、以下2つのケースがあります。
| 他資格等保有による免除 | 弁護士・会計士・情報処理技術者など、他の国家資格を保持していることで、科目免除を受けられます。 |
| 科目合格による免除 | 前年以前に、60点以上を確保し、「科目合格」となった科目について、次年度以降に科目免除とすることができます。 |
二次試験の特徴
2次試験は、中小企業診断士となるために必要とされる応用能力を保持しているのか、を判断するための試験です。
筆記試験と口述試験の2段階のプロセスがあり、筆記試験は4科目の事例問題を解答します。口述試験に進めるのは、筆記試験に合格した者だけです。
なお、2次筆記試験は、模範解答が公開されません。そのため、「どのように解答すればよいのか」という絶対的な基準がなく、対策の方向性が定まりにくい側面があります。
実際、各資格学校が発表する解答例の内容も、それぞれ異なるものになっています。
このように取り組みにくい二次筆記試験に対して、口述試験は出席しさえすれば、ほぼ合格する試験となっています。
| 受験資格 | その年、または前年の一次試験合格者 |
| 試験形式 | ①筆記試験: 4科目の事例問題。20文字から200文字程度で解答する設問を6~8個ほど出題する記述式。②口述試験: 面接による試験(10分程度) |
| 受験手数料 | 令和4年に改訂が入り、17,800円(令和3年度までは17,200円)となりました。 |
| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区。受験する地区は、申込時に希望する地区を指定可能。 |
| 合格基準 | 総得点数の6割以上であって、さらに1つの科目も4割未満がない者であり、口述試験においては6割以上の評定を獲得した者。 |
| 合格率 | 例年20%程度 |
二次試験 実施スケジュール(試験日)
- 出願期間:8月下旬から9月中旬
- 筆記試験実施:10月下旬の日曜日 ※第3日曜日が多い
- 筆記試験合格発表:12月上旬
- 口述試験実施:12月中旬の日曜日
- 口述試験合格発表:12月下旬
合格に必要な勉強時間
一般的に、中小企業診断士試験の合格に必要とされる勉強時間は、1000時間から1,200時間が目安です。
1年間は約50週ですから、1週間あたり24時間の勉強時間が必要となります。ざっくり、平日3時間+週末5時間、というイメージになります。
※中小企業診断士の勉強時間についてくわしくは、次の記事もチェックしてください。

中小企業診断士試験の難易度(偏差値ランキングによる難易度)
中小企業診断士は難関国家資格試験(士業)のなかでは平均的な位置づけであり、偏差値60程度とされています。
他では、公認会計士・弁理士・税理士・司法書士は偏差値65~64と、最難関の司法試験に次ぐ難しさです。
なお、社労士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格は、「仕事をしながら取得できる資格としては最難関」と言わることがよくあります。実際に、これらの資格を働きながら目指す方は多くいます。
行政書士の偏差値59、社労士は60であり、その点からも、これら3つの資格試験の難易度は変わらない、といえます。なお、難関国家資格の入り口的なポジションとされる宅建試験の偏差値は52となっています。
※上記はWeb上の非公的機関による複数の「資格難易度・偏差値ランキング」等からまとめた数値であり、厳密な根拠があるものではありません。あくまで相対的な難易度を知るための参考値であることを、ご了承ください。
※中小企業診断士の難易度の詳細については、下記記事を参考にしてください。
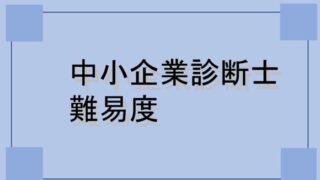
最短の勉強時間で合格するための勉強方法(ポイント)
中小企業診断士に限りませんが、難易度の高い国家資格(試験)を突破するためには、以下のような勉強法が定石になります。
- 満点を目指さない(診断士の場合は70点を目指す)
- テキストのインプットに時間を掛け過ぎない
- 過去問を徹底利用してアウトプット学習を増やす
- 細かい単位ごとにテキスト→過去問のループを繰り返し、何周も回す
過去問を何度も回して基本的な問題を取りこぼしさえしなければ、自ずと合格は見えてきます。
一次試験の勉強方法
一次試験勉強方法の詳細について、さらに知りたい方は、下記の「一次試験 完全合格マニュアル」をチェックしてみてください。
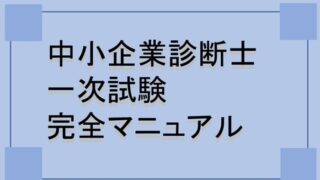
二次試験の勉強方法
二次試験の勉強方法については、下記の記事を参考にしてみてください。

※また、中小企業診断士の独学用テキストについて詳しくは、下記記事を参考にしてください。

まとめ
以上、中小企業診断士の資格に関する噂や疑問、ネガティブなイメージに対して、私なりに答えてみました。
繰り返しになりますが、診断士の資格は、少しずつ注目されて来ている一方、まだまだ世間一般には充分に認知・評価されていないのも事実です。
しかし、だからといって、
「中小企業診断士の資格を取っても仕方ない。もっとメジャーな社労士や行政書士を取った方が良い」
などと考えるのは短絡的です。
なぜならば、ここまで見た通り、「中小企業診断士が役に立つ・意味のある資格」であることは間違いありませんし、さらに、世間でまだまだ知名度が低い部分があるのであれば、それは逆にチャンスでもあるからです。
将来的に、ますます差別化を図れる資格になることは間違いないでしょう。
誰もが注目する超人気資格になる前に、あなたが一年でも早く中小企業診断士の資格を手に入れれば、それはその他大勢の方に対する先行者利益になるというものです。
少しでも興味がある方は、是非チャレンジしてほしいと 思います。
最短合格のための受験ノウハウ本 【無料でもらえる】
中小企業診断士試験に関心を持たれた方向けに、
『最短合格に必要な受験ノウハウ』が分かるノウハウ本をご紹介します。
実は、市販のノウハウ本が、なんと無料【タダ】で手に入ります。
というのは、現在、クレアールの中小企業診断士通信講座では、資料請求した方に市販の中小企業診断士受験ノウハウ本を無料プレゼントしているからです。
 非常識合格法
非常識合格法<クレアールに資料請求で、市販の書籍「中小企業診断士・非常識合格法」が貰える!【無料】>
現在、クレアールの中小企業診断士講座へ資料を請求するだけで、受験ノウハウ本(市販品)が無料で進呈されます。
試験に関する最新情報を始め、難関資格である診断士試験を攻略するための「最速合格」ノウハウが詰まっています。
無料【0円】なので、ぜひ応募してみてください。
診断士試験に本格的にチャレンジしたい方へ
また、この記事を読まれて
「本格的に中小企業診断士試験の勉強をしたい」
と思われた方には、
コスパの高い「スマホ動画対応オンライン通信講座」の利用をおすすめします。
なぜなら、
- スマホで視聴できる動画講義で、時間や場所を選ばず、隙間時間に勉強できる
- テレビやYouTubeの番組を見るイメージで、リラックスしつつ知識を学べる
- 高価格な大手スクールのカリスマ講師と同等以上の、質の高いプロ講師の講義を受講可能
など、非常に進化した学習環境を実現した講座となっているからです。
難しいテキストを読み込むことなく、分かりやすく噛み砕いた動画講義を見るだけで知識がインプットできます。
あまり苦労せず、少しの努力や集中力で、勉強を有利に進めることができますよ。
具体的には、5万円台から受講できる「診断士ゼミナール」と「スタディング」が、質の高さと料金の安さにおいて、他の講座を圧倒しています。
どちらを選んでも間違いはないので、よろしければ以下の「診断士ゼミナール」や「スタディング」の記事を読んでみてください。


それぞれの公式ページを確認したい方は、以下をどうぞ。
■
※診断士の勉強法については、以下の記事も参考にしてみてください。
中小企業診断士の通信講座おすすめは? ~独学にも使える、2024年最新版 比較・ランキング
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |