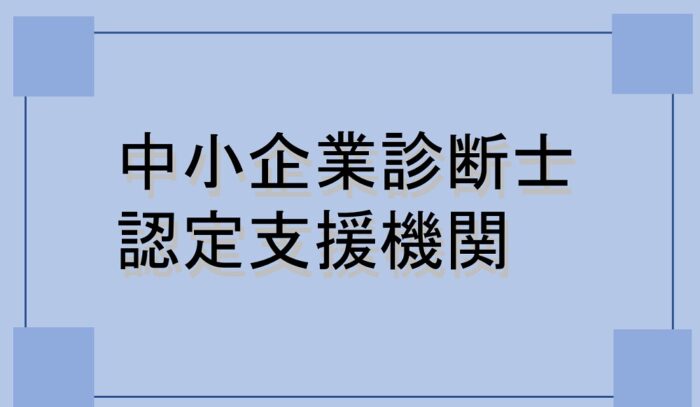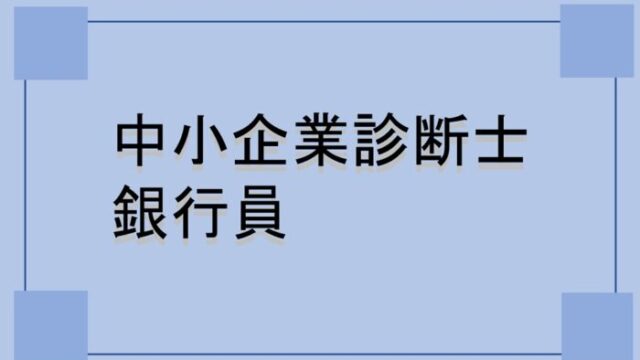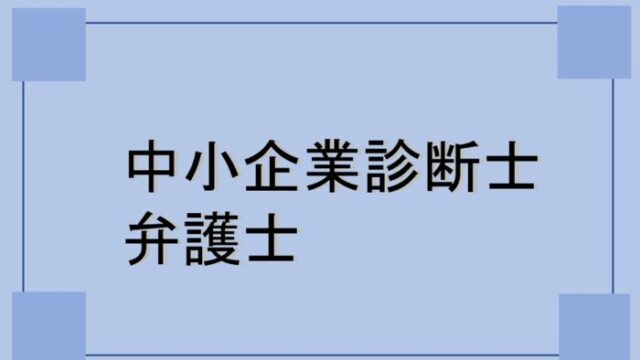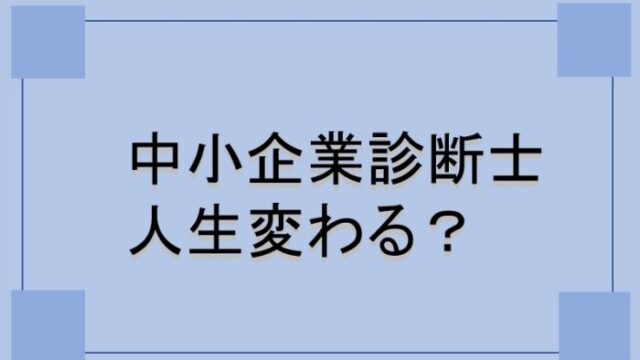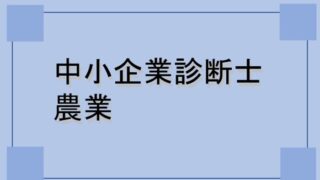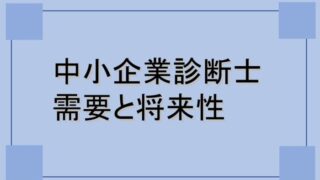認定支援機関(経営革新等支援機関)とは?
中小企業者/小規模事業者等の経営強化を図るため、平成24年の8月30日に、中小企業経営力強化支援法が開始(施行)されました。
日本の経済の発展には、中小企業者/小規模企業者の活性化が必要不可欠ですが、次のようにたくさんの課題があります。
・経営課題を直視して解決できないか?
・外部環境を認識して活用できないか?
・経営効率を改善して成長できないか?
そこで、中小企業経営力強化支援法を施行するとともに、認定支援機関(経営革新等支援機関)を認定する制度が新たに創設されました。
認定支援機関とは国によって認定された中小企業支援者で、一体何を指しているのか見ていきましょう。
- 中小企業者および小規模事業者の多様化かつ複雑化する経営課題に対し、高度な専門性によるサポートを行う目的で創設された
- 税務や金融、企業の財務に関わる専門的なノウハウや知識を持っており、経営革新計画の策定業務に関する一定の経験年数を持つ機関や人を認定する
- これに当てはまるのは、「金融機関」「税理士」「公認会計士」「弁護士」「中小企業診断士」など
堅苦しい文章でわかりにくいと思いますが、簡単に説明すると国が認めたレベルの個人や法人を認定支援機関と位置付け、中小企業者の経営をサポートする制度です。
以前までは専門知識を有する人という基準で、税理士・公認会計士・弁護士が無条件で認定を受けていました。
今現在では、ビジネスパーソンから人気の資格の中小企業診断士を持つ人も、認定支援機関の認定を受けられます。
中小企業診断士が認定支援機関になる方法
2013年末の時点で、認定支援機関の数は全国で19,788と増えています。
中小企業診断士の資格を持つ方で、認定支援機関(経営革新等支援機関)の認定を受けている人は少なくありません。
「自分にはあまり関係ないよね?」とイメージしている方も多いですが、中小企業診断士として認定支援機関(経営革新等支援機関)に申請・登録をしますと、活躍できる業務の幅が広がります。
中小事業者等に対し、専門性の高いサポートを行うための担い手として認定支援機関(経営革新等支援機関)は認定されていますので、これから中小企業診断士を目指す人とも深く関わっているわけですね。
中小企業診断士が認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法は、次のどちらかの条件を満たして認定申請する必要があります。
- 経営革新計画等の策定に際して支援者として関与した後に、計画の認定を3件以上に渡って受けている(更に3年間以上の実務経験が必要)
- 中小機構に指定された研修を受講して、実施されている試験に合格する
中小企業経営力強化法に基づいて経営革新計画や経営力向上計画を3件以上行う中小企業診断士は、支援先からの証明書で認定支援機関(経営革新等支援機関)の認定を受けられます。
もう1つのルートは中小企業経営改善計画の策定支援研修(内容は理論研修および実践研修から構成)で、17日間・120時間の理論研修を中小企業大学校で受講し、2日間の実践研修を行った後に試験に合格しないといけません。
研修を受ければ認定を受けられるわけですが、理論研修が99,000円、実践研修が26,000円とトータルで125,000円の費用が発生します。
そのため、都合良く経営革新計画や経営力向上計画を行う対象企業がない場合は、高額な費用を支払って研修を受けないといけないのです。
どちらの方法で認定支援機関(経営革新等支援機関)になれば良いのか、中小企業診断士の資格を持っている方(或いは、取得予定の方)は一度考えてみましょう。
認定支援機関の中小企業診断士の仕事内容
認定支援機関の中小企業診断士も、他の人と同じように多岐に渡る仕事内容をこなしていきます。
具体的にどのような業務と携わることになるのかいくつか見ていきましょう。
- 創業支援:創業やベンチャー支援など円滑な事業活動のために経営サポートを行う
- 事業計画作成支援:融資や補助金の申請の際に必要な事業計画の作成をサポートする
- 事業承継:会社の経営を後継者に引き継ぐ際のアドバイスを行う
- M&A:2つ以上に会社が合併したり他の会社を買収したりする際のサポートをする
- 情報化戦略:経営戦略策定を受けて個別の情報システムの検討を補助する
- 知財戦略:経営や事業戦略に基づく知財の取得や活用方針を文書化したものをサポートする
- 人材育成:会社の経営戦略の実現に貢献できる人材の作成に関するアドバイスをする
- BCP作成支援:自然災害など不測の事態が起こった際に中核となる事業を継続する方法や手段をアドバイスする
- 物流戦略:企業戦略に沿って設定されるアクションプランの策定をサポートする
中小企業等経営強化法に基づいて国に認定された支援者が認定支援機関(経営革新等支援機関)ですので、その業務は幅広くなっています。
資格試験に合格したからといって企業支援ができるとは限らないため、中小企業診断士になった後も研鑽を積み、経営と財務の両方の知識やスキルを兼ね備えるようにしないといけません。
中小企業診断士が扱う主な補助金の申請
中小企業診断士の業務は経営コンサルタントだけではありません。
中小企業の補助金の申請をサポートするのも、重要な仕事内容の一つです。
そもそも、補助金とは一体何なのか簡単に説明していきます。
・国や地方自治体から交付される返済義務のないお金
・目標を達成する事業者のために給付されている
・補助を受けられるのは事業全体、または一部の費用
中小企業の行いたい事業と行政上の目的が合って効果が期待できれば、補助金を受けられる可能性が高いのです。
そこで、中小企業診断士が取り扱っている主な補助金の申請について確認しましょう。
- ものづくり補助金:正式名称はものづくり・商業・サービス新展開支援補助金で、新しいものづくりやサービス開発に取り組む中小企業や小規模事業者を支援する制度
- IT導入補助金:中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズとマッチしたITツールを導入する費用をサポートする補助金制度
- 小規模事業者持続化補助金:日本商工会議所と全国商工会連合会が実施する補助金で、経営計画に基づき実行する販路の開拓などのプロジェクトに対して支給される補助金
- 軽減税率対策補助金:消費税軽減税率制度への対応が必要な中小企業や小規模事業者に対して、対応レジや受発注システムの導入費用を補助する制度
ゆとりある資金のない中小企業にとって、補助金や助成金の制度は欠かせません。
補助金の種類によって給付される金額や条件には違いがありますが、要件を満たしていればどの中小企業でも申請できます。
ただ残念なことに、補助金の存在を知らない中小事業者も多くいます。
そのような中小事業者に、最適な補助金をお伝えする役割も、中小企業診断士に求められているのではないでしょうか。
まとめ
認定支援機関の中小企業診断士になる方法や仕事内容についておわかり頂けたでしょうか。
経営革新計画・経営力向上計画を3件以上行ったり、中小企業経営改善計画の策定支援研修を受けて試験に合格したりすれば、認定支援機関(経営革新等支援機関)の申請ができます。
中小企業診断士の試験に合格するのが一番の目的ではありませんので、合格後に活躍する場所の一つとして、ぜひ認識しておいてください。