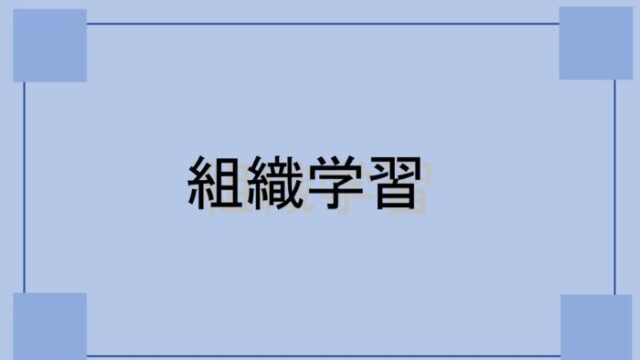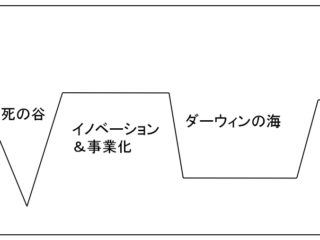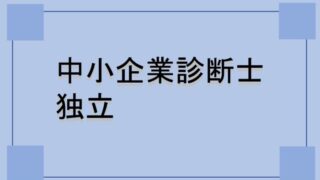こんにちは、トシゾーです。今回は、「男女雇用機会均等法」について学びます。この法律は1985年に成立し、1986年から施行されました。
この法律では、職場における男女の平等を確保し、女性が差別を受けることなく、仕事と家庭の両立ができるように制定されました。
その後、1997年に全面改正、2007年に再改正され、「女性だけではなく、男性へのセクハラについても考慮する」など、法律としては高いレベルになった、と言えるでしょう。
それでは、男女雇用機会均等法について、詳しくみていきましょう。
目次
男女雇用機会均等法の概要
男女雇用機会均等法の目的
この法律では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図ることを目的としています。あわせて、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することもを目的としています。
男女雇用機会均等法において「差別禁止項目」とされているもの
この法律では、以下の4点について差別することを禁止しています。
- 募集及び採用
- 配置・昇進及び教育訓練
- 福利厚生
- 定年・退職及び解雇
※男女雇用機会均等法では、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いを禁止する旨(男女同一賃金の原則)の記載はありません。
賃金についての男女の差別的取扱い禁止については、労働基準法で明記されています。

ポジティブアクション
この法律においては、通常の差別だけでなく、女性に対する逆差別(優遇措置)も禁止しています。しかし、男女の均等な機会および待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として行われる措置を講ずることについては、違法にはならないとしています。
例としては、女性の管理職比率が低い場合に、それを改善するため、女性のみを対象とした管理職登用研修を行う、などが挙げられます。
セクシャルハラスメント
事業主は、女性労働者の就業環境が害されることがないよう、雇用管理上の措置を講じることが必要です。
さらに男女平等の観点から、女性だけではなく、「男性への性的嫌がらせ」などにも必要な措置を講じることが必要です。
また、女性労働者と事業主の間の紛争(募集・採用を除く)について、関係当事者の双方または一方から調停の申請があった場合、都道府県労働局長は、必要性がある認められる場合において、紛争調整委員会に調停を行わせることが可能です。
さらに、勧告に従わない企業があった場合には、厚生労働大臣は、その企業名を世間に対して公表することができる権限を持ちます。
男女雇用機会均等法 まとめ
いかがでしたでしょうか。我が国の高度成長時代の最後・バブル前期に成立・施行された本法律ですが、すでに30年以上の月日が経ちました。
本法律のおかげもあり、我が国では急速に「男女平等意識」や「性差別に対する問題意識」が広まりつつあります。
中小企業診断士試験対策だけではなく、日常の業務の取り組みにおいても、ぜひ、本法律の内容を意識してみてください。

![企業の社会的責任[CSR]](https://shindan-model.com/wp-content/uploads/2021/10/S858-001-002-640x360.jpg)