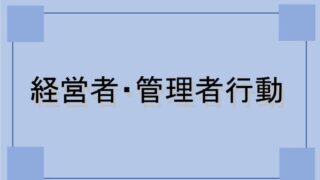目次
組織学習とは
組織学習とは、組織が持つルーティン(行動プログラム)が変化するプロセスとして定義されるものです。
組織ルーティン
それでは、組織ルーティンとは何でしょうか?
組織ルーティンとは、公式の文書として制度化されている諸規則、手続き、組織構造、さらに、組織文化、個人レベルにまで還元される知識などをすべて含有した概念です。
そのような総合体である組織ルーティンを変化させるプロセスそのものを組織学習といいます。
組織は、組織ルーティンを利用して様々な問題を解決します。その問題解決能力は組織の適応能力と言えるものであり、つまり、組織学習とは組織の適応能力の進化させることといえるでしょう。
センゲの「ラーニング・オーガニゼーション」
センゲは、ラーニング・オーガニゼーション(学習する組織)という考え方を提唱しました。
ラーニング・オーガニゼーションでは、継続的に自らの力で変革を行っていくことになります。
センゲによれば、ラーニング・オーガニゼーションには、
①ビジョンの共有、②チーム学習、③自己学習、④メンタル・モデルの克服(思い込みの排除)、⑤システム思考(全体構造や作用の把握)
以上の5つの要因(フィフス・ディシプリン)が必要と考えました。
組織学習のメカニズム
組織学習には2つの学習メカニズムがあります。それが、「積極的問題解決学習」と「不安除去学習」です。
積極的問題解決学習
組織に関する重要な問題を解決できた場合、その解決策は再利用され、組織に保存されますが、このような、プラスの効用をもたらす学習をのことを「積極的問題解決学習」といいます。
不安除去学習
「不安除去学習」とは、マイナスの効用を除去するための学習です。具体的には、組織にとっての恐怖、苦痛、不安を除去・軽減するためにある行動が有効だった場合、その行動は何度も繰り返し定着することになります。
組織の発展プロセス
組織の発展プロセスは、以下の通り、漸次的進化過程と革新的変革過程があります。
漸次的進化過程
組織の発展プロセスにおいて、比較的安定した段階における連続的な進化のプロセスであり、絶えず漸次的な修正や改善が行われています。
革新的変革過程
組織が危機に直面した際、不連続な変化にて別の段階に移る状態のことであり、外部環境の劇的な変化などがおこると、戦略や組織の再構築を行うようなケースなどがあります。
組織学習のレベル
組織学習には、「低次学習」と「高次学習」の2種類があります。
低次学習
低次学習には、「単なる行為の繰り返し」「部分修正」などの特徴があります。
シングルループ学習(所与の条件の中でエラーのみ修正する学習)も、低次学習の主要な特徴です。
高次学習
高次学習には、「組織全体に影響する学習」「規範や認知枠組みなどの変化をもたらすような学習」などの特徴があります。
ダブルループ学習(既存の価値や目標、政策などの文脈を超えて、それらのものの修正を伴う学習)も、高次学習の主要な特徴の1つです。
なお、組織の発展プロセスとの関係を考えた場合、低次学習は、組織の漸次的進化過程にて行われます。
一方、高次学習革新的変革過程にて行われます。
ただし、高次学習が実行されるのは難しいものです。そのため、組織においては低次学習が実施されやすいという実情があります。
組織の学習サイクル
組織学習は、各構成員を介在し、以下のプロセスにて実行されます。
①ある組織行動がもたらした環境の変化(結果や成果)を個人が知覚し、観察・分析する。その結果、個人の信念や知識に修正が加えられる。
↓
②個人が学習した成果により、個人の行動が変化する。
↓
③各個人の行動が変化し、組織の行動も変化する。
↓
④新たな組織の行動は、新しい成果や結果を生み出す。
安定的な段階に組織がある時、この組織の学習サイクルは不安定になりがちといわれています。
学習サイクルが不安定となる要因
組織の状態が安定的な場合、組織の学習サイクルの各移行時において、それぞれうまく移行できないケースが発生することがあります。これには、次の4つの理由があります。
①曖昧さのもとでの学習
なぜ環境が変化したのか、その理由を適切に解釈できないケースであり、そのため個人の信念が修正されず、あるいは、間違った修正がされてしまうケースです。
②役割制約的学習
組織の役割や規定、手続き等の決まりごとが障害となり、個人が自分の思いどおり行動ができないケースです。
③傍観者的学習
個人の学習成果が組織の新たな行動に活かせないケースです。
④迷信的学習
組織の行動、そして、結果としての環境変化の間における因果関係を適切に理解できないケースです。
まとめ
以上、組織学習の解説でした。
実は、この「組織学習」の出題のタネ本は、試験委員の桑田先生の著書になります。そちらについては以下の記事に書いてますので、よろしければチェックしてみてください。

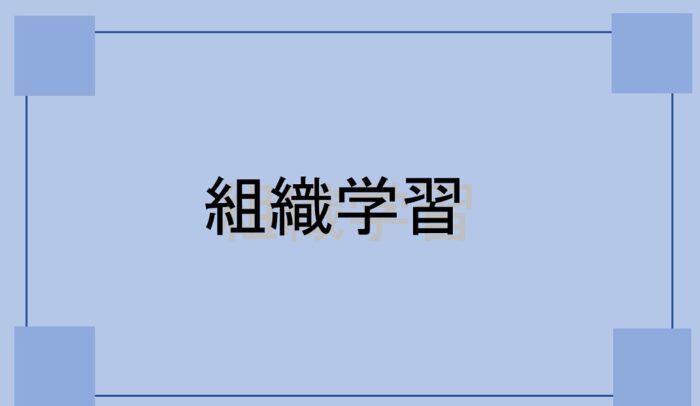
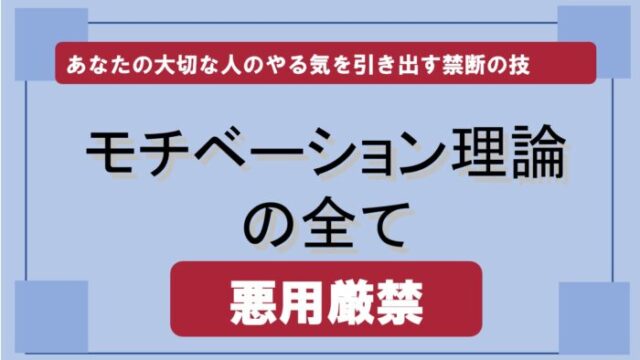
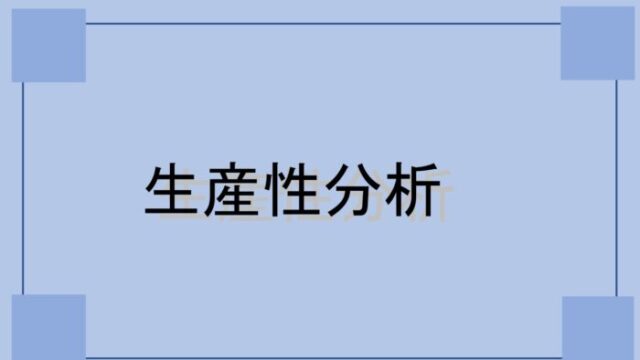

![企業の社会的責任[CSR]](https://shindan-model.com/wp-content/uploads/2021/10/S858-001-002-320x180.jpg)