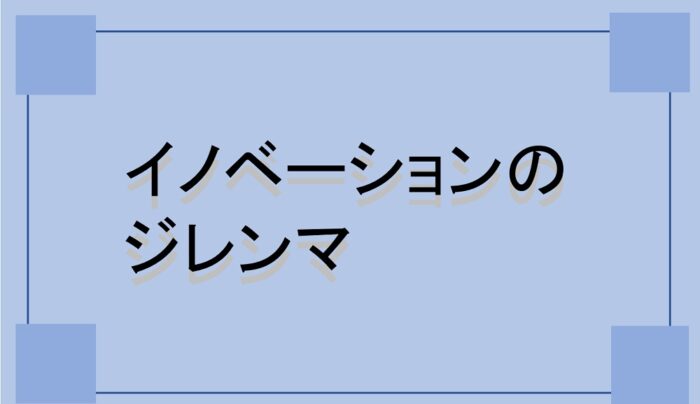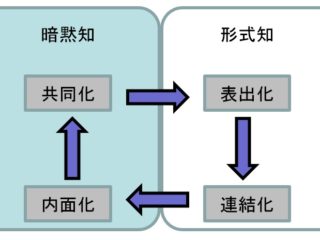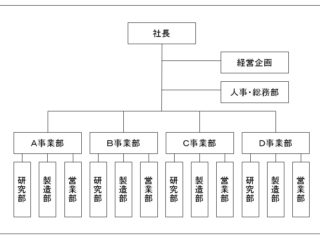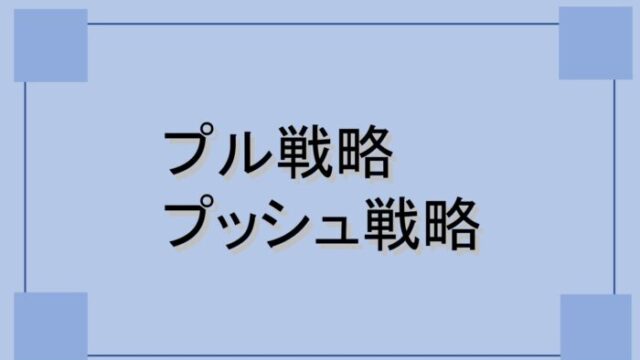今回は、「イノベーション」がテーマです。
イノベーションという言葉は、よく耳にするのではないでしょうか? 日本語では「革新」という意味です。
しかし、「イノベーション=革新」と言われても、いまいちピンと来ない方も多いのではないでしょうか?
また、企業で働いているビジネスマンの方は、
「イノベーション、イノベーション!」
などと、「何とかの一つ覚え」みたいに連呼する上司がいて、面倒くさかったりするのではないでしょうか?(笑)
今回は、そんな
「よく聞く言葉だけど、いまいち実体がよく分からない”イノベーション”」
について、説明していきたいと思います。
イノベーションの定義
前述のとおり、「イノベーション=革新」なわけですが、もう少し詳しく説明すると、
イノベーションとは、「新しく発明された技術」や「新たな技術的革新」のことであり、さらに、
「企業や組織が、そのような新たな技術を使って価値ある商品・サービスなどを作り上げる過程(プロセス)」
もイノベーションに該当します。
経済学者のシュンペーターは、
『イノベーションとは、「新結合の遂行」である』と位置づけました。
シュンペーターが述べた「新結合」とは、次の5つになります。
イノベーションの定義 ~シュンペーターの「新結合」とは?
①新しい製品・サービスの提供、あるいは、製品・サービスの新しい品質を作り出すこと
②新しい生産方法を導入すること
③新たな組織を創り出すこと
④製品・サービスの新たな販売マーケットを開拓すること
⑤新しい原材料の買い付け先を開拓すること
イノベーションの4類型
イノベーションには、大きく4つに類型化ができます。
イノベーションの類型(1) プロダクトイノベーション
新たな製品・サービスを生み出すイノベーションです。
イノベーションの類型(2) プロセスイノベーション
これまでの製品・サービスの生産方法に関するイノベーションです。
イノベーションの類型(3) 持続的イノベーション
インクリメンタルイノベーションとも呼ばれます。現状の技術を積み重ねた、継続性のあるイノベーションです。
イノベーションの類型(4) 破壊的イノベーション
ラディカルイノベーションとも呼ばれます。
従来の技術とは異なる、まったく新しい価値や知識によるイノベーションです。当初は未成熟であり、現状技術には及ばないことが多いですが、将来、現状技術を破壊するような、大きな革新となるポテンシャルを秘めている技術もあります。
イノベーションのジレンマ
イノベーションのジレンマとは、現在のリーダー企業が陥りがちな罠とも言える者です。
ある業界において、現在のリーダー企業は、既存顧客の多くから支持を得ています。
つまり、既存製品の改良を繰り返す「持続的イノベーション」に取り組むことが多くなります。
もちろん、そのような「持続的イノベーション」を実施することも大切ですが、持続的イノベーションばかりに気を取られていると、
その業界を大きく変えるような、あらたなイノベーション=「破壊的イノベーション」への取り組みが遅れてしまうことになります。
その結果、次世代技術が市場の主流になるころには、市場で生き残れなくなるか、或いは撤退することになってしまいます。
イノベーションのジレンマ 事例
かつてソニーは、「トリニトロン」という、競争力のあるブラウン管ディスプレイの技術を保持していました。
ソニーは、そのトリニトロンの技術に注力するあまり、液晶ディスプレイ技術への取り組みが遅れていました。
その結果、ディスプレイ市場において、ブラウン管から液晶へと大きく技術革新が起こった際、ソニーは液晶技術への本格参入が遅れてしまいました。
※イノベーションのジレンマについては下記動画でも詳しく説明しています。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |