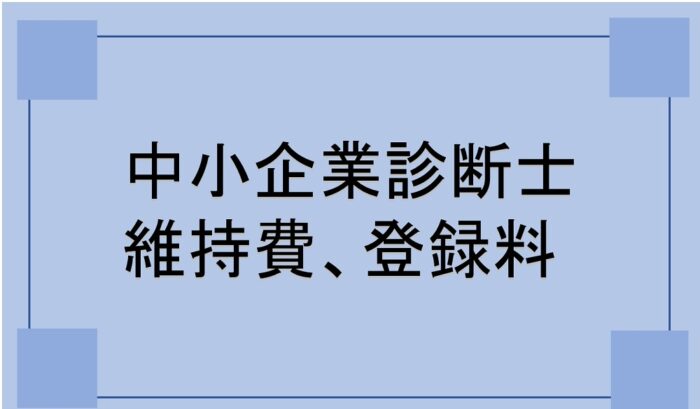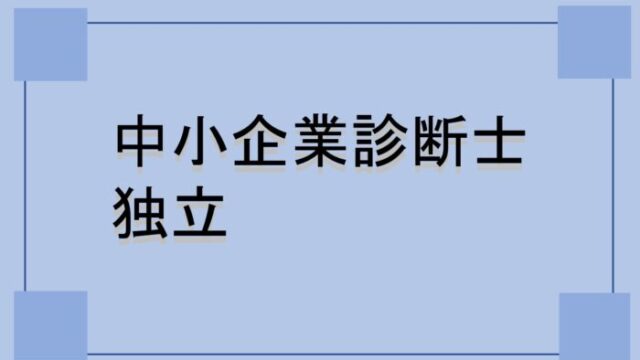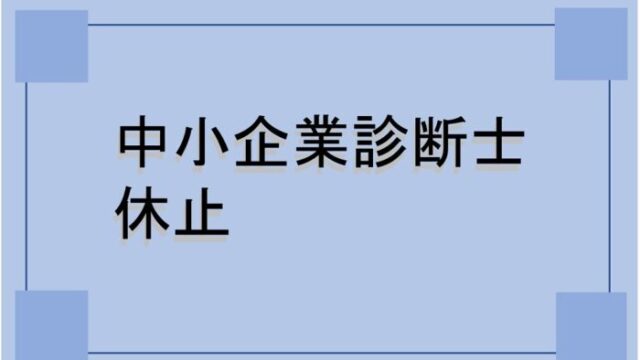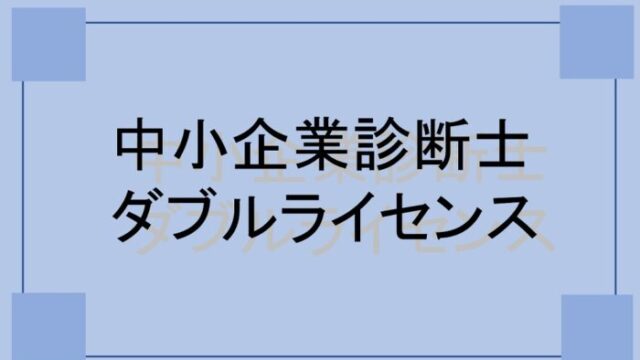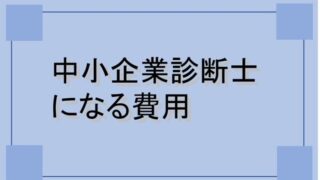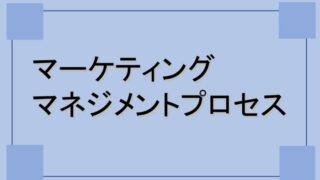こんにちは、トシゾーです。
この記事では、中小企業診断士資格の取得をはじめ、資格登録、そして資格維持費まで、「実際に、必要となる費用」に関して、ご説明していきます。
ご存じの通り、中小企業診断士試験はかなり難関なので、「費用も、かなり掛かるのでは?」と、資格取得を躊躇している方もいるかも知れません。
ここでは、必要な費用を分かりやすく説明しますので、ぜひ参考にして欲しいと思います。
目次
中小企業診断士の資格取得費用はどのくらい?
まず、資格取得までにかかる費用です。
中小企業診断士の資格取得費用は、「どのような方法(ルート)で資格を取得するか」という選択により、変わってきます。
どのようなルートを選んだ場合でも、最初に以下の第1次試験(全部で7科目)を突破しなければならないことは、変わりません。第1次試験の受験手数料は13,000円です。※令和4年から14,500円になりました。
第1次試験に合格した後は、中小企業診断士第ニ次試験を受けるか、中小企業基盤整備機構あるいは登録養成機関が開催する養成課程を受講するか決めます。
第2次試験の受験手数料は17,200円となります。※令和4年から17,800円となりました。
一方、第1次試験の後に中小企業診断士養成課程を受講すれば、第2次試験や実務補習が免除されるのがメリットです。
しかし、養成課程の受講料は100万円以上と非常に高く、300万円以上がかかる学校も少なくありません。
つまり、中小企業診断士養成課程の受講は必然的に資格取得費用も高くなるわけです。
養成課程について詳細は、下記の記事を参考にしてください。
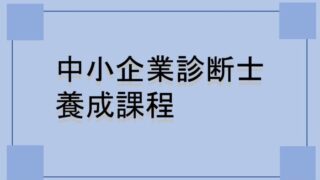
一方で第2次試験を受ける場合は、合格した後に次のいずれかを実施しなければなりません。
- 15日間以上の診断実務
- 15日間以上の実務補習
診断実務(実務従事、コンサル業務)に15日間以上従事するのであれば、特に費用はかかりません。ただし、診断実務先のクライアント企業は、自ら見つけてくる必要があります。
2次試験の受験手数料だけで、中小企業診断士の資格が取得できますよ。
一方、中小企業診断士の第2次試験を受けた後に15日間以上の実務補習を受ける場合は、約15万円の受講料を支払わないといけません。
実務補習のほうは、中小企業診断協会が準備するコンサル実務のトレーニングのため、有償なのです。
中小企業診断士養成課程よりも資格取得費用は安いのですが、15日間以上の診断実務従事を行うルートと比べてみると金銭的な負担は大きくなります。
※実務補習と実務従事(診断実務)について詳細は、下記の記事を参考にしてください。
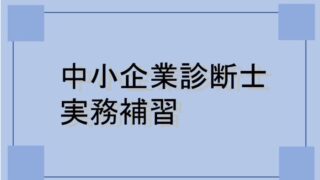
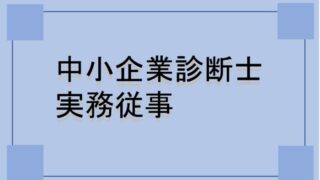
資格取得のための受験勉強にかかる費用はどのくらい?
ここまで、資格取得に必須な費用を見てきました。もっとも一般的なルートである「1次試験+2次試験+実務補習」のケースだと、約18万円の費用がかかることが分かったと思います。
ただし、この金額には、資格試験に合格するための受験勉強にかかる費用は含まれていません。
さすがに、中小企業診断士ように難易度の高い試験であれば、受験勉強にも、それなりの費用がかかります。
独学の場合でも、テキスト購入費が4~5万円程度必要ですし、大手資格予備校に通学するとなると、25~30万円以上のコースが普通です。
最近では、スマホ対応動画講義の付属した通信講座(オンライン講座)が増えて来ていますが、こちらは、独学と同程度の4~5万円から始められるため、急速に人気が高まっています。
以上が、中小企業診断士の資格取得にかかる費用です。
弁護士や公認会計士、医師などの超難関試験ほどではないですが、資格取得のためには、決して安くはない費用が掛かることがお分かりかと思います。
※低価格なオンライン講座をお探しの場合は、下記を参考にしてください。


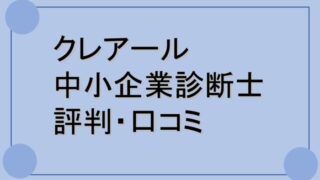
中小企業診断士資格、登録するための費用はどの程度?
試験合格、そして実務補習(実務従事)修了後、経済産業大臣に登録が完了すれば、正式に中小企業診断士となります。
「経済産業大臣登録」については、登録料は不要です。
また、中小企業診断士は、他の多くの士業と違って、業界団体(中小企業診断協会)に入会することも強制されません。
つまり、登録費用はゼロ円となります。資格取得までにお金がかかるので、非常に嬉しく感じたことを覚えています(個人的な感想です^^)。
※ただし、予算が許すならば、新人の頃は中小企業診断協会に入るメリットは大きいです。詳しくは後述します。
中小企業診断士の資格の維持費はどのくらい?
続いて、資格を維持する費用をチェックしましょう。
他の士業と比較してみると、中小企業診断士の資格の維持費は安いのが特徴です。
他の士業だと、税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士などは独占業務があるからなのか、開業して士業として活動するためにはそれぞれ士業団体(業界団体)に入会して会員になることが必須です。たとえば行政書士などは年間会費が平均して合計20万円以上とも言われ(正確には都道府県で異なります)、馬鹿にならない高額な費用ですよね。
中小企業診断士の場合は、中小企業診断協会の入会も任意ですから、その点だけでも違います。
それでも、中小企業診断士は5年間ごとに更新が必要ですので、どのくらいの維持費がかかるのかしっかりと心得ておいた方が良いでしょう。
※中小企業診断士の更新手続きの詳細については、下記記事も参考にしてください。
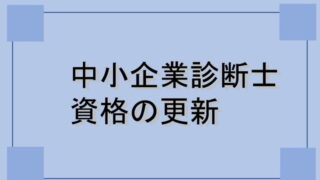
次項、中小企業診断士の更新手続き別で資格の維持費についてまとめてみました。
維持費(その1):知識の補充の要件を満たすための費用
中小企業診断士の資格更新では、知識の補充の要件を満たす必要があります。
知識の補充の要件を満たすのは4時間の理論政策更新研修で、登録有効期間の5年間のうちに5回修了しないといけません。
中小企業診断士の理論政策更新研修で学ぶテーマの例をいくつか挙げていきます。
- 新しい中小企業政策について
- 飲食店のコンサルティング/補助金活用の実態
- 診断士が知っておくべき創業融資を活用するノウハウ
- 人材を確保するための組織マネジメント講座
- 中小企業の海外展開支援
- 中小企業の事業承継支援
- 中小企業の人材活用や育成支援
- 士業のための戦略的Webマーケティング実践講座
- 経営力強化に繋がる知的資産経営の進め方
- ローカルベンチマークを活用した中小企業支援
- 総合経営支援(SMASH)によるS社の経営革新事例
中には中小企業診断士の業務で本当に勉強になる研修もありますので、しっかりと受講したいところですね。
理論政策更新研修は、各都道府県の診断協会支部が開催する研修でも、中小企業庁登録研修機関の実施するものでも、値段は変わらず1回当たり6,000円がかかります。
5年間に5回の理論政策更新研修を受ける形になりますので、中小企業診断士の資格の維持費はトータルで3万円というわけです。
研修に行く時間がない時は、与えられたテーマの論文を提出する理論政策更新論文を選択できます。
しかし、理論政策更新論文の費用(受信料)も6,000円ですので、中小企業診断士の維持費の節約にはなりません。
維持費(その2):実務の従事の要件を満たす費用
中小企業診断士のもう一つの更新要件は、実務の従事です。
次のいずれかを5年間で30点取得すると、中小企業診断士の資格を更新できます。
- 中小企業者に対する経営診断や助言診断(1日1点)
- 実務補習または養成課程の実習の指導
中小企業診断士の仕事に携わっていて普段から中小企業の支援をされている方は、その業務がそのままポイントとなります。
クライアントから証明書に署名や捺印をもらえれば、実務従事の要件を満たすことができます。
自分で対象企業を見つける形になりますので、更新の費用は0円で資格の維持費はかかりません。
しかし、企業勤めをしている企業内診断士は日々の生活で中小企業へのコンサルティングをしていないため、支援先が見つからない時があります。
そういった場合は中小企業診断協会などが実施する実務従事に参加することになりますが、その場合、25~30万円程度の費用が必要となります。
5年間で25~30万円なので、1年あたり5~6万円程度の計算になりますね。
維持費(その3):中小企業診断協会の入会金・会費(任意)
前述のとおり、中小企業診断協会の入会は完全に任意です。他の士業のように「入会しないと〇〇士を名乗れない」などは一切ありません。
中小企業診断協会へは、任意の都道府県協会に入会することになります。各都道府県協会によって詳細は異なりますが、おおむね「入会金5万円 + 年会費5万円」が相場となっています。新規入会から5年間で30万円といったところです。
中小企業診断協会への入会は任意・有償とはいえ、新人中小企業診断士にとっては、診断士同士の人脈作りも含めてかなりメリットはありますので、予算が許すようであれば検討してみてください。
※中小企業診断協会の先輩方からの紹介仕事などが多くありますから、やる気さえあれば、年会費の回収ぐらいは余裕でできてしまいます(私自身がそうでした。私が入会した東京都中小企業診断協会の支部では、入会して献身的に活動した結果、初年度で二十万円程度の仕事の紹介を受けることができました)。
診断士登録したばかりの初回1年だけでも経験しておくのは悪くないと思います。
※中小企業診断協会については、私の経験談も含めて下記にくわしく説明していますので、よろしければ参考にしてみてください。
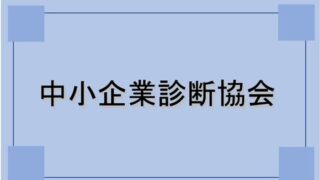
維持費(その4):自己研鑽のための投資(任意)
この項目は、中小企業診断士の資格の維持で絶対に必要な費用ではありません。
しかし、経営コンサルタントとして独立して成功するには、中小企業診断士の資格を取得したり更新したりするだけではなく、専門知識を磨くなど自己研鑽のための投資が必要になります。
中小企業診断士の基本的な業務は、中小企業経営者のパートナーとして企業が抱える問題や課題の解決です。
相談相手の経営者が満足するには企業経営に関する知識に加えて、様々な面からの知識やスキルが求められます。
つまり、中小企業診断士としてスキルアップするために、独学で教養をつけたりセミナーに参加したりといった対策を行いましょう。
継続的な自己研鑽では一定の維持費がかかりますが、中小企業診断士の仕事に必ず活きてきます。
まとめ
以上のように、中小企業診断士の資格取得費用や登録費用、維持費について詳しくまとめました。
中小企業診断士の資格取得のためには、それなりの費用が掛かります。
しかし、登録は無料ですし、5年間に1回のペースで資格の更新が必要なものの、他の士業と比べると更新の維持費は安く、金銭的な負担は少なくなっています。
中小企業診断士は様々な業界で活かせますので、資格取得のための勉強を始めてみてください。
| 著者情報 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |